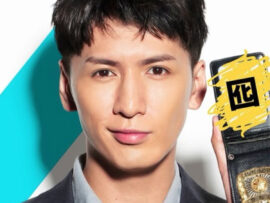近年、ウェブニュースで話題になることは多いものの、本業の野球では長らく低迷から抜け出せない状況が続く中日ドラゴンズ。しかし、昭和のプロ野球ファンにとって「燃える男」と称された星野仙一氏が指揮を執った時代は、今なお色褪せることのない懐かしい記憶として残っています。彼の熱い魂がチームを牽引し、数々のドラマが生まれたその時代は、中日ドラゴンズ史において特別な輝きを放っていました。本稿では、別冊宝島編集部の『永久保存版 嗚呼、青春の昭和プロ野球 心震えた名場面とその舞台裏』から一部を抜粋・編集し、伝説的な「星野がいた時代」の象徴ともいえる熱血エピソードを深く掘り下げて振り返ります。
 「燃える男」として中日ドラゴンズを率いた星野仙一氏。彼の情熱がチームを動かした時代を象徴する一枚。
「燃える男」として中日ドラゴンズを率いた星野仙一氏。彼の情熱がチームを動かした時代を象徴する一枚。
伝説の始まり:宇野勝「ヘディング事件」の舞台裏 (昭和56年)
星野仙一氏が中日ドラゴンズのエースとしてマウンドに君臨していた昭和56年、プロ野球史に残る衝撃的な出来事が発生しました。当時、宿敵である巨人打線を6回までわずか2安打無得点に抑え込み、中日の2点リードで迎えた7回裏、二死二塁の場面。この日無安打だった松本匡史選手に代わって打席に入った山本功児選手の打球は、力なくショート後方へ上がるポップフライとなりました。
中日の遊撃手、宇野勝選手が後退しながら捕球体勢に入ると、星野氏はアウトを確信し、悠々と自軍ベンチへ戻りかけていました。しかし、次の瞬間、球場全体が息をのむ事態が発生します。宇野選手はまさかの捕球失敗。打球は彼の右側頭部を直撃し、大きく跳ね返ってレフトフェンス際まで転がっていったのです。頭を抱えてうずくまる宇野選手を目の当たりにした星野氏は、一瞬呆然と立ち尽くしましたが、すぐさま本塁後方へ猛然とバックアップに走ります。その目前を、二塁走者の柳田真宏選手がホームへと駆け抜けていきました。
珍プレーの誕生と国民的ブーム
山本功児選手は本塁で刺殺され、同点は免れたものの、星野氏は自身の連続得点試合記録を阻止されたことに激昂し、グラブを地面に叩きつけました。この後、試合は両軍無得点のまま中日が2対1で勝利を収めます。試合後、「後でカラダ空けとけ!」と怒り狂う星野氏に対し、宇野選手が「空いてません」と必死に逃げたという逸話は広く知られていますが、実はこれは一部事実とは異なるようです。
当時の宇野選手は、チームが勝利したこともあり、自身のエラーをそれほど重大な事態とは捉えていなかったといいます。彼自身は、星野氏からの食事の誘いを、たまたま上京していた実兄との先約があったため断っただけ、と認識していたのです。しかし、このプレーはフジテレビの『プロ野球ニュース』で、みのもんた氏のナレーションによって「珍プレー」として放送されるやいなや、全国的な大反響を呼びました。そしてシーズン終了後には、特番『プロ野球珍プレー・好プレー大賞』が放送され、宇野選手はこの「ヘディング事件」によって“珍プレーの元祖”としてゲストに呼ばれるまでになったのです。
時代を超えて語り継がれる熱血の記憶
宇野選手の「ヘディング事件」は、星野仙一氏の情熱的なプレースタイルと、当時のプロ野球が持っていた人間味溢れる魅力を象徴する出来事として、多くのファンの記憶に深く刻まれました。星野氏の「燃える男」としての姿は、単なるプレーだけでなく、グラウンドでの喜怒哀楽、そして選手との人間関係を通じてファンを魅了し続けました。
このエピソードは、単なるエラーという事実を超え、昭和のプロ野球における「熱血」と「ドラマ」の象徴として語り継がれています。現代のプロ野球がシステム化・戦略化される中で、星野仙一氏が体現したような情熱は、今もなお多くの野球ファンが求める「野球の面白さ」の原点なのかもしれません。中日ドラゴンズの未来を語る上で、この熱血時代を忘れることはできないでしょう。
参考文献
別冊宝島編集部『永久保存版 嗚呼、青春の昭和プロ野球 心震えた名場面とその舞台裏』