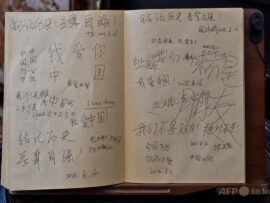2025年に創業100周年を迎える解熱鎮痛薬「ケロリン」。長年にわたり日本の家庭薬として親しまれる一方で、そのユニークな広告媒体として知られる「ケロリン桶」は、多くの人々に愛される存在となっています。この象徴的なブランドの魅力について、銭湯研究家の町田忍氏とタレントの壇蜜氏が、それぞれの視点から深い想いを語りました。本稿は、監修・笹山敬輔氏による『ケロリン百年物語』(文藝春秋)から一部を抜粋・編集したものです。「ケロリン」がどのようにして日本の庶民生活に深く根差し、文化の一部となったのかを探ります。
 銭湯研究家・町田忍氏とタレントの壇蜜氏が解熱鎮痛薬「ケロリン」について語る
銭湯研究家・町田忍氏とタレントの壇蜜氏が解熱鎮痛薬「ケロリン」について語る
「銭湯研究」の原点:ケロリン桶との出会い
銭湯研究家として知られる町田忍氏は、「ケロリン桶」との出会いを昭和30年代後半の中学生時代に遡ります。当時、行きつけの銭湯で木桶が黄色い「ケロリン桶」に変わる瞬間に立ち会ったことで、その存在と鎮痛薬「ケロリン」を知ったといいます。
町田氏が本格的に銭湯巡りを始めたのは1980年代に入ってからです。ある時、日本に滞在していたオーストラリアの友人を日本の庶民生活を体験させようと銭湯に連れて行ったところ、その銭湯が「宮造り」の建築様式であったことに友人が驚き、「なぜ銭湯は、お寺や神社のようなのか」と興味深い質問を投げかけました。この問いがきっかけとなり、町田氏は日本の銭湯文化が失われる前に記録を残すべきだと感じ、銭湯の写真を撮り始めます。地元である目黒区から調査を開始し、やがて全国へと範囲を広げていく中で、どこの銭湯にも「ケロリン桶」が置かれていることに気づき、その普及度合いに興味を抱きました。この関心から、内外薬品の本社を訪れ、当時の社長であった笹山和紀氏に直接インタビューを行うに至ったのです。
時代を映す「ケロリン桶」の進化と魅力
「ケロリン桶」が誕生したのは昭和38年(1963年)ですが、その普及を後押しした大きな時代背景として、翌年の昭和39年(1964年)に開催された東京オリンピックが挙げられます。この時期は、プラスチック製品が広く普及し始めた時代と重なります。「木の桶」に比べてメンテナンスが不要なプラスチック製の桶は、当時の合理化の波にも乗り、新しい時代の素材を象徴する存在となりました。白い「ケロリン桶」も一時存在しましたが、黄色い桶こそが「ケロリン」のイメージとして定着しています。黄色は目立つだけでなく、薬品のイメージにも合致するため、広告媒体として非常に効果的でした。
さらに、桶に書かれた「ケロリン」の文字には特別な技術が施されています。浴室という過酷な環境下でも文字が消えないよう、黄色いプラスチック樹脂の中に特殊なインクを染み込ませる方法が開発されたのです。当時、東京駅前にあった人気の温泉施設「東京温泉」に「ケロリン桶」が置かれた際には、その斬新さが話題を呼びました。「ケロリン桶」は銭湯だけでなく、温泉施設やゴルフ場などにも置かれ、その高い広告効果を発揮しました。町田氏は30年以上前から「ケロリン桶」を収集しており、現在では新品が手に入る一方で、廃業する銭湯から譲り受けることも多いといいます。
粉末薬「ケロリン」の誕生秘話と愛される理由
「ケロリン」の薬自体にも、町田氏は銭湯巡りを始めた頃から改めて着目するようになりました。特に薬局で目にしたパッケージデザインに感銘を受け、その歴史を調べ始めたのです。「ケロリン」がここまで売れた最大の理由は、その「粉末」という形状にありました。昭和初期、主流だった鎮痛剤は液体タイプが多く、持ち運びに不便でした。そこに登場したのが、持ち運びに便利な粉末状の「ケロリン」です。
そのネーミングも秀逸で、「ケロッと治る」という語呂合わせから「ケロリン」と名付けられました。その絶大な人気ゆえに、当時多くの偽物が出回ったというエピソードも残っています。「ケロリン」はパッケージデザインは大きく変わっていませんが、時代に合わせて中身の一部成分は改良されてきました。これは、ラーメンやチョコレートといった他のロングセラー商品と同様に、消費者のニーズや科学技術の進歩に対応してきた証と言えるでしょう。
日本の日常に息づく文化遺産
解熱鎮痛薬「ケロリン」と、その広告媒体である「ケロリン桶」は、単なる商品としてだけでなく、日本の庶民文化や歴史を映し出す貴重な存在です。銭湯文化とともに歩み、素材の変化や技術革新を取り入れながら、時代を超えて愛され続けてきました。町田忍氏の語りからは、「ケロリン」がいかに人々の記憶に深く刻まれ、日常風景の一部として親しまれてきたかが伝わってきます。100周年を迎える「ケロリン」は、これからも日本の生活に寄り添う、生きた文化遺産としてその歴史を紡いでいくことでしょう。
参考文献
- 監修・笹山敬輔『ケロリン百年物語』文藝春秋