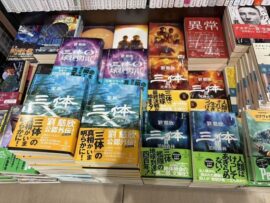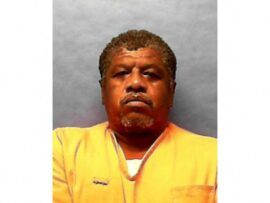2023年、神奈川県大磯町立小学校の校長(当時)がいじめの加害児童に対し、3週間の「校長室登校」を命じた問題で、町教育委員会は8月23日、「不適切だった」と公式に認めたと東京新聞が報じました。この措置により、児童は授業や給食をすべて校長室で過ごすことになり、「嫌だ」と訴え、保護者も中止を求めたにもかかわらず、結果的に不登校となり、復学することなく卒業に至っています。校長は既に依願退職していますが、町教委への事前の相談はなかったとされます。一方で、SNS上では「なぜ不適切なのか分からない」「いじめが事実なら妥当な指導だ」といった意見が多数寄せられており、この校長権限による措置の法的な妥当性について、学校問題に詳しい高島惇弁護士に見解を伺いました。
 いじめ問題における校長室登校と別室指導の法的解釈
いじめ問題における校長室登校と別室指導の法的解釈
「別室授業」は一概に「不適切」ではない:いじめ対策としての法的根拠
公立学校において、いじめが発生し、被害児童が安心して教育を受けられない状況が生じた場合、「いじめ防止対策推進法」第26条に基づき、学校は出席停止措置や別室指導といった必要な措置を講じることが可能です。したがって、いじめの程度、被害状況、特に被害児童の登校状況にもよりますが、加害児童を校長室で別室授業としたこと自体が、直ちに不適切指導と評価されるものではありません。
別室指導は、公立・私立学校問わず毎年多数実施されているのに対し、出席停止措置が講じられるケースは非常に少ないのが実情です。文部科学省が毎年公表している「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によれば、ここ数年、出席停止の件数は年間で一桁台に留まっており、特に小学校では年間1件あるかないかという状況です。これは、出席停止措置を講じるには保護者からの意見聴取や理由を記載した文書交付など、煩雑な事務手続きが必要であるため、より迅速かつ柔軟に対応できる自宅謹慎措置や別室指導が主に用いられるという背景があります。
これらの措置はすべて「教育的指導」として行われるため、「学校教育法」第11条に定める「懲戒」とは性質が異なり、小中学生に対して禁止されている「停学処分」にも形式的には該当しません。教育的観点からなされる措置であることから、校長の裁量はより広範に設定されており、児童や保護者の意に反して行われたとしても、児童へ罰を与えることを目的としたものではないため、法律上は特に問題がないと理解されています。
大磯町教育委員会が「不適切だった」と判断した背景には、児童が不登校に至り、最終的に復学することなく卒業したという深刻な結果や、保護者の意向が尊重されなかったことなど、教育的配慮の側面が大きく影響していると考えられます。しかし、法的な枠組みの中では、いじめ問題に対する別室指導そのものが直ちに違法となるわけではないという点が重要です。
参考文献
- Yahoo!ニュース: いじめ加害児童に「校長室登校」は不適切指導か? 弁護士の見解は(2023年8月28日)
https://news.yahoo.co.jp/articles/b4f8ee098ccbda57e5af59f544fa125b67b60185