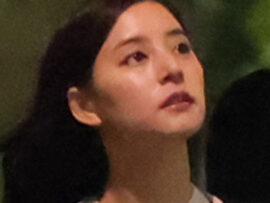英国の有力シンクタンク「王立防衛安全保障研究所」(RUSI)に掲載された英空軍スチュアート・グレゴリー大佐の論考は、日英両国間で「次世代型防衛能力」が着実に蓄積されている現状に警鐘を鳴らしています。グレゴリー大佐は、この動きが安全保障における米国の主導権に対抗しうるものと見なされる可能性を指摘し、日英関係が事実上「同盟」に近い形態へと進化しつつあることを示唆しています。米国が両国にとって最大の同盟国である以上、その信頼関係を損なわずに協力関係を深化させるための慎重な調整が急務とされています。
「経済版2+2」で強化される日英関係
今年3月、東京で初めて「日英経済版2+2」閣僚会合が開催されました。この会合には、日本側から外務大臣と経済産業大臣、英国側から外務大臣とビジネス・通商大臣が出席し、貿易、経済安全保障、外交分野における対話が促進されました。英国は、インド太平洋地域を経済と安全保障の両面で極めて重要視しており、日英関係を「強化されたグローバル戦略的パートナーシップ」と再定義しています。会合では、次世代量子コンピューティング開発におけるサプライチェーン協力、軍事転用可能な物質・技術の輸出管理強化、洋上風力発電、先進ロボット技術、自律システム分野での協力が確認され、両国の包括的な協力姿勢が鮮明になりました。
 日英両国の要人が会談し、防衛・経済協力の強化を議論する様子
日英両国の要人が会談し、防衛・経済協力の強化を議論する様子
第6世代戦闘機プログラム(GCAP)と防衛産業
日英伊の3カ国が進める第6世代戦闘機プログラム(GCAP)は、2035年以降の本格生産・配備開始を目指す野心的な取り組みです。これは、ステルス戦闘機F-22などに課された米国の厳しい輸出制限を受け、西側諸国が対米依存度を低減し、自国の防衛産業基盤を強化するという喫緊の課題に応えるものです。この共同開発は、単なる技術協力に留まらず、各国の防衛能力と産業戦略に深く関わる戦略的な意義を持っています。
「準同盟」としての現在の日英防衛協力
グレゴリー大佐は、日英間の現在の一連の合意や準同盟的な枠組みについて、敵対国や同盟国が「かなり深く結びついた関係」と受け取る可能性を指摘しています。特に、包括的サイバーパートナーシップやGCAPといった枠組みには、相互に義務が伴うとされています。中国人民解放軍の台湾侵攻シナリオに日本の軍事施設や米軍基地の破壊が含まれる状況を鑑み、グレゴリー大佐は、英国が日本との「同盟関係にあることの意味を再認識し、日本に対する防衛義務を明確にする必要がある」と提言しています。これは、将来の有事における日英協力の具体的なあり方を問うものです。
変化する安全保障環境と米国の役割
アフガニスタンからの撤退、ウクライナ戦争、そして「米国第一主義」を掲げるドナルド・トランプ元大統領の再登場の可能性は、日本と英国に「米国主導の安全保障が必ずしも確実とは限らない」という疑念を抱かせる一因となっています。これにより、両国は独自の抑止力構築を模索せざるを得ない状況です。宇宙、電子戦、自律型兵器、人工知能(AI)といった分野において日英は互いに補完関係にあり、ハードパワー不足を補う可能性を秘めています。しかし、このような協力の深化は、必然的に米中両大国の注目を集めることになります。北大西洋条約機構(NATO)のような集団防衛メカニズムがアジア太平洋に存在しない中で、この地域における二国間同盟のほぼ全てが米国を巻き込んでいるという現状も、日英協力の調整を複雑にしています。
グレゴリー大佐は、日英間にまだ形式的な条約は存在しないものの、実質的には同盟に近い関係にあると結論付けています。今後の方向性として「日英条約型同盟」の検討が現実的であるとしながらも、その際には米国との信頼関係を損なわないよう、米国を含めた慎重な調整が不可欠であると強調しています。日英関係の進化は、世界の安全保障環境の変化に対応しつつ、既存の国際秩序との調和を図るという複雑な課題に直面しています。