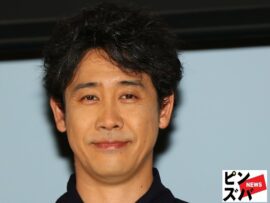近年、職場で「働かないおじさん」や「妖精さん」と揶揄されるミドルシニア世代のビジネスパーソンが増加しているという声が聞かれます。彼らが時に「窓際族なのに年収2000万円」を意味する「Windows2000」と呼ばれるのは、その存在感の薄さと年功序列による高収入の矛盾を指摘するものです。しかし、この現象は単なる個人レベルの問題にとどまらず、日本の労働市場が経験した歴史的な転換期と深く関連しています。
日本総合研究所が2024年に20代から60代までの2万400人の企業勤めの人々を対象に行った調査では、キャリアと組織の成長を自ら切り開く「プロアクティブ人材」の度合いを示すスコアが、40代、50代で最も低いという結果が示されました。このデータは、ミドルシニア世代の仕事に対するモチベーション低下が、個々人の意識の問題だけでなく、より広範な社会経済的背景によって引き起こされている可能性を示唆しています。
 法政大学キャリアデザイン学部教授、田中研之輔氏の肖像。日本のミドルシニアのキャリア課題について語る。
法政大学キャリアデザイン学部教授、田中研之輔氏の肖像。日本のミドルシニアのキャリア課題について語る。
「働かないおじさん」化するミドルシニア世代の背景
法政大学キャリアデザイン学部の教授であり、『これからのキャリア開拓』の共著者である田中研之輔氏は、ミドルシニア世代が「働かないおじさん」化する要因を「戦後、働き方の歴史的転換に直面した初めての世代だから」と指摘しています。これは、彼らが従来の働き方と新たな働き方の間で、複雑な状況に置かれていることを意味します。
「組織内キャリア」から「自律型キャリア」への変遷
田中教授によれば、現在のミドルシニア世代より上の世代は、企業や組織に自身のキャリアを委ね、終身雇用制の下で組織が敷いたレールに沿って定年を迎える「組織内キャリア」が一般的でした。一方、ミレニアル世代やZ世代といった下の世代では、長期の景気低迷、企業や組織の変革、転職に対する社会的な意識の変化などが進み、企業に依存せず主体的にキャリアを開拓する「自律型のキャリア」が当たり前になっています。学校でのキャリア教育も始まり、キャリアに対する意識は大きく様変わりしました。
経済変動と「就職氷河期」の影響
現在の40代から50代は、まさにこの「就職氷河期世代」と重なります。彼らは経済不況の影響を真正面から受け、その経験が現在のモチベーションに深く影を落としています。田中教授は「今の40代〜50代は、経済不況の影響をもろに受けてきた。同じ組織内キャリアを歩んできたものの、経済が上り調子で、社会に出てから順調に収入もウェルビーイングも向上していった上の世代とは異なり、それらを享受できていない。組織内キャリアの矛盾を、体感してしまったわけです」と述べています。
就職氷河期には、大卒者の就職率が1999年から2004年度にかけて50%台まで落ち込むなど、深刻な状況にありました。この時代の影響は、現在もミドルシニア世代の年収が上がりにくいことや年金への不安といった形で付きまとっています。彼らは、時代と世代の狭間で社会の変化に戸惑い、その結果としてモチベーションの低下を招いているのです。
日本総研の調査による年代別プロアクティブスコアのグラフ。40代、50代のスコアが低い傾向を示す。
挑戦への意識と労働組合活動の変化
田中教授は「学校から社会に出ていく転換期につまづいたのが、氷河期世代。その経験が大きなチャレンジはしない方がいいという意識を生んでいる」と指摘します。この意識は、彼らの労働組合活動への向き合い方にも表れています。上の世代が春闘での賃金交渉などを通して、より良い待遇や職場環境を求めて「闘ってきた」のに対し、現在のミドルシニア世代が労働人口の中心となった近年では、共闘よりも「協調」の活動が顕在化している傾向が見られます。これは、組織や人事の意向に静かに対応し、波風を立てることを避ける、あるいは立てたくないという意識の表れであると田中教授は分析しています。
まとめ
「働かないおじさん」と称されるミドルシニア世代のモチベーション低下は、個人的な問題として片付けられるものではありません。彼らは、日本の労働環境が大きく変化する過渡期に生き、特に「就職氷河期」という困難な時代を経験したことで、キャリアに対する意識や行動様式が形成されてきました。従来の「組織内キャリア」の恩恵を十分に享受できず、かといって「自律型キャリア」へのスムーズな移行も困難な状況に置かれた結果、彼らの多くが仕事に対する意欲を失い、静かに現状に順応していると言えるでしょう。この世代が抱える課題を理解することは、現代日本の企業が人的資本経営を推進し、多様な人材が活躍できる職場環境を構築する上で不可欠です。