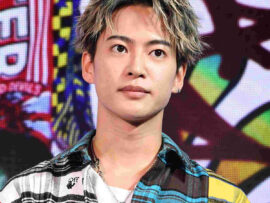日本国内で一定の「合格点」と評価された米日関税合意ですが、その内容、特に日本経済の主要産業である自動車分野の関税(15%)部分の曖昧さ、そして合意文書の不在が波紋を広げています。国会ではこの「口頭合意」を巡る与野党の激しい攻防が繰り広げられ、さらに交渉の舞台裏が次々と明らかになっています。
国会で問われる「口頭合意」の是非
4日、衆議院予算委員会に出席した石破茂首相は、野党からの自動車関税に関する質問攻勢に対し、「自動車関税を下げることに全力を注ぐ」と強調し、合意の意義を力強く擁護しました。しかし、最大野党である立憲民主党の野田佳彦代表は、合意文書が存在しない点を繰り返し指摘。「トランプ米政権が拡大解釈を続けることで、日本は不利益を被り続けるのではないか」と強い懸念を示しました。これに対し石破首相は、「文書を作成することで関税引き下げが遅れるということを一番恐れている」と反論し、文書化を避けた理由を説明しました。先月末にトランプ大統領が行政命令に署名し、日米間の関税交渉は一段落したとされますが、相互関税(15%)以外の、日本政府が最も重視した自動車および部品関連の部分は、口頭合意(15%)以外に具体的な文書がなく、野党からの批判の的となっています。
日米関税交渉の舞台裏:日経が報じた「計算式」の要求
こうした中、日米関税交渉の具体的な過程が徐々に明らかになっています。この日、日本経済新聞(日経)は、自動車関税交渉において米国が日本側に対し「計算式」の提示を求めていたと報じました。石破首相の側近である赤沢亮正経済再生担当相は、当初は明確な約束も得られないまま米国を繰り返し訪問し、ベッセント財務長官やラトニック商務長官らと協議を重ねました。訪問回数が増え「また来たのか」という声が聞かれるほどになると、米国の態度に変化が見られたといいます。米国側は日本に対し「協力」を求め、「全世界で使える計算式を考えてほしい」と具体的な宿題を突きつけました。これは、日本だけに関税を引き下げることは困難であるという米国の立場を示唆するものでした。これを受け、日本側は米国の現地生産台数などに基づき、各国にも適用可能な「統轄」関税率計算式を提案。この計算式によれば、日本の自動車関税は8%に引き下げられる見込みでした。日本はこの計算式を携え、6月のカナダG7(主要7カ国)サミットで石破首相がトランプ大統領と会談し、合意に至るという構想を描いていました。しかし、日経によると、トランプ大統領は「よりシンプルなもの」を要求し、この時点では合意には至りませんでした。
交渉の加速と最終合意の内訳
一時停滞状態にあった交渉が大きく加速したのは、約1カ月後のことでした。先月21日(現地時間)、赤沢経済再生担当相が米ワシントンを訪問した際に大きな進展が見られました。ラトニック商務長官の自宅で最終的な予行演習を終えた後、翌日にはトランプ大統領との間で合意に成功しました。この合意により、日本は5500億ドル(約81兆円)の対米投資を行うとともに、相互関税を25%から15%に引き下げ、自動車関税も25%から15%(既存の2.5%関税を含む)に引き下げることで合意しました。日経は、トランプ大統領が大富豪の性犯罪者ジェフリー・エプスタイン事件に言及しながら「米国側も合意を急いだ」と説明。日本との合意を早期にまとめることで、他の国との交渉にも弾みをつけ、実績をアピールしたいという理由から、米国が早期合意に積極的だったと分析しています。
 衆議院予算委員会で野党の自動車関税質問に答える石破茂首相
衆議院予算委員会で野党の自動車関税質問に答える石破茂首相
今回の米日関税合意は、一定の成果を収めた一方で、自動車関税の「口頭合意」という異例の形式が、今後の日米関係や日本の貿易政策にどのような影響を与えるのか、引き続き注目が集まります。政府は国民への丁寧な説明と、実効性のある合意履行に向けた明確な道筋を示すことが求められるでしょう。
参考資料
- 日本経済新聞
- Yahoo!ニュース