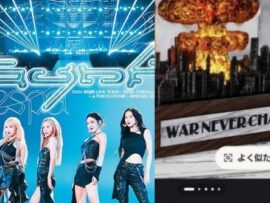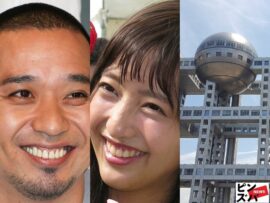1945年8月6日、広島の街は原子爆弾の壊滅的な猛威にさらされ、その年の暮れまでに約14万人の尊い命が失われました。この未曽有の災害は人命だけでなく、都市機能の中核を担っていたインフラにも甚大な被害をもたらしました。市民の重要な交通手段であった広島電鉄も例外ではなく、変電所の大部分が破壊され、保有する123両の車両のうち無傷だったのはわずか3両という壊滅的な状況に陥りました。
しかし、驚くべきことに、被爆当日には宮島線の一部区間が復旧し、その後わずか3日で市内線の一部も運行を再開しました。さらに、2度の大型台風に見舞われながらも、同年10月には広島駅までの大動脈が単線ながらも復旧を果たすという、まさに「奇跡」と呼べる速さでの復興を遂げました。一体なぜ、広島電鉄はこれほどまでの迅速な復旧を成し遂げることができたのでしょうか。その裏側には、歴史の表舞台にはほとんど語られることのない、多くの「名もなき人々」の知られざる奮闘がありました。
本記事では、当時の広島電鉄電気課長を務めた松浦明孝氏の手記、その手記を基にした書籍『だから路面電車は生き返った』(南々社)の著者である元運転士の中田裕一氏への取材、そして広島電鉄の社史といった貴重な資料を紐解きながら、被爆後の広島電鉄が辿った復興の軌跡と、それを支えた人々の献身的な努力の全貌を明らかにします。
爆心地近くで止まらない復旧の意志
原爆投下により、広島市中心部は壊滅状態に陥りました。広島電鉄の施設も例外ではなく、多くの変電所が機能停止し、多数の路面電車車両が大破しました。しかし、このような絶望的な状況下にあっても、広島電鉄の復旧への強い意志は途絶えることはありませんでした。宮島線の一部が被爆当日中に復旧したという事実は、当時の関係者たちの並々ならぬ決意と、わずかに残されたリソースを最大限に活用しようとする不屈の精神を物語っています。
広島電鉄の復旧は、単なる交通インフラの再構築以上の意味を持っていました。それは、生き残った市民にとって、希望の光であり、日常を取り戻すための象徴でもあったのです。壊滅した都市の中で、再び電車が走る音は、人々に大きな勇気を与え、復興への活力を生み出す原動力となりました。
変電所復旧:電力再開への道
広島電鉄の早期復旧において、電力供給の再開は最も重要な課題の一つでした。宮島線が迅速に復旧できたのは、廿日市変電所が無事だったためですが、市内広範囲に送電し、路面電車を運行させるためには、より大規模な千田町変電所の復旧が不可欠でした。
この困難な作業には、陸軍の船舶司令部「暁部隊」が支援に駆けつけました。彼らは崩落した変電所の屋根をテントで応急的に修復し、無数の瓦礫を撤去するという骨の折れる作業に従事しました。当時の整流器は現在のシリコン整流器とは異なり、水銀整流器というトラブルの多い形式で、原爆の爆風で飛散したガラス片が内部に突き刺さるなど、その修理・復旧は非常に手間のかかるものでした。
 原爆の被害を受けた広島電鉄の路面電車。被爆直後の荒廃した広島市内で、復旧の困難さを物語る被爆車両の写真。
原爆の被害を受けた広島電鉄の路面電車。被爆直後の荒廃した広島市内で、復旧の困難さを物語る被爆車両の写真。
広島電鉄の電気課員たちは、昼夜を問わず献身的に復旧作業に没頭し、わずか10日後の8月16日には送電が復旧、翌17日には電車の試運転が開始されるという驚異的なスピードで作業を進めました。この変電所復旧の成功は、市内線の本格的な運行再開に向けた大きな弾みとなりました。その後、小網町〜土橋間が8月18日に復旧、そこから十日市町、左官町(現:本川町)へと小刻みに路線が広がり、9月7日には爆心地の目の前を通過する己斐〜八丁堀間が復旧を果たしました。これは、当時の人々の強い復興への執念が実を結んだ結果と言えるでしょう。
架線工事:プロ集団「満長組」の貢献
電力復旧と並び、路面電車の運行に不可欠なのが架線の修理です。被爆当時、広島電鉄の架線係は全員が亡くなるという悲劇に見舞われ、専門的な技術を持つ人材が完全に失われていました。
そこに現れたのが、関門海峡で電線工事を行っていた電気工事のプロ集団「満長組」(現:サンテック)でした。彼らは空襲に備え、電線の碍子(がいし)や電気工事用具のストックを豊富に持っており、すぐに広島市内の架線工事に着手しました。
満長組の作業員たちは、「降りる暇もなく電柱の上で飯を食う」と言われるほどの猛烈なスピードで作業を進めました。彼らは広島電鉄の架線係に代わり、壊滅した架線を張り直し、再び電車が走れる状態へと復旧させました。当時の満長組の社長は、「わしらの手で広島を復興させよう!」と熱い思いを語っていたと伝えられています。この言葉は、単なる業務を超えた、深い郷土愛と使命感が彼らを突き動かしていたことを示唆しています。彼らのような外部からの支援と、そのプロフェッショナルな仕事ぶりが、広島電鉄の奇跡的な復旧を支える重要な要素となりました。
復興の象徴としての広島電鉄
広島電鉄の迅速な復旧は、単なる交通インフラの再建に留まらない、より深い意味合いを持っていました。それは、原爆によって打ちひしがれた人々の心に希望の光を灯し、広島の街が必ず復興するという強いメッセージを送り続けるものでした。変電所を復旧させた電気課員たち、瓦礫を撤去し電源を復旧させた「暁部隊」、そして命がけで架線を張り直した「満長組」など、彼ら「名もなき人々」の献身的な努力と、それぞれの持ち場でのプロ意識が結集した結果でした。
広島電鉄の復旧は、戦後の混乱と絶望の中にあって、人々が手を取り合い、共通の目標に向かって奮闘することの重要性を雄弁に物語っています。今もなお広島の街を走る路面電車は、単なる交通手段ではなく、平和への願いと、どんな困難にも屈しない人々の強い意志、そして復興の象徴として、私たちに多くのことを語りかけています。この歴史的偉業とその背後にある人々の物語は、後世に語り継がれるべき貴重な教訓です。
参考文献
- 松浦明孝氏の手記
- 中田裕一著『だから路面電車は生き返った』(南々社)
- 広島電鉄の社史