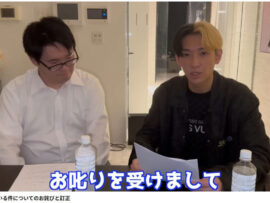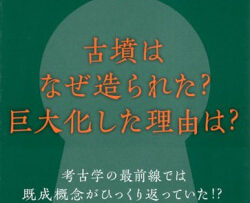茨城県常陸大宮市が太平洋ミクロネシア地域のパラオ共和国から男女2人の研修生、ケネリー・レケメルさん(22)とシェナ・セゲバオさん(23)を受け入れている。ともに先の大戦の激戦地として知られるペリリュー島の出身だ。
戦時中、ペリリュー島の水戸歩兵第二連隊を中心とする守備隊は、上陸してきた米軍との交戦で約1万人が戦死。うち75人が常陸大宮市出身だった。近年、遺族らの慰霊訪問を契機にパラオへ消防車や救急車、野球用具などを寄贈する交流が生まれた。
さらに来年の東京五輪開催が決まると常陸大宮市はパラオのホストタウンとなり、事前キャンプ地にも名乗りを上げた。研修生2人は選手らが来日した場合のサポートのほか、市民との交流が主な役割だ。
今回が2度目の常陸大宮市滞在で、小学校などでかつての激戦の模様を日本語で伝えるレケメルさんは「戦争は二度と起きてほしくないが、忘れてもいけないこと」と強調する。
研修生を世話する市の東京オリパラ推進室、相田英樹さん(43)は父方の大叔父がペリリュー島で戦死。「不思議な縁を感じる。子供たちが研修生と触れ合うことで海外へ目を向け、将来国際的な場で活躍するような人材が育ってくれれば」と夢見る。
戦争をきっかけとする3000キロ以上南に離れた地域との交流が、今度は五輪という平和の祭典でさらに深まろうとしている。何だか胸が熱くなった。(三浦馨)