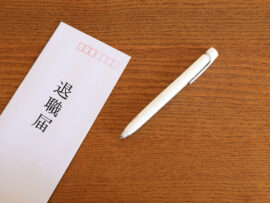映画『国宝』が公開から2カ月が経過し、依然として多数の観客を動員し、異例のロングラン上映が続いています。現在の興行収入は85億円を超え、2025年公開の実写映画として既にトップの座を獲得しています(2025年8月3日現在)。この驚異的なヒットの要因としては、主演の吉沢亮をはじめとする豪華俳優陣の熱演や、口コミによる幅広い世代への浸透が指摘されていますが、意外にも、監督である李相日氏の手腕に注目する声は多くありません。しかし、李監督のこれまでのフィルモグラフィーを紐解くと、『国宝』の成功は、まさに彼ならではの「ヒットの方式」に基づいたものであり、彼だからこそ成し得た偉業と言えるでしょう。
『国宝』の驚異的なヒットと「100億円突破」の可能性
映画『国宝』は、このままの勢いを維持すれば興行収入100億円超えも現実的な目標となり、社会現象と化しています。これは実写の日本映画において、これまでに『踊る大捜査線』の映画2作と『南極物語』という、いずれもフジテレビが制作に携わった3作品しか達成していない稀有な記録です。もし『国宝』が100億円を突破すれば、テレビ局が制作に関与していない実写邦画としては史上初の快挙となります。
現在、興行収入80億円を超える邦画の多くは、『海猿』や『花より男子』など、テレビ局が主導した作品が目立ちます。これらの作品は、テレビ局の持つ大規模な宣伝力を背景に、公開初週から爆発的なヒットを記録することが一般的です。
一方、『国宝』は、そうした大規模な宣伝による認知を得た作品とは一線を画しています。その証拠に、公開初週の全国映画動員ランキングでは3位スタートという出だしでした。しかし、SNSや口コミを通じて作品の魅力がじわじわと広がり、公開3週目で初めてトップの座を獲得するという、非常に珍しいヒットの軌跡を辿っています。この現象は、紛れもなく「作品そのものの力」が観客を動員し続けていることを示しています。
 映画『国宝』のポスター。興行収入85億円超えの異例ヒットを記録し、その「作品の力」が注目される。
映画『国宝』のポスター。興行収入85億円超えの異例ヒットを記録し、その「作品の力」が注目される。
映画『国宝』の物語概要と監督の視点
改めて、『国宝』の物語を簡潔に紹介しましょう。物語は、任侠の一門に生まれた喜久雄(吉沢亮)が歌舞伎の名門に引き取られ、その家の御曹司である俊介(横浜流星)と共に、歌舞伎役者として厳しい研鑽を積んでいく過程を描いています。喜久雄が歌舞伎一家の血を継がぬ存在であるのに対し、俊介は正当な後継者の血筋を引いているという設定が、二人の関係性に複雑な影を落とし、ドラマの核を成しています。この繊細な人間関係と伝統芸能の世界を描く上で、李相日監督の演出手腕が光ります。
李相日監督のフィルモグラフィーと過去作品
1974年生まれの李相日監督は、1999年に映画監督としてデビューして以来、ここ数年は数年に一度のペースで長編映画を発表し続けています。李監督が手掛けたこれまでの作品と興行収入の観点から見ると、『国宝』以前の作品において、興行収入順のトップ3が挙げられていますが、具体的な作品名は本記事の参照元では明記されておりません。監督の過去作には、観客の心に深く残る重厚なテーマ性や、登場人物の内面を深く掘り下げる演出が見られ、それが今回『国宝』で発揮された「作品の力」の源泉となっていると考えられます。
結論:『国宝』の成功は李相日監督の集大成
映画『国宝』の類を見ない大ヒットは、単に俳優陣の人気や宣伝戦略、口コミ効果だけによるものではなく、その根底には、李相日監督が長年培ってきた作品作りの哲学と「作品の力」が結実した結果であると結論付けられます。テレビ局主導ではない独立した作品が、これほどまでに社会現象となるのは、まさにその内容の深さ、演出の卓越性、そして観客が純粋に感動し、語り継ぎたくなる物語の力が圧倒的である証拠です。李相日監督のフィルモグラフィーを振り返ることで、『国宝』がなぜこれほどまでの成功を収めたのか、その本質的な理由が見えてくるでしょう。
参考文献:
- Yahoo!ニュース: https://news.yahoo.co.jp/articles/0ab9b0d530194908aaa01e0b949a9aac1dd14ec6
- 東洋経済オンライン (Original source implicitly via Yahoo! News)