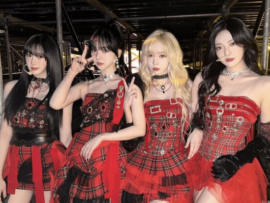近年、企業の「出社回帰」の流れが顕著に加速しています。リモートワークが普及する一方で、「チームの結束力が低下した」「メンバーの意欲が見えにくい」「重要な情報が画面越しでは伝わりにくい」といった管理職の悩みは増える一方です。こうした課題を背景に、アマゾンやアクセンチュアが週5日出社を義務付け、LINEヤフーもリモートワークを廃止するなど、大手企業を中心にオフィスへの回帰が進んでいます。しかし、働き手側からはリモートワーク継続を望む声も根強く、この「出社回帰」は賛否両論を巻き起こしています。本記事では、リモートワークが組織力にもたらす代償と、出社回帰の真の意図、そしてその効果的な活用法について掘り下げていきます。
 オフィスで協力して働くビジネスパーソン、出社回帰のメリットとチームワークの重要性
オフィスで協力して働くビジネスパーソン、出社回帰のメリットとチームワークの重要性
大企業が直面する組織課題と出社回帰の背景
日本の大企業は今、かつてないほど大きな変革期にあります。日本経済新聞の調査によると、2024年の採用計画における中途採用の割合は46.8%と過去最高を記録しました。これは、企業が従来の「同質的な組織」から、プロパー社員、中途入社者、契約社員、外国人材など、多様な価値観と経験を持つメンバーが集まる「多様な集合体」へと大きく転換している現実を示しています。
出社回帰の要因は多岐にわたりますが、筆者はこの組織構造の変化が重要なポイントの一つであると考えています。多様なメンバーを効果的に機能させるには、従来の「同じ組織の仲間だから分かり合える」といった暗黙の了解だけでは限界があります。特にリモート環境では、この多様性がかえってチーム内の分断を招きかねません。
さらに、人手不足の深刻化に伴い、管理職自身がプレイングマネージャーとして業務に追われる中、限られた時間でメンバーとの信頼関係を築き、チーム全体のパフォーマンスを最大化する必要性が高まっています。果たして、画面越しのコミュニケーションだけでこれらの複雑な課題を解決できるのでしょうか。
リモートワークで失われた二つの重要な要素
リモートワークには、時間効率の向上や集中作業への適性など、多くの魅力があることは事実です。しかし、組織力という観点から見た場合、特に以下の二つの重要な要素が失われがちです。
1. メンバーの「本当の状態」が見えないリスク
リモートワークでは、「静かなる退職」、つまり物理的には業務に従事しているものの、精神的には組織から離脱している状態を見逃してしまうリスクが高いです。顔の表情の微細な変化、声のトーン、デスクでの姿勢など、非言語情報はメンバーが抱える課題や悩みの重要なサインですが、画面越しでは十分に読み取ることが困難です。Zoom会議で「問題ありません」と答えていても、実際には深刻な問題を抱えているケースは少なくありません。
さらに深刻なのは、メンバー間の関係性が見えにくくなることです。誰が困っているのか、誰が助けを求めているのか、誰と誰の相性が良く、自然な協力関係が築かれているのかといった、組織内の微妙な人間関係や相互作用の把握がリモート環境では極めて困難になります。
2. チームの「熱量」が生まれにくい環境
画面越しの会議や業務だけでは、チーム全体の推進力や一体感を共有することが難しいという課題があります。「みんなで目標に向かって頑張っている」「チーム一丸となって取り組んでいる」といった感覚は、物理的な共存体験なくしては生まれにくいものです。
小さな成功を積み重ねても、それをチーム全体で共有し、次のステップへの強力な推進力に変換することが、リモート環境では格段に難しくなります。個々のメンバーが成果を上げても、その喜びや達成感がチーム全体に波及せず、個人の成功に留まってしまう傾向があります。また、困難な状況に直面した際にも、「全員で乗り越えよう」という一体感を醸成することが難しく、個々のメンバーが孤立感を抱えながら業務に取り組むことになりがちです。
このような課題意識から、多くの経営者や組織は「リアル出社」を命じていますが、単にオフィスに物理的に集まるだけで全ての課題が解決するほど単純ではありません。そこで、リアル出社をより効果的に活用するための、戦略的なアプローチが必要となります。具体的な解決策については、今後さらに深く掘り下げていく必要があるでしょう。
結び
出社回帰の動きは、単なるリモートワークからの脱却ではなく、変化する企業組織の現状に対する戦略的な対応策であると言えます。多様化するメンバー構成の中で、見えにくくなった個々の状態や失われがちなチームの熱量といった組織力を再構築するためには、リアルな場での交流が不可欠です。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、単に「出社すること」を目的とするのではなく、明確な意図と目的を持ったオフィスの活用が求められます。
長村禎庸[EVeM代表取締役CEO]
参考資料
- ビジネスインサイダー: 「なぜ今、出社回帰が増えているのか。単に「オフィスに来ればいい」ではない」
https://www.businessinsider.jp/post-283187 - Yahoo!ニュース: 「なぜ今、出社回帰が増えているのか。単に「オフィスに来ればいい」ではない」
https://news.yahoo.co.jp/articles/7805fcbadd898d10a2b26d01d3486514134e3655