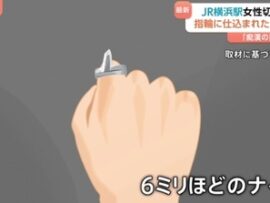広島に原子爆弾が投下されてから、今年の8月6日で80年という節目を迎えます。世界で唯一の被爆国である日本にとって、「あの日」の記憶を後世に語り継ぐことは責務です。本記事では、爆心地から870メートルの至近距離で被爆し、その後の人生を放射線の後遺症と闘いながら原爆の悲劇を伝え続けた被爆者、兒玉光雄氏(享年88)の壮絶な体験に焦点を当てる。兒玉氏は2020年に亡くなるまで多発がんを患いながらも証言活動を続け、その人生はNHKディレクター横井秀信氏の著書『異端の被爆者 22度のがんを生き抜く男』(新潮社刊)に詳しく綴られている。この記事は同書から引用し、80年前の広島で何が起こったのか、そして被爆者の苦悩と使命を深く理解する一助となるだろう。
80年前の8月6日:運命の夜明けと日常の断片
原爆投下前日の1945年8月5日、広島は午後9時20分の警戒警報、その7分後の空襲警報のサイレンで静寂を破られました。電気を点けることも許されない漆黒の闇の中、家族は息をひそめB-29の旋回を見守りましたが、機は飛び去り午後11時55分に空襲警報は解除。しかし、午前0時25分には再びサイレンが鳴り響き、2時10分に解除され、市民の睡眠と日常は蝕まれました。
運命の8月6日を迎えました。旧制広島第一中学1年生だった12歳の兒玉光雄氏は、眠い目をこすりながら起床。同級生の土井隆義さんと顔を合わせ、「眠いのう」「アメ公め、わしらを寝かせんつもりじゃ。ほんに、憎たらしいのう」と当時の少年らしい会話を交わし、学校へ向かいました。
二人が空を見上げると、雲ひとつない快晴で、まだ低い太陽がすでに熱い日差しを投げかけていました。戸板駅から汽車に揺られ、広島駅からは徒歩で学校を目指します。しばらくすると、長いサイレンが響き渡り、警戒警報が発令されました。街の防空壕に身を寄せることも考えましたが、午前7時半の集合時間に間に合わない。警戒警報での遅刻は、教員の鉄拳や同級生からの笑いを招く。そんな空気が漂う中、「急ごう」と二人は歩を早めた。
 広島原爆の壮絶な被爆体験を語り継いだ被爆者・兒玉光雄氏の肖像
広島原爆の壮絶な被爆体験を語り継いだ被爆者・兒玉光雄氏の肖像
爆心地870メートル:一瞬で奪われた「日常」と「命」
午前7時31分、警戒警報は解除され、「上空に敵機なし」のラジオ放送を確認した教員たちは、中庭に集まった生徒たちの点呼を始めました。この日は、空襲に備えた防火帯づくりのための建物疎開作業と、学徒動員で中止されていた授業の補習内容が発表される予定でした。土井さんは疎開作業現場へ、待機組の兒玉氏は教室へと移動しました。
兒玉氏がいた1年6組の教室は賑やかでした。生徒たちは時間割をノートに写し終えると、思い思いに動き回り、気の合う仲間と談笑にふけっていました。普段は軍隊式の礼儀作法に縛られる生徒たちも、教員や上級生の目のない教室では自由に振る舞っていました。外の陽射しは時間とともに強さを増し、セミの声がこだまのように響いていました。そこに「ブゥー」という低い音が覆い被さります。「お、Bじゃ」誰ともなくB-29の飛来を告げる声が上がりました。生徒たちは警戒警報がないことに訝しがりましたが、敵機の出現には慣れていました。音が徐々に近づくのが分かりました。
「おい、見に行こう」何人かが北側の廊下へ走り出し、他の教室からも飛び出していきました。「おい、落下傘か何か落としたで」という叫び声も聞こえます。この時、兒玉氏も同級生から外に行かないかと誘われ、椅子から腰を上げた瞬間、別の騒ぎが気になりました。学校への持ち込みを禁じられていた雑誌「少年倶楽部」を、何人もの生徒が群がってのぞき見していたのです。「わしにも見せてみい」と、兒玉氏がその一団に割り込もうとした、まさにその刹那――彼の右眼に、まばゆいばかりの「黄金の火柱」が飛び込んできました。
被爆直後から脱毛、発熱、吐血といった放射線の影響に苦しめられた兒玉氏は、当初、それが原爆だとは知らされませんでした。その後、61歳で大腸がんを発症して以来、胃、甲状腺、皮膚と、生涯で22回もの多発がんを患いながらも、「地獄を見せつけられた原爆に、人生まで支配されるのはまっぴらごめん」という強い意志を持って、原爆被害の恐ろしさを訴え続けました。旧制広島第一中学の同級生307人のうち復学できたのはわずか19名という絶望的な状況。生き延びた兒玉氏の証言活動は、核兵器の非人道性と被爆者の苦悩を伝え、後世に貴重な教訓を残しました。広島原爆投下から80年を迎える今、私たちは兒玉光雄氏のような被爆者たちの体験から学び、二度と悲劇が繰り返されないよう、平和への祈りと行動を続けることの重要性を改めて心に刻むべきです。