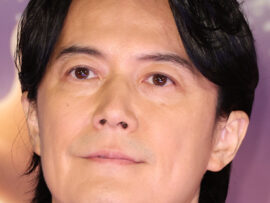かつて、未婚男性と聞けば20代の若年層をイメージするのが一般的でした。しかし、現代の日本社会ではその構図が大きく変化しています。国勢調査の長期的な推移を見ると、未婚男性の年齢構成は劇的に変化しており、中年層の存在感が増していることが明らかになっています。この変化は、日本の社会構造や個人のライフスタイルに深い影響を与えています。
昭和から令和へ:未婚男性の年齢構成の劇的変化
国勢調査のデータは、日本の未婚男性の年齢構成が過去100年間でいかに変化したかを明確に示しています。1920年には、20歳から50歳までの未婚男性のうち、20代が占める割合は驚異の87%に達していました。これは戦後の第二次ベビーブーム期である1970年代までほぼ変わらず続きました。
しかし、その後、未婚化と高年齢化が急速に進行し、2020年時点では20代の割合は41%まで大幅に低下。代わりに台頭してきたのが40代から50代の未婚男性で、その割合は36%と20代に迫る勢いとなっています。さらに、今後の人口推計によると、2050年には20代と40代から50代の未婚男性人口がほぼ同数になると見込まれています。ここでいう「未婚」とは、一度も結婚歴がない人々を指し、生涯を一度も結婚せずに終える指標である「生涯未婚率(50歳時未婚率)」が3割を超えるという推計とも符合します。もはや未婚男性の中心は若者ではなく、中高年層へとシフトしており、今後の20年間はまさに「中年未婚男性激増時代」に突入すると言えるでしょう。
 ソロ活を楽しむ中年男性。一人での食事風景は、未婚男性のライフスタイル変化を象徴する。
ソロ活を楽しむ中年男性。一人での食事風景は、未婚男性のライフスタイル変化を象徴する。
「結婚できない男」が予言した日本のソロライフの未来
このような未来を予見するかのようなドラマが、かつて人気を博しました。2006年夏に放送された阿部寛主演のテレビドラマ「結婚できない男」です。平均視聴率16.9%、最終回視聴率22.0%という高い人気を誇り、2019年には続編「まだ結婚できない男」も放送されました。
このドラマの主人公である桑野信介(阿部寛)は、40歳で未婚の建築デザイナー。自身の事務所を構えるほどのキャリアを持ち、年収も高水準です。家族でも住めるほどの広さを持つ、夜景の美しいタワーマンションで一人暮らしを謳歌しています。劇中の女性陣から「高年収で高身長、ルックスも悪くないから、お見合い写真だけならモテるのにねえ」と指摘されるものの、そのこだわりが強く偏屈な性格が災いし、結婚はおろか恋愛とも無縁のキャラクターとして描かれました。
しかし、桑野本人にとって、そうした独身のソロライフは決して苦痛ではありません。むしろ、徹底的に「一人が好き」というソロ気質を貫き通します。「一人レストラン」「一人焼肉」「一人ビアガーデン」「一人花火大会鑑賞」「一人バスツアー」など、あらゆる「ソロ活」を満喫するシーンが数多く登場します。まだ「ソロ活」という言葉が一般に浸透していなかった時代に、先んじてこのライフスタイルを実践していた元祖的存在と言えるでしょう。ドラマのタイトルは「結婚できない男」ですが、桑野本人は「俺は結婚できないんじゃないんだ、結婚しないんだ」と語るように、明確な意志を持って独身を選択する「選択的非婚」主義者です。「妻と子どもと家のローンは人生の三大不良債権だ」といった名言(あるいは迷言)は、多くの視聴者に強烈な印象を与えました。
まとめ
日本社会における未婚男性の高齢化は、統計データが明確に示す不可逆的なトレンドです。若年層中心の未婚者像は過去のものとなり、今や中高年層が未婚男性の大きな割合を占める時代へと突入しています。ドラマ「結婚できない男」の主人公、桑野信介のような「選択的非婚」のライフスタイルは、もはやフィクションの中だけの特別な存在ではなく、現実社会で増え続ける中高年未婚男性の一側面を象徴していると言えるでしょう。この社会構造の変化は、単なる人口動態の問題に留まらず、家族のあり方、消費行動、住宅事情など、多岐にわたる社会経済的な影響をもたらすものとして、今後も注目され続けるでしょう。