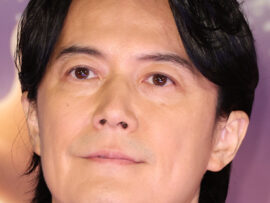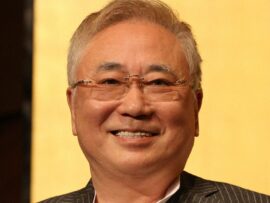現在放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』。その主題歌を人気ロックバンドRADWIMPSが担当する『賜物』が、放送開始以来、視聴者の間で賛否両論を巻き起こしています。X(旧Twitter)では「最初は不快でもしばらくしたら耳に慣れてくると思っていたのに、放送から3か月経った今でも全然慣れない」といった声が上がり、インターネット検索では「あんぱん 主題歌 ひどい」といった関連キーワードが表示されるほど、異例の事態となっています。なぜ、数々のヒット曲を生み出し、映画音楽でも高い評価を得てきたRADWIMPSが、朝ドラという国民的コンテンツで苦戦しているのでしょうか。本記事では、その背景と理由を深く掘り下げていきます。
 RADWIMPS野田洋次郎、朝ドラ『エール』出演経験と音楽性
RADWIMPS野田洋次郎、朝ドラ『エール』出演経験と音楽性
視聴者から「慣れない」の声、なぜ『あんぱん』主題歌は賛否を呼んだのか
朝ドラ『あんぱん』は、その内容やキャスト陣が好評で順調な滑り出しを見せていましたが、唯一、主題歌に対する受け入れ難さが放送当初から話題となっています。朝ドラに詳しいライターの津田春子氏によると、「従来の朝ドラ主題歌とは異なり現代的なテンポの上に、よく聞き取れない難しい歌詞、ドラマ内容とは異なるワンピース姿の今田美桜さんが近未来的な風景の中を走り回るという意味不明なタイトルバック」が、視聴者の困惑を招いていると指摘しています。このオープニング映像と楽曲の組み合わせが、多くの視聴者にとって「なぜこの選択をしたのか」と疑問を抱かせるレベルだという声も聞かれます。
映画音楽で実績のRADWIMPS、朝ドラでの「マリアージュ」の難しさ
今年メジャーデビュー20周年を迎えるRADWIMPSは、新海誠監督の『君の名は。』(2016年)、『天気の子』(2019年)、『すずめの戸締まり』(2022年)といった大ヒットアニメ映画で野田洋次郎氏が音楽を担当し、作品の世界観を音楽で見事に表現してきました。映画の興行成績とともに主題歌も大ヒットを記録し、その音楽性は高く評価されています。それゆえに、国民的番組である朝ドラの主題歌担当というニュースは大きな期待を集めましたが、その「作品の世界観を大切にできる音楽家」であるはずのRADWIMPSが、朝ドラという毎日視聴されるフォーマットにおいて、なぜ視聴者の心をつかみきれていないのか、その“マリアージュ”(融合)の難しさが浮き彫りになっています。
米津玄師の成功例から見る朝ドラ主題歌の「最適解」
今回のRADWIMPSの件とは対照的に、高く評価された成功例として、2024年放送の朝ドラ『虎に翼』の主題歌を担当した米津玄師氏のケースが挙げられます。米津氏は、制作側から台本と短い資料映像を受け取ってから曲作りを始めたといい、「毎日食えるものというか、軽やかなものを作るべきだろうというところから始まりました」とインタビューで語っています。重厚な楽曲で知られる米津氏が、朝ドラという「毎日の生活に寄り添う」コンテンツに合わせ、その世界観に軽やかにフィットさせてきた手腕は、「さすが」の一言に尽きます。朝ドラの主題歌は平日の毎朝流れるため、制作側との入念な打ち合わせが行われるとされており、視聴者の日常に自然に溶け込むような「親しみやすさ」が求められる傾向にあります。
結論:日常に寄り添う「朝ドラらしさ」との調和が鍵
RADWIMPSと野田洋次郎氏の音楽性は、映画という特定の時間と空間で深く没入させるアート作品においては絶大な力を発揮します。しかし、朝ドラは国民の日常生活の一部として、毎朝繰り返し聴かれ、見る人の感情にそっと寄り添うような「日常性」が重視されます。米津玄師氏の例が示すように、アーティストの個性と朝ドラというコンテンツの「慣習」や「期待」との調和こそが、主題歌成功の鍵となるのでしょう。今回の『あんぱん』主題歌への賛否は、単なる楽曲の良し悪しに留まらず、コンテンツの特性を深く理解し、それに寄り添うことの重要性を改めて浮き彫りにした事例と言えます。
参考文献
- Yahoo!ニュース (2025年8月7日). 「あんぱん」主題歌のRADWIMPSに賛否、朝ドラと音楽のマリアージュの難しさ. https://news.yahoo.co.jp/articles/fa2e94362a914da5c7d2f5b7eaf34e5b5b3d983f