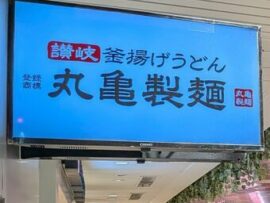日米間で「認識の違い」が指摘されていた相互関税15%の問題に関し、赤沢経済再生担当相は、トランプ政権の閣僚らとの協議の結果、アメリカ側が大統領令の修正に応じることになったと明らかにしました。しかし、その具体的な修正時期は依然として不透明なままです。この相互関税を巡る日米間の混乱は、当初の合意内容と実際の適用方法に大きな乖離が生じたことで表面化しました。
相互関税「一律15%上乗せ」の衝撃と影響
当初、日本の認識では、従来の関税が15%未満の品目については15%に引き上げ、元々15%以上の品目については関税率を据え置くという取り決めでした。しかし、実際に運用が始まると「一律15%が上乗せされる」という状態になっており、これが日米間の認識の齟齬の核心となりました。例えば、マヨネーズは6.4%から15%になるはずが、さらに15%が上乗せされ21.4%に高騰。牛肉に至っては、従来の26.4%に据え置かれるはずが、41.4%へと大幅に引き上げられる事態に発展しました。赤沢経済再生担当相は「きわめて遺憾です」とこの状況への不満を表明していました。
 赤沢経済再生担当相が日米相互関税の「認識の齟齬」について遺憾の意を表明している様子
赤沢経済再生担当相が日米相互関税の「認識の齟齬」について遺憾の意を表明している様子
赤沢経済再生担当相の訪米と交渉成果
こうした状況を受け、訪米中の赤沢経済再生担当相は、トランプ政権の閣僚らとの協議に奔走しました。自身のX(旧Twitter)では、「本日、米国商務省にラトちゃんを訪ねました」「大親日家のベッちゃんとも旧交を温めました」とSNS特有の親しみを込めた表現で投稿し、協議が順調に進んでいることをアピールしました。その後、赤沢経済再生担当相は「日米間の認識に齟齬はありません」と明言し、アメリカ側が関税に関する大統領令の修正措置を行うとともに、誤って徴収された関税は遡って払い戻すことを説明したと発表しました。
 訪米中の赤沢経済再生担当相がトランプ政権の閣僚らとの協議結果を説明している場面
訪米中の赤沢経済再生担当相がトランプ政権の閣僚らとの協議結果を説明している場面
業界の動揺と専門家の見解、そして政府の姿勢
この関税の混乱に振り回されていたのは、年間およそ100トンもの和牛をアメリカに輸出している企業など、日本の輸出業者です。ある和牛輸出企業の担当者は、「商売はやりづらい。一喜一憂しますよね。話いったんは煮詰まった上でまた煮詰め直さないといけない」と、相次ぐ状況の変化に対する困惑を露わにしました。この問題の原因について、アメリカ政府関係者に話を聞いたという明海大学の小谷哲男教授は、「閣僚級の会話が全体に共有されておらず、他の事例と同じく追加関税だと理解したと。合同文書を作らなかったが故にこうなったと考えられます」と分析しました。一方、国内では共同文書を作成しなかったことが裏目に出たのではとの批判も出ていますが、赤沢経済再生担当相はこれに対し、「共同文書を作成していないから何か起きたというのは、私は全く理解ができない。合意文書を作るなら日本に都合のいい関税率をこうする、ということだけ書いて米側が署名してくれると思いますか?」と反論し、共同文書作成の現実的な難しさを強調しました。
 明海大学の小谷哲男教授が日米間の貿易問題の原因について見解を述べる様子
明海大学の小谷哲男教授が日米間の貿易問題の原因について見解を述べる様子
今後の展望:不透明な修正時期
アメリカ側による大統領令の修正措置が約束されたものの、その具体的な適用時期については「適時」とされており、依然として不透明な状況が続いています。今回の件は、国際的な貿易交渉における合意内容の徹底した確認と、その後の実務的な運用における情報共有の重要性を改めて浮き彫りにしました。日本企業が安心して輸出を行えるよう、早期の明確化が待たれます。
参考文献:
- 日テレNEWS NNN (2025年8月9日). 日米で“認識の違い”が指摘されている15%の相互関税について、赤沢経済再生担当相はトランプ政権の閣僚らとの協議の結果、大統領令が修正されることとなったと明かしました。ただ、修正の時期などはわかっていません。
- Source link:
https://news.yahoo.co.jp/articles/ed9aef85b94958bec0b17f2792d8de80059cf71e
- Source link: