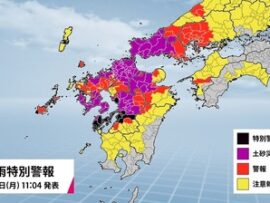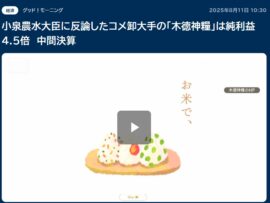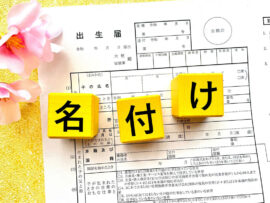2024年、海上自衛隊では特定秘密の不適切な取り扱いや潜水手当の不正受給など、信頼を揺るがす不祥事が立て続けに発覚しました。これらの問題は、単なる個別の事案ではなく、長年にわたる海上自衛隊の組織文化と深く関連していると、元海上自衛隊自衛艦隊司令官の香田洋二氏は指摘します。長きにわたり組織の中枢を担った同氏が、その痛恨の思いと共に、問題の背景にある組織の病巣と、変革への提言を語ります。
「退官後も海上自衛官」としての使命感と危機感
香田洋二氏は1972年に防衛大学校を卒業以来、2008年に退官するまで36年間にわたり海上自衛隊に身を捧げました。その経験は彼の人生そのものであり、「アドミラル・コウダ(提督)」と呼ばれることに国際的な敬意を感じるように、今なお自身を海上自衛官だと認識しています。それゆえに、海上自衛隊が称賛されれば喜び、批判に晒されれば忸怩たる思いを抱かずにはいられないといいます。現在の海上自衛隊の不祥事は、香田氏にとって歯ぎしりするほど苦しい現実であり、組織の元リーダーの一人として、読者への謝罪とともにその責任を痛感しています。
2024年、海自を揺るがす一連の不祥事の概要
2024年に表面化した海上自衛隊の主な不祥事としては、以下のような問題が挙げられます。まず「特定秘密の不適切な取り扱い」は、国家の安全保障に関わる機密情報の管理体制に大きな疑問を投げかけました。次に「業者からの不適切な物品供与」は、外部との関係における透明性の欠如と倫理観の低下を示唆しています。そして「潜水手当の不正受給」は、規律を重んじるべき組織内部における不正行為が露呈した形です。香田氏はこれらの問題が、長年の慣習が積み重なった「悪弊」であると分析し、組織的な病理が根底にあることを示唆しています。
 2024年7月12日、潜水手当不正受給問題で謝罪する酒井良海上幕僚長(時事通信フォト)。海上自衛隊の一連の不祥事を受け、組織文化の変革が求められている様子を示す一枚。
2024年7月12日、潜水手当不正受給問題で謝罪する酒井良海上幕僚長(時事通信フォト)。海上自衛隊の一連の不祥事を受け、組織文化の変革が求められている様子を示す一枚。
特殊な「海上勤務」が生む光と影:組織文化の深層
なぜこのような不祥事が発生したのか、香田氏はその原因の一つに海上自衛隊特有の「海上での共同生活」という環境を挙げます。艦艇内での生活は、限られた空間で長期にわたり行動を共にすることで、隊員間の強固な結束を生み出すという利点があります。しかし、この密接な人間関係は、一歩間違えれば、不祥事を起こした「身内」を庇い立てし、外部に問題が漏れることを防ごうとする「悪弊」を生み出す危険性をはらんでいるのです。
香田氏の見立てでは、こうした海上自衛隊の閉鎖的で特殊な組織文化こそが、今回の一連の不祥事の温床となったと強調します。残念ながら、この問題意識はまだ海上自衛隊内部で十分に共有されているとは言いがたい状況にあるとも述べており、抜本的な組織改革の必要性を示唆しています。
結び:信頼回復への道は「組織文化」の変革から
海上自衛隊を揺るがす一連の不祥事は、個々の隊員の資質の問題に留まらず、その根底には長年にわたり培われた組織文化が深く関わっていることが、元トップである香田洋二氏の分析から浮き彫りになりました。海上での特殊な共同生活がもたらす結束と、それが裏目に出てしまう「身内意識」という両面を深く理解し、負の側面を克服することが、信頼回復への第一歩となります。この提言は、国民の信頼を取り戻し、防衛組織としての健全性を保つために、海上自衛隊が真摯に向き合うべき喫緊の課題であることを示しています。
参考文献:
- 香田洋二『自衛隊に告ぐ 元自衛隊現場トップが明かす自衛隊の不都合な真実』中央公論新社