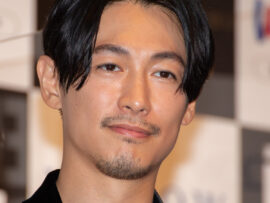現代の教育現場では、子どもたち一人ひとりの個性と能力を最大限に引き出すための多様な学習方法が模索されています。その中で注目を集めているのが「自由進度学習」です。東京都町田市立小川小学校(児童数411名、15学級)では、星彰校長が提唱する「見抜く、仕掛ける、なじませる」という独自の教育アプローチに基づき、この自由進度学習を実践し、子どもたちが「遊ぶように学ぶ」環境を創出しています。従来の学級担任制からチーム担任制へと移行し、教師間の協働を深めることで、全学年で授業改革を推進。2025年6月には、100名を超える教育関係者を招き、校内研究会を自主開催しました。本稿では、小川小学校が描く「学びの楽しさを実感する」自由進度学習の現状と、その先にある教育の未来について詳述します。
主体的な学びを育む教育現場の革新
2025年6月に開催された第1回公開校内研究会は、「学びの楽しさを実感する自由進度学習〜すすんで自分の学びを深め、学びの楽しさを実感する子の育成〜」という研究主題のもと、5・6時間目を利用した複数教科単元内自由進度学習の授業が公開されました。小川小学校に足を踏み入れると、その教育風景の斬新さに驚かされます。2年生から6年生の児童たちが、それぞれの教室はもちろんのこと、体育館、視聴覚室、図書室、英語ルーム、そして廊下といった多様な場所で、自らが選択した学習に没頭している光景が広がっていました。教員は各所に複数配置され、子どもたちに直接指示を出すのではなく、「見守る」姿勢を貫き、質問や相談があった場合にのみ、きめ細やかなサポートを提供しています。この主体性を尊重する環境が、児童の自律性と探究心を育む基盤となっています。
 町田市立小川小学校における自由進度学習の風景:児童が主体的に学ぶ様子
町田市立小川小学校における自由進度学習の風景:児童が主体的に学ぶ様子
複数教科にまたがる体験的な学び:3年生の挑戦
この日の公開授業で特に印象的だったのは、3年生と4年生の取り組みでした。3年生は、算数「長さ」と理科「風やゴムの力」という複数教科単元内での自由進度学習を展開。児童たちは、見開き版で作成された学習の手引き、ワークシート、プリント、筆記用具を手に、自分が取り組みたい学習内容と、それができる最適な場所を自ら選び、学びを進めていました。
体育館は「ゴムの力の実験」や「風の力の実験」の会場となり、児童たちは2人1組で、ウインドカーと送風機などを用いて、風の強さと車が動く距離の関係について実験を行いました。入り口に設置された説明ボードやワークシートで内容を確認し、まずは結果を予想。「準備はこれで大丈夫だね」「じゃあ、弱い風と強い風を比べてみよう。最初は弱い風ね」といった活発な会話を交わしながら実験を進める姿は、まさに真剣そのものでした。「あ、止まった!距離を測ろう」と、実験で得られた結果はすぐに記録され、シールとして表に貼り付けられ、仲間と共有されていました。
算数の「長さ」の学習会場は、教室と隣接する英語ルームでした。計測や計算に集中できる教室には、異なる長さの物差しや巻き尺が用意され、保護者ボランティアが作成したサクラやカリンの切り株模型の円周を測る児童の姿が見られました。また、廊下では、床に貼られたテープの間を数を数えながら往復する児童も。「100mは何歩か測っている」という彼らは、10m、100mの歩数を基に、これまで学習した内容を応用して「1kmは何歩になるか」を予想するなど、体験を通して実用的な算数の知識を深めていました。このような実践的な学びは、児童が知識を実生活と結びつけ、応用力を養う上で非常に効果的です。
自律性と計画力を育む:4年生の多教科連携
4年生は、算数「角」、国語「本は友達」、書写「部分の組み立て」(上下)という、一見すると関連性の低い3教科の単元内自由進度学習に挑戦していました。算数は教室、国語は図書室と教室、書写は英語ルームと、それぞれの学習内容に適した場所が用意されています。3年生と同様に、児童たちは3教科の学習の手引きを手に、その日の学習内容を決め、自ら学習場所へ移動します。
書写の教室では、筆で「雲」の字を書く子どもたちの姿がありました。自身が「難しい」と感じた部分にシールを貼ったり、上手に書くための「ポイント」を付箋に書いて共有したりと、互いに学びを深め合う協働学習の様子が見られました。直接的な関連のない複数教科の学習であるにもかかわらず、子どもたちは2時間の中で、どの教科にどのくらいの時間をかけるかを自分で調整しながら取り組んでいました。「習字を最初にやったら結構時間がかかっちゃった」「今日は国語と算数を進めることができた」など、試行錯誤しながらも自分のペースで単元のゴールを目指そうとする児童の姿は、教育者としても頼もしい限りです。
「遊ぶように学ぶ」:小川小学校が示す教育の未来
友達と一緒に「次はどの教室に行く?」と誘いあったり、一人で静かに廊下を歩いて集中したり、「集中しすぎて疲れた〜。少し休む」と言って机に伏せたりする姿も。一見すると、どこか「これが授業?」と疑問に感じるような、まるで学校全体がお祭りであるかのような光景がそこかしこで繰り広げられていました。しかし、その根底には、子どもたちが「遊ぶように学ぶ」という、生き生きとした学習体験が一貫して流れています。
町田市立小川小学校の自由進度学習は、単に学習のペースを個々に委ねるだけでなく、児童が自らの興味に基づき、主体的に学習内容や場所を選択し、仲間と協働しながら学びを深めるという、次世代の教育モデルを提示しています。このような個別最適化された学びは、子どもたちの自己調整能力や問題解決能力を育み、将来にわたって自ら学び続ける力を培う上で不可欠です。小川小学校の実践は、日本の教育改革において、子どもたちが真に「学びの楽しさを実感し、自らの学びを深める」ことができる未来の教育像を鮮やかに描き出しています。