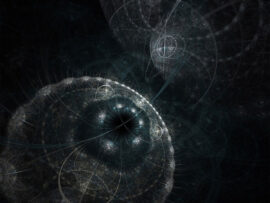夏の休暇シーズンを迎え、空港を訪れる海外旅行者が急増している中、「飛行機に乗るのが怖い」と感じる人が増えています。乱気流によって飛行機が激しく揺れるケースが頻発しているためです。この乱気流の増加の背景には、深刻化する気候変動が指摘されています。航空便の安全性への懸念が高まる中、乱気流の現状と、それに対する航空業界の対応、そして未来に向けた対策について深く掘り下げていきます。
乱気流発生の実態と事故の増加
乱気流の発生件数は、近年顕著な増加傾向にあります。昨年、11の韓国籍航空会社が国土交通部に報告した乱気流発生件数は合計2万7896件に上り、これは前年の2万575件と比較して35.6%の増加です。さらに、航空便1便あたりの乱気流件数も2022年の0.044件から昨年は0.052件へと増えており、2019年の0.027件と比較すると、わずか5年間で約2倍に急増していることが分かります。
乱気流による航空事故も増加傾向にあり、国際的なデータがその深刻さを示しています。国際民間航空機関(ICAO)によると、昨年世界で発生した94件の航空事故のうち、乱気流に関連する事故は32%(30件)を占めました。直近の事例としては、先月、米国発のデルタ航空機が激しい乱気流に遭遇し、乗客および乗務員25人が負傷し、緊急着陸後に病院へ搬送される事態が発生しました。
このような乱気流による安全事故のリスクの高まりを受け、航空会社も対応に追われています。例えば、大韓航空は昨年8月から、乱気流による危険を考慮し、エコノミークラスでのカップラーメンの提供を中止しました。また、アシアナ航空も同様に、熱い飲み物の提供を停止するなど、安全確保のための対策を講じています。
 雲の中を飛行する旅客機と、気候変動による乱気流の増加
雲の中を飛行する旅客機と、気候変動による乱気流の増加
気候変動と乱気流のメカニズム
乱気流は発生原因によって「晴天乱気流(CAT)」「山岳波乱気流」「対流雲乱気流」の3つに大別されます。この中で特に懸念されるのが、晴れた空に突然発生するため予測が難しい「晴天乱気流」です。
晴天乱気流は、強いジェット気流によって引き起こされますが、地球温暖化の影響で東アジア上空のジェット気流が強まっているため、韓半島(朝鮮半島)周辺を含む東アジアの空域が最も危険な地域の一つとされています。ソウル大学地球環境科学部のキム・ジョンフン教授の研究チームが1979年から2019年までの世界の晴天乱気流発生頻度を分析した結果、東太平洋や北西大西洋よりも、東アジアでのジェット気流および晴天乱気流の増加傾向が顕著であることが明らかになりました。
キム教授は、この現象について次のように説明しています。「温暖化により、熱帯地域の対流圏(高度10キロ以下)が熱くなり、北極の成層圏は逆に冷たくなったことで、両者の境界で温度差が生じ、ジェット気流が強まっています。このジェット気流が強まる地域が、ちょうど韓国から日本を経て米国に向かう主要な航空路と重なるため、今後晴天乱気流がさらに増えると予想されます。」
その他の乱気流と今後の予測・対策
一方、東南アジアなどの熱帯地域では、積乱雲の発達に伴って発生する「対流雲乱気流」が最も増加しています。晴天乱気流が数十分間揺れるのに対し、対流雲乱気流は前触れもなく数秒以内に非常に強い揺れが発生するため、予測が難しく、より危険性が高いとされています。昨年5月には、シンガポール航空機がミャンマーの上空で対流雲乱気流に遭遇し、1人が死亡、機内は一瞬で大混乱となりました。このため、東南アジア地域を通過する際には、突発的な乱気流に備えてシートベルトを常時着用することが強く推奨されます。
キム教授は、「最近では、晴天乱気流を12時間前に予測し、航空路を調整する技術も発達している」としながらも、「予測が難しい突発的な乱気流が今後増える見込みであり、AI技術を活用して予測・対応能力を飛躍的に高めていく必要がある」と述べています。
結論
気候変動が引き起こす乱気流の増加は、航空旅行の安全性に新たな、そして深刻な課題を突きつけています。特に東アジアや熱帯地域での乱気流の頻発は、乗客だけでなく航空会社にとっても喫緊の課題であり、その対応が求められています。最新の予測技術やAIの活用、そして乗客自身の安全意識向上が、今後ますます重要となるでしょう。安全な空の旅のためにも、乱気流に関する情報への関心と、事前の準備がこれまで以上に求められます。
参考資料
- 中央日報(JoongAng Ilbo)記事
- 国際民間航空機関(ICAO)の報告
- ソウル大学地球環境科学部 キム・ジョンフン教授の研究