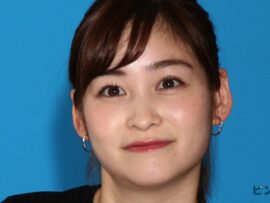近年、日本の大学受験において、総合型選抜をはじめとする推薦入試が一般選抜に代わり主流となりつつあります。特に女子生徒においては、その傾向が顕著で、大学進学者の半数以上、実に6割以上が推薦入試で進学している現状があります。しかし、推薦入試は一般選抜とは異なる「難しさ」を内包していると指摘されています。
本稿では、受験ジャーナリストの杉浦由美子氏が、自身の著書『大学受験 活動実績はゼロでいい 推薦入試の合格法』の好調な売れ行きを背景に、総合型選抜を実際に経験した学生への取材に基づき、その実態と敗因を分析します。これは「総合型選抜の敗因分析」の前後編の前編にあたります。
推薦入試が主流となる背景と女子生徒の現状
大学受験の変化は数字にも表れており、特に女子生徒の一般選抜率は約37%にすぎません。これは、多くの女子生徒が推薦入試ルートを選択し、成功していることを示唆しています。一方で、推薦入試の難しさは、単なる学力だけでなく、多角的な評価が求められる点にあります。
今年、難関私立大学群MARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)に一般選抜で合格した女子学生Aさんも、当初は早慶上智ICUといったより上位の大学を総合型選抜で目指していました。彼女が総合型選抜を選んだ背景には、通っていた女子校の教育方針が大きく影響していました。「私の学校は推薦入試で大学に進学する生徒がほとんどだったんです」とAさんは語ります。
総合型選抜への挑戦と自身の強み
小学5年まで海外で過ごし、帰国生入試で中堅私立校に進学したAさんの学校は、「探究学習」に非常に力を入れていました。授業では大勢の前でプレゼンテーションをする機会が頻繁に設けられ、探究活動やスピーチコンテストへの参加も積極的に奨励されていました。
 推薦入試と総合型選抜が主流となる現代の大学受験
推薦入試と総合型選抜が主流となる現代の大学受験
Aさんは高校2年生の時、探究学習やスピーチのコンテストで入賞を果たします。この実績が評価され、学校の先生から「総合型選抜なら慶應や上智に受かるかもしれないよ」と勧められ、挑戦を決意しました。高校3年生の4月からは推薦入試専門の塾に通い、志望理由書の作成に取り組みました。この塾での経験を通して、Aさんは改めて自身の「話すこと」に強みがあることを再確認しました。
彼女は「頭のいい学校の子達は補講や宿題がたくさんあってすごく勉強していたけれど、探究やプレゼンはあまりやってなくて、私は学校の授業でプレゼンをする機会がたくさんあったので恵まれていると思いました」と述べます。実際に取材してみると、Aさんのプレゼン能力は目覚ましく、滑舌が良く、適度な声の高さで明確に話す姿は、聞き手を惹きつけるものでした。このような「活動実績」や「非認知能力」とも言える強みが、総合型選抜で評価される重要な要素となります。
まとめ:推薦入試は「簡単」ではない
本稿で紹介した女子学生Aさんの事例は、推薦入試、特に総合型選抜が単に学力だけでは測れない、多面的な能力や経験が求められる複雑な入試形式であることを示唆しています。学校の教育方針や、生徒自身の持つ特性が合致した場合に大きな強みとなり得る一方で、安易に「楽な入試」と捉えるべきではないことが浮き彫りになります。推薦入試の成功には、自身の強みを深く理解し、それを効果的にアピールする戦略が不可欠です。
参考文献: