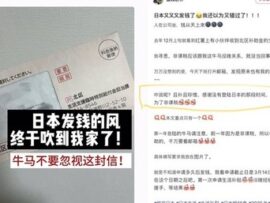文部科学省は、次期学習指導要領において「特定分野に特異な才能のある児童生徒」を対象とした特別な教育課程編成の特例を認める方針を示しました。この新しい動きは、学校現場にどのような変化をもたらすのでしょうか。また、具体的にどのような支援が想定されているのでしょうか。文部科学省の「特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業」で教員の研修用パッケージ監修を務め、2025年4月に開設された愛媛大学教育学部附属才能教育センターのセンター長に就任した、同大学教育学部教授の隅田学氏へのインタビューを通し、その具体的な内容と支援の基本的な考え方を探ります。
「特異な才能」とは何か?文科省の見解と多様な姿
「ギフテッド」と呼ばれることも多い才能ある子どもたちに対し、文部科学省は「特異な才能のある児童生徒」という言葉を用いています。しかし、この「特異な才能」の内容に関して、文科省は特定の基準を示していません。才能教育の研究においても、「才能」は知能、創造性、芸術、リーダーシップ、特定の学問といった多様な観点が交差し、本人の素質と環境の相互作用によってさまざまな形で現れるとされています。そのため、一律的な認定は避けつつ、多様な定義や見いだし方が模索されています。
一つ確かなことは、年齢や地域にかかわらず、特異な才能のある子どもはどこにでも存在するという事実です。愛媛大学では2010年から、興味関心や能力の高い幼年期の子ども向けの教育支援活動「キッズアカデミア」を実施しており、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国から多様な才能を持つ子どもたちが参加しています。これは、才能が特定の地域や環境に限定されるものではないことを示しています。
 教室で真剣に学ぶ児童生徒たち。文部科学省が推進する「特異な才能のある児童生徒」への支援の重要性を示唆する一枚。
教室で真剣に学ぶ児童生徒たち。文部科学省が推進する「特異な才能のある児童生徒」への支援の重要性を示唆する一枚。
「多様性を認め合う教育」が支援の基本理念
特異な才能のある児童生徒への支援にあたり、文部科学省の有識者会議は、「児童生徒を特定の基準で選抜し、特別なプログラム等を提供することを目指すのではなく、才能のある児童生徒を含むすべての子どもたちが多様性を認め合い、高め合える指導・支援の在り方を考えていくこと」を基本的な考え方としています。
多様性を尊重する教育は世界中で重視されており、各国の児童生徒の才能を伸ばすための取り組みも多岐にわたります。しかし、共通しているのは、単一の教育モデルを全員に当てはめるのではなく、個々の強みや可能性を最大限に伸ばすため、教育をより柔軟なものにしていくという方向性です。これは、個別最適化された学びを追求し、すべての児童生徒が自己肯定感を持ちながら成長できる環境を築くための国際的な共通認識と言えるでしょう。
「特異な才能のある児童生徒」への支援は、選抜された一部の子どもたちのためだけのものではなく、多様性を認め合い、それぞれが持つ能力を最大限に発揮できるような教育環境を社会全体で構築していくことを目指しています。文部科学省の新たな方針と、教育現場や専門家からの見解は、今後の日本の教育がより柔軟かつ個別最適化された学びへと進化していく方向性を示唆しています。これは、才能教育を通じて、すべての子どもたちの可能性を広げるための重要な一歩となるでしょう。
参考文献
https://news.yahoo.co.jp/articles/c274dd37932492381077c788c95a8820eec56d35