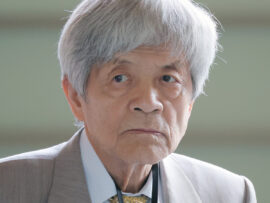日本の地図帳を開いて、南樺太(ロシア名:サハリン島)の南半分と千島列島(ロシア名:クリル諸島)が着色されていないことに疑問を抱いたことはないだろうか。これらの地域が「どこの国にも属さない」とされているのは、第二次世界大戦終結時の日ソ戦争と、その後の複雑な国際関係に起因する。本稿では、日本とロシア(旧ソ連)の間で長らく未解決となっているこれらの領土問題の歴史的背景と、日本の敗戦を巡る大国の思惑について紐解く。
南樺太と千島列島、その領有権の変遷
日露間の国境画定の歴史は、1855年の日露通好条約に遡る。この条約で、日本とロシア帝国は択捉島とウルップ島の間を国境と定めた。その後、1875年の樺太・千島交換条約で日本は千島列島全島を獲得し、1905年のポーツマス条約で日露戦争に勝利した日本は南樺太も手に入れた。しかし、第二次世界大戦末期の1945年、ソ連は日ソ中立条約を一方的に破棄して対日参戦し、南樺太と千島列島を占領した。翌年にはこれらの地域を自国領土として編入し、その施政権は現在のロシア連邦へと引き継がれている。
一方、日本は1951年に調印されたサンフランシスコ平和条約で南樺太と千島列島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄した。しかし、ソ連はこの条約に調印せず、また、現在に至るまで日露間でこれらの領有についての話し合いが十分に行われていないため、日本政府は両地域の帰属を「未確定」と主張している。この見解に基づき、日本の地図帳ではこれらの地域が特定の国の色で塗られていないのだ。
米国の焦り、日本の誤算、ソ連の漁夫の利
日露両国の主張は異なるが、この領土問題の根本は、日ソ戦争におけるソ連軍の占領に始まる。特に南樺太と千島列島での戦闘は、本土における地上戦の延長線上にあった。第二次世界大戦末期、B29による日本本土への空襲が激化し、フィリピンを米軍に奪還された1944年秋には、日本の敗北は既に決定的な状況にあった。しかし、日本は連合国が突きつけた「無条件降伏」を頑なに拒否した。その最大の理由は、「国体護持」、すなわち天皇を中心とする政治体制の維持が危うくなると恐れたためである。
 第二次世界大戦終結後の国際秩序を形成したヤルタ会談から70年、クリミア半島ヤルタに立つ米英露首脳(ルーズベルト、チャーチル、スターリン)の像。日ソ戦争と日本の領土問題に繋がる密約の背景を示唆。
第二次世界大戦終結後の国際秩序を形成したヤルタ会談から70年、クリミア半島ヤルタに立つ米英露首脳(ルーズベルト、チャーチル、スターリン)の像。日ソ戦争と日本の領土問題に繋がる密約の背景を示唆。
日本側は、一度は戦況を好転させ、その後に「国体護持」などの条件を付けて米英と講和することを夢想していた。さらに、日ソ中立条約の存在を理由に、ソ連が米英との橋渡し役になってくれるかもしれないという根拠のない期待を抱き、ソ連への仲介を要請した。しかし、これは「見たい現実」しか見ないという日本の指導者の誤算に他ならなかった。
一方、米国は、日本本土への進撃は快進撃のように見えながらも、米兵の犠牲者が増え続けることに頭を抱えていた。こうした状況において、米国にとってソ連の対日参戦は、日本を早期降伏に追い込むための決定的な「切り札」だった。そのため、米国は対独戦と同様に、対日戦のためにもソ連に惜しみなく物的援助を与え、ポツダム宣言受諾後のソ連の対日参戦を促した。結果として、ソ連は日本の降伏間際に参戦することで、南樺太と千島列島を占領し、「漁夫の利」を得る形となったのである。
未解決の領土問題と日本の未来
南樺太と千島列島の領土問題は、日ソ戦争の終結と戦後処理の複雑さ、そして当時の国際情勢における日本の外交的な誤算が絡み合って生まれた。この歴史的経緯は、単なる領土の帰属を超え、国際関係の機微、大国の思惑、そして国家の決断がもたらす長期的な影響を現代に伝える重要な教訓となっている。これらの地域が地図上で「色なし」であり続ける限り、日本にとって第二次世界大戦の「終わらなかった戦争」の象徴であり続けるだろう。
参考文献
- 『Wedge』2025年8月号 特集「終わらなかった戦争 サハリン、日ソ戦争が 戦後の日本に残したこと 戦後80年特別企画・後編」
- 拙著『日ソ戦争』(中公新書)