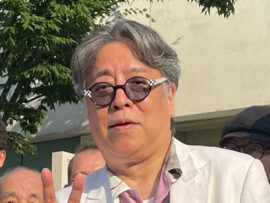80年前の8月14日、日本はポツダム宣言を受諾し、太平洋戦争は終結を迎えました。しかし、沖縄ではその日以降も戦闘が続き、正式な降伏調印式は9月7日でした。さらにその後27年間、沖縄はアメリカの統治下に置かれることになります。こうした沖縄戦の悲劇と市民の困難に光を当てるのが、大阪在住のホリーニョ氏(@horinyo)の活動です。彼は沖縄戦当時の白黒写真をカラー化しSNSで公開し続け、今年2月28日にはそれらをまとめた書籍『カラー化写真で見る沖縄』(ボーダーインク)を出版しました。本記事では、ホリーニョ氏のカラー化写真が伝える、戦場での人々の背景と共感の力を深掘りします。
「共感」を生むカラー化の狙い:女性と子どもの視点
ホリーニョ氏がカラー化に取り組む沖縄戦の写真には、特に女性や子どもが写っているものが多く見られます。その背景には、沖縄戦についてあまり詳しくない層、特に本土の読者に対して「これから少し学んでみよう」というきっかけを作りたいという彼の明確なコンセプトがありました。
沖縄戦の残酷さや悲惨さを伝える既存の書籍は多数存在しますが、ホリーニョ氏は「自分たちと変わらない普通の生活を送っていた人々も、いかに戦争に巻き込まれていったのか」という共感を抱いてもらうことを重視しました。そのため、戦場で特に弱い立場に置かれた女性や子どもたちが、そこに確かに存在していたという事実を肌で感じられるような写真を重点的にカラー化しています。しかし、その過程で、彼は深い「葛藤」に直面することになります。
衝撃の一枚が問いかけるもの:自決を試みた女性の真実
ホリーニョ氏がカラー化する女性の写真を探し、沖縄県公文書館で資料を検索していた際に、ある写真が目に留まりました。
 1945年4月4日、沖縄本島に上陸した米軍が設置した病院で手当を受ける女性患者たち。沖縄県公文書館所蔵の白黒写真をホリーニョ氏がカラー化。
1945年4月4日、沖縄本島に上陸した米軍が設置した病院で手当を受ける女性患者たち。沖縄県公文書館所蔵の白黒写真をホリーニョ氏がカラー化。
最初にその写真を見たとき、ホリーニョ氏は「手当されている」「助かったのだな、よかった」と安堵の気持ちを抱いたといいます。しかし、その写真のキャプションを読み進めるうちに、衝撃的な事実が明らかになりました。写っていたその女性は、米軍が沖縄に上陸した数日後に自ら首を切って自殺を図り、その傷を治療されている最中の姿だったのです。この事実は、単なる負傷者の治療という表面的な情景とはかけ離れた、沖縄戦の深い絶望と人間の尊厳に関わる問題を示しており、ホリーニョ氏に「覚悟はあるか?」と問いかけてくるような強烈な印象を与えました。
沖縄戦の記憶は、ただの歴史的事実ではなく、そこに生きた人々の感情や決断、そして深い傷跡が色濃く残っています。ホリーニョ氏のカラー化作業は、色を付けるという行為を超え、これらの見過ごされがちな真実を現代に蘇らせ、私たちに深い共感を促す貴重な試みと言えるでしょう。
まとめ
ホリーニョ氏のカラー化写真は、太平洋戦争終結後も過酷な状況下に置かれた沖縄の人々の生々しい歴史を、現代の私たちに伝える強力な手段となっています。特に女性や子どもといった立場の弱い人々に焦点を当てることで、戦争の非人間性と、それに直面した「普通の」人々の苦悩を鮮やかに浮かび上がらせます。一枚の写真が持つ情報だけでなく、その背景にある「自決」という悲劇的な真実を掘り起こすことで、カラー化された歴史は単なる視覚情報以上の深い意味を持ち、見る者に倫理的な問いを投げかけます。彼の活動は、歴史を学ぶことの重要性、そして過去から未来への教訓を継承することの意義を改めて私たちに示しています。
参考文献
- 文春オンライン (2024年8月15日). 『「覚悟はあるか?」問われた気がした1枚の写真…沖縄戦の白黒写真をカラー化する会社員を苦しめた”女性の真実”』. Yahoo!ニュースより引用.