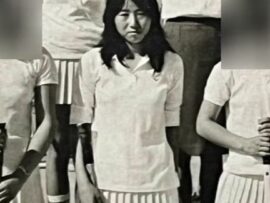近年、日本の教育現場では教員の働き方が大きな課題となっています。そうした中で、「フリーランス教員」という新たな働き方を提唱し実践しているのが木野雄介氏です。彼は、報酬や勤務条件について学校側と直接交渉し、合意形成を図ることで、従来の非正規教員とは一線を画す独自のキャリアを築いています。これは、安定志向が強いとされる日本の教職において、柔軟性と専門性を両立させる新たな可能性を示唆しており、教育現場における多様な働き方の未来を考察する上で重要な事例です。
「フリーランス教員」という選択肢:従来の非常勤講師との違い
日本の教員には、大きく分けて正規教員と非正規教員が存在します。非正規教員はさらに、正規教員と同様に担任や部活動顧問も務める「常勤講師」と、契約した授業時間のみを担当する「非常勤講師(時間講師)」に分類されます。常勤講師は正規教員に近い職務を担うにも関わらず、待遇面では劣ることが一般的です。一方、非常勤講師は授業以外の校内分掌(雑務)などには関わらず、その分処遇は常勤講師よりも低い傾向にあります。
フリーランス教員である木野氏は、この非常勤講師のカテゴリに属すると言えるでしょう。しかし、一般的な非常勤講師が学校側の提示する条件をそのまま受け入れるのに対し、木野氏の働き方の最大の特徴は、報酬を含むあらゆる条件を学校と「交渉」によって決定する点にあります。この交渉力により、彼は一般的な非常勤講師よりも恵まれた処遇を実現しており、自身の専門性を最大限に活かす働き方を確立しているのです。
困難な道のり:就職氷河期と教員採用試験への挑戦
大学卒業後、木野氏は当初スキーインストラクターとしての道を歩みました。教員採用試験に初めて挑戦したのは28歳の時です。1990年代のバブル崩壊に続く不況が長期化し、「就職氷河期」と呼ばれた時代はまだ続いていました。企業が採用数を絞る反動で公務員人気が高まり、安定した職業とされる教職にも応募が殺到していました。現在の教員不足とは信じられない状況で、当時は数十倍もの競争率になることも珍しくなく、木野氏の最初の挑戦は残念ながら不合格に終わりました。
 教員採用試験に臨む人々
教員採用試験に臨む人々
経験が拓く道:IT・海外勤務から正規教員へ、そして転機
最初の不合格を経て、木野氏は国内の教育IT企業で勤務したり、海外で働く経験も積みました。彼自身、「海外での勤務経験は、教員採用試験において高く評価されると考えた」と語っています。こうした多様な経験が実を結び、29歳で私立の中高一貫校に「正規教員」として採用されることになります。
しかし、2020年3月末、彼はその正規教員の職を辞することを選びます。その経緯について、木野氏は次のように説明しています。「教職に就いた当初、私は自分が小中高で教わってきた教師のイメージにとらわれ、子どもたちの人権を後回しにし、ひたすらクラスの秩序を最優先させていました。怒鳴りつけて子どもたちを黙らせ、脅して良い成績を取らせるようなやり方です。当時はそれでクラスをうまくまとめ、教師として成功しているとさえ思っていました。」この自己認識の変化が、彼が新しい働き方を模索する大きな転機となったのです。
まとめ:新しい教育の未来を切り拓くフリーランス教員
木野雄介氏の「フリーランス教員」としての挑戦は、従来の教育現場が抱える働き方の課題に対し、具体的な解決策を提示するものです。彼の経験は、報酬や働き方を自ら交渉する新たな教員像を提示し、教職におけるキャリアの多様性を広げる可能性を秘めています。また、自身の教育観を見つめ直し、生徒の人権を重視する姿勢へと転換した彼の道のりは、教育現場が本質的に目指すべき方向性についても示唆を与えています。今後、日本の教育システムがより柔軟で持続可能なものへと進化していく上で、木野氏のような先駆者の存在は、ますますその重要性を増していくでしょう。