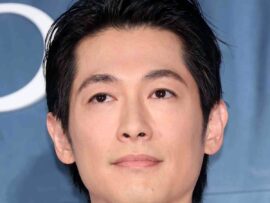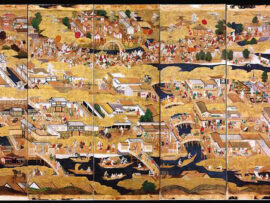近年、日本各地でクマをはじめとする野生動物による人身被害が急増し、喫緊の社会課題となっています。捕獲されたクマへの対応を巡っては、「殺すのはかわいそう」「もっと適切に対応しろ」といった批判的な意見が自治体に寄せられることも少なくありません。しかし、報道を通じてしか実情を知らない匿名の声の裏側には、どのような厳しい現実が横たわっているのでしょうか。秋田県でクマ対策の最前線に立つ専門職員、近藤麻実氏にその実情を聞きました。
 秋田県でクマ対策の専門職員として人身事故現場を検証する近藤麻実さん
秋田県でクマ対策の専門職員として人身事故現場を検証する近藤麻実さん
「対策を上回るペースで出没」危機的な現状
「各種対策で対応していますが、それを上回る勢いでクマが出没しています」と、近藤氏は言葉を選びながら秋田県におけるクマ出没の現状を説明しました。最前線でクマ対策に奔走する専門職員の言葉は、その生々しい「リアル」を伝えています。
近藤氏は2020年4月に秋田県庁に入庁し、クマをはじめとする野生鳥獣の対策を担う専門職員として活動しています。学生時代から野生動物の生態を学び、クマ対策に携わって5年以上になる彼女の言葉は、状況がいかに重篤で深刻であるかを物語っています。
今年7月には北海道福島町でヒグマによる新聞配達員の死亡事故が発生。ごく普通の日常の中で人の命が奪われた事実は、社会に大きな衝撃を与えました。北海道ではさらに、8月14日に日本百名山の一つである羅臼岳(標高1661メートル)で、20代の登山者がヒグマに襲われ死亡するという痛ましい人身被害も発生しています。
その他にも、「散歩中に」「自宅の庭で」「農作業中に」など、最近では日本全国で日常の中でのクマ関連事故が相次いでいます。これらの事例は、クマの活動域がすでに人間の生活圏と明確に重なってしまっていることの証明に他なりません。
「自宅居間での死亡事故はあり得ない」専門家の見解
岩手県北上市では7月に81歳の女性がクマに襲われ命を落とす事故が発生しましたが、その場所はなんと自宅の居間でした。前代未聞とも言える最悪の事態について、近藤氏は専門職員の立場から「あり得ない」と強く語ります。
その理由は明確です。「クマがいきなり人家に侵入することは考えづらいです。空き家や小屋などへの侵入を繰り返すうちに、その行動がエスカレートしていくものと推測しています」と近藤氏は説明します。だからこそ秋田県では、小屋への侵入などの「予兆」があればすぐにワナの設置について市町村と協議する体制を整えていると言います。
捕獲できた場合は、小屋の侵入箇所などから採取しておいた体毛と捕獲個体のDNAを照合し、侵入個体を見逃さず確実に捕獲できたかを確認するなど、人家侵入やそれに伴う重大事故につながらないよう、迅速かつ積極的に対応しています。クマ対策の現場を担う各自治体は、常に最善の選択で最悪の結果を防ぎ、地域住民の安全確保に尽力しているのです。
結論
日本の野生動物、特にクマによる人身被害は、専門家の努力や自治体の対策をもってしても、その増加ペースを食い止めきれない深刻な状況にあります。近藤氏の言葉は、現場の切迫感と、世間の認識とのギャップを浮き彫りにします。個人の生活圏にまで侵入するクマの存在は、従来の対策だけでは不十分であり、より早期かつ積極的な介入の必要性を示唆しています。この課題に対し、地域住民の安全とクマ保護のバランスをいかに図っていくか、社会全体の議論と理解が求められています。