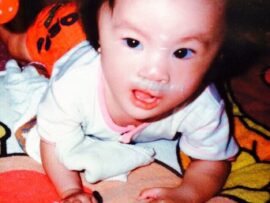南海トラフ巨大地震において、最も切迫性の高い「巨大地震警戒」が発令された際、津波からの事前避難を求められる住民が全国で52万人を超え、その半数以上が高齢者や障害者などの要配慮者であることが、国による初の全国調査で明らかになりました。政府はこの調査結果を受け、事前避難がより円滑に進むよう、各自治体への助言と支援を強化する方針です。
 南海トラフ地震の津波に対する事前避難対象地域の概念図
南海トラフ地震の津波に対する事前避難対象地域の概念図
南海トラフ地震と事前避難の背景
南海トラフ地震では、地域によっては地震発生からわずか数分で津波が到達する恐れがあります。このため、国は避難が間に合わない可能性のあるエリアを「事前避難対象地域」に指定するよう各市町村に要請しています。この対象地域は、「全住民対象」と「高齢者等(要配慮者)対象」の2種類に分けられ、「巨大地震警戒」が発表された場合には、対象住民に対して1週間の事前避難が求められます。
初の全国調査概要と対象住民数
昨年8月8日に宮崎県沖の日向灘で初めて「南海トラフ地震臨時情報(注意)」が発表されたことなどを契機に、政府は今年6月から8月にかけて、国が「防災対策推進地域」に指定する29都府県707市町村(5月時点)を対象に、事前避難の指定状況に関する初の全国調査を実施しました。
その結果、千葉県から鹿児島県までの16都県130市町村が事前避難対象地域を指定しており、対象となる住民総数は52万人を超えることが判明しました。内訳は、全住民が対象となる地域が約24万5600人、高齢者や障害者などの要配慮者が対象となる地域が約27万4800人でした。都県別では、高知県が9万2100人で最も多く、次いで宮崎県が7万9900人、静岡県が7万200人となっています。読売新聞の取材によれば、土砂災害警戒区域や耐震性が不足する住宅、さらには海抜ゼロメートル地帯を対象とする自治体も存在します。
自治体が抱える課題と国の対応
事前避難の推進にあたり、多くの自治体から「避難所不足」や「高齢者・障害者らの避難支援」が具体的な課題として挙げられています。これを受け、国は今年7月に改定した南海トラフ地震の防災対策推進基本計画において、事前避難の方針や具体的な方法を各自治体の推進計画に明確に記載するよう求めました。また、8月には臨時情報のガイドラインを改定し、事前避難の検討対象に海抜ゼロメートル地帯を新たに加えました。これらの対応により、今後対象地域や対象住民が増加する可能性もあります。
専門家の提言と今後の展望
京都大学防災研究所の矢守克也教授(防災心理学)は、今回の調査結果について、「国は単に人数を把握するだけでなく、事前避難にかかる諸費用を補助するなど、自治体に対する実質的な支援体制を強化する必要がある」と指摘しています。南海トラフ地震臨時情報には、平常時よりも発生可能性が数倍程度高い「巨大地震注意」と、100倍程度高い「巨大地震警戒」があり、これらの情報が適切に活用されるための国の積極的な支援が不可欠です。
今回の調査結果は、南海トラフ巨大地震への備えの現状と、今後の対策における具体的な課題を浮き彫りにしました。国、自治体、そして住民一人ひとりが連携し、より実効性のある事前避難体制の構築と、そのための財政的・人的支援の強化が喫緊の課題として求められています。
出典
読売新聞 (https://news.yahoo.co.jp/articles/975ae9a62bf565bf8ee8a554ebde0258dbadb92b)