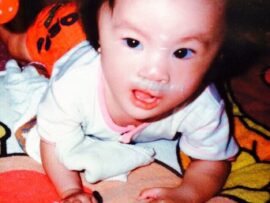日本の高齢化が急速に進む中、年金制度はかつての「胴上げ型」から大きく変化し、現役世代の負担は増大しています。一方で、年金を受給する高齢者自身の生活も厳しさを増しており、2023年の厚生労働省の調査によると、年金のみで生活している65歳以上の割合は41.7%にとどまっています。本稿では、変わりゆく高齢者の年金生活の実態と、副収入を得る手段として注目される「スポットワーク」の現状について深く掘り下げます。
「胴上げ型」から「肩車型」へ:年金制度の構造的変化
日本の年金制度は、1965年(昭和40年)におよそ9人の現役世代が1人の65歳以上の高齢者を支える「胴上げ型」でした。しかし、2012年には2.4人の現役世代が1人の高齢者を支える「騎馬戦型」となり、2040年にはわずか1.4人で1人の高齢者を支える「肩車型」へと移行する見込みです。このような急激な構造変化は、現役世代の高齢者に対する不満を増幅させ、社会全体を揺るがす大きな問題となっています。
年金だけでは支えきれない老後:高齢者の収入源の実態
年金制度の変化に伴い、年金だけで老後を支えることはますます困難になっています。厚生労働省が2023年に実施した「国民生活基礎調査」によれば、65歳以上の高齢者のうち、年金収入のみで生計を立てている人の割合はわずか41.7%です。この割合は今後さらに減少すると予測されており、多くの高齢者が年金以外の収入源を模索せざるを得ない状況が浮き彫りになっています。
 デスクワークをする高齢者のイメージ
デスクワークをする高齢者のイメージ
新しい働き方「スポットワーク」の台頭:63歳男性の事例
このような状況の中、注目を集めているのが「スポットワーク」、いわゆるスキマバイトです。ジャーナリストの若月澪子氏の著書『ルポ 過労シニア』に登場する東京都に住むRさん(63歳)もその一人。Rさんは現在、65歳まで勤める会社での仕事を終えた後、「NISA・タイミー・年金」の三本柱で生活していくことを計画しており、週末には居酒屋でスポットワークを行っています。ロマンスグレーの髪に洒落たストールを巻いたRさんは、若々しい印象の「イケオジ」です。
定年後の収入減と生活費の負担
Rさんは長年勤めた紳士服の卸会社で、定年後も嘱託社員として週4日勤務しています。現在の給料は定年前の約7割に減少し、手取りは月17万円程度。ボーナスも10万円ほどと、退職前と比較して手取りが月10万円ほど減少しました。Rさんはまだ年金を受給していませんが、社会保険や年金の負担が非常に重くのしかかり、可処分所得の減少を実感しているといいます。持ち家ではないため家賃もかかり、「副業をしないと生活に潤いがない」とRさんは語ります。
面接・履歴書不要のスキマバイト
Rさんが60歳になる少し前から始めたスポットワークは、専用アプリに個人情報を登録するだけで、自分の都合の良い時間に3〜5時間程度の単発アルバイトができる新しい働き方です。仕事に応募する際に面接や履歴書の提出が不要である点が最大の特徴です。
都心の居酒屋では、学生やフリーター、外国人労働者に加えてスポットワーカーの活用が増えています。労働力不足が深刻な店舗では、スポットワークは貴重な労働力となっています。物流倉庫の仕分け作業やスーパーの品出し作業など、初心者でも取り組みやすい仕事が多く、Rさんは居酒屋で食事後のグラスや皿の片付け、洗い物などを担当しているとのことです。
高齢者雇用の多様化と社会への影響
日本の社会構造が変化する中で、高齢者の年金生活は転換期を迎えています。年金だけに頼る生活は困難になりつつあり、多くのシニアが「スポットワーク」のような新しい働き方を通じて、自らの生活を支え、社会との接点を持ち続けています。この働き方の多様化は、高齢者の経済的自立を促すだけでなく、深刻な労働力不足に直面する企業にとっても重要な解決策となりつつあります。今後、このような働き方がさらに広がることで、高齢者がより活動的で充実した老後を送れる社会の実現が期待されます。