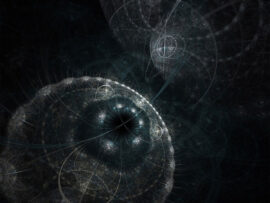近年、職場における新たな問題が浮上しています。かつては「静かな退職(Quiet quitting)」が注目されましたが、今、雇用主が直面しているのは、従業員の「静かな崩壊(Quiet cracking)」という、より深刻な隠れた精神的疲弊です。EYアメリカのチーフ・ウェルビーイング・オフィサーであるフランク・ジャンピエトロ氏は、現在の労働市場において、多くの労働者が「静かに苦しんでいる」状況を指摘しています。この「静かな崩壊」は、従業員のエンゲージメントを低下させ、最終的には燃え尽き症候群にも繋がりかねない、見過ごされがちな警戒サインとなっています。
 静かな崩壊に苦しむ従業員を表すイメージ。現代の労働市場における見えないストレスとメンタルヘルスの課題を示唆している。
静かな崩壊に苦しむ従業員を表すイメージ。現代の労働市場における見えないストレスとメンタルヘルスの課題を示唆している。
静かな崩壊とは何か?:見過ごされがちな従業員の心理状態
静かな崩壊とは、従業員が「出社して仕事はするものの、その間、静かに苦しんでいる」状態を指します。ジャンピエトロ氏がBusiness Insiderのインタビューで述べたように、多くの人々は現在の雇用主の元に留まっていますが、実際のところ仕事に対して意欲的ではありません。これは、現在の不確実な労働市場の状況が大きく影響しています。経済の先行きが不透明なため、労働者の多くはたとえ現在の仕事に満足していなくても、辞めることをためらっています。採用活動の減少や、転職に伴う賃金上昇への悪影響も、彼らが動き出せない要因となっています。
ジャンピエトロ氏は「多くの人が実際、現状に行き詰まりを感じているが、続ける決断をしているわけではなく、他に良い選択肢がないだけだ」と語っています。この状況は、労働者の心理に大きな負担をかけ、見えない形で精神的苦痛を増幅させています。
エンゲージメント低下と生産性への影響:見えない損失
静かな崩壊の進行は、結果として従業員エンゲージメントの低下、不満の増大、そして生産性の低下を引き起こします。これらは、最終的に燃え尽き症候群へと発展する可能性を秘めています。
ギャラップ(Gallup)が発表した4月の調査報告によると、従業員エンゲージメントは昨年、世界的に23%から21%へと低下しました。このエンゲージメントの低下が引き起こす生産性の損失は、世界経済全体で約4380億ドル(約64兆7700億円)に上ると推定されています。過去12年間で従業員エンゲージメントが低下したのはわずか2回しかなく、前回の低下は2020年のパンデミック下でした。
昇進の機会が厳しくなっていることも、この問題に拍車をかけています。企業は人事評価を見直し、職場への復帰を厳しく求め、大規模なレイオフを実施している現状があります。経済の不透明さと、多くの業界で過酷な労働文化への移行が相まって、労働者が転職を恐れるのは当然のことです。そもそも、興味のある求人が見つかるかどうかも不透明な状況です。ジャンピエトロ氏は、「多くの人がストレスだらけだと言っていて、その多くがおそらくすでに燃え尽き症候群か、その直前のどちらかということだ」と述べ、この見えない問題が深刻な段階にあることを示唆しています。
静かな崩壊は、個々の従業員のウェルビーイングに影響を及ぼすだけでなく、組織全体の生産性や健全な職場環境にも大きな損失をもたらす可能性があります。企業は、従業員の隠れた苦悩に早期に気づき、心理的安全性やサポート体制を強化することで、この新たな脅威に立ち向かう必要があります。