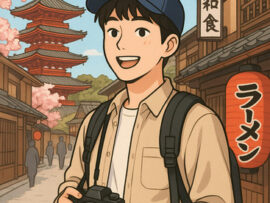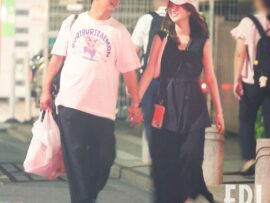参議院選挙での歴史的敗北を受け、自由民主党内では石破茂首相の「リコール」に繋がる総裁選挙前倒しの検討が始まった。しかし、この動きは石破首相の退陣を画策する議員たちの思惑通りには進まず、党内の意見対立は深刻化している。日本政治の混迷が深まる中、自民党の次期リーダーシップを巡る攻防に注目が集まっている。
総裁選前倒し、異例の手続きと党内対立
自民党の総裁選前倒しは、党所属国会議員と都道府県支部連合会の過半数の要求によって実施可能とされているが、過去に実際に適用された前例はない。8月8日に開催された党両院議員総会では、参院選大敗の責任を石破首相に問い、総裁選の早期実施を求める声が噴出。これを受け、参院選の「総括」が終了した後に、総裁選挙管理委員会が国会議員および全国支部の意思確認手続きを進めることになった。しかし、前例がないゆえに具体的な規定が存在せず、手続きの進め方自体が課題となっている。
8月19日に行われた総裁選管理委員会の会合では、手続きについて話し合われたものの、意見が対立し結論には至らなかった。この状況は、党内における石破首相の進退を巡る根深い溝を浮き彫りにしている。
 自民党両院議員総会で演説する石破茂首相と森山裕幹事長、総裁選前倒しを巡る議論の背景
自民党両院議員総会で演説する石破茂首相と森山裕幹事長、総裁選前倒しを巡る議論の背景
割れる党内意見:早期実施か、続投か
総裁選前倒しを巡っては、党内で意見が真っ二つに割れている。「イライラするよ。本当に早く総裁選をやってもらいたいと思っている人がほとんどだ」と語るのは、旧安倍派の衆議院議員A氏。A氏は、党内の多くの議員が石破体制の早期刷新を望んでいるとの見方を示す。
一方で、昨年9月の総裁選で石破茂首相を支持した無派閥の衆議院議員B氏は、早期実施に異を唱える。「石破首相が就任してまだ1年もたっていない。自民党が昨年の衆院選、参院選で負けた最大の原因は政治とカネ、つまり安倍派の裏金事件です。総裁選を前倒しする必要はない」と述べ、首相続投の正当性を主張する。この発言は、参院選敗北の原因が石破首相個人にあるのではなく、党全体が抱える構造的な問題、特に「裏金事件」にあるという認識を示している。
総裁選管理委員会の「絶妙な」人選とその影響
19日の総裁選管理委員会開催に先立ち、選挙での落選や閣僚就任により欠員となっていた委員の補充が発表された。委員長の逢沢一郎衆議院議員以下、委員は衆参両院議員11人で構成されている。この人選は、派閥や出身地域のバランスを考慮したとされており、旧安倍派と旧岸田派が各2人、麻生派、旧茂木派、旧森山派が各1人、無派閥が4人という内訳だ。
この人選について、旧安倍派のA氏からは不満の声が上がっている。「総裁選管の人選は、森山裕幹事長や逢沢委員長が担っているのだろうが、旧派閥でバランスをとるというなら、100人いた旧安倍派からもっと選ぶべきではないのか。なぜ、10人もいない旧森山派からも選ぶのか」と述べ、旧安倍派の代表が不足しているとの認識を示した。
自民党の閣僚経験者C氏は、この委員会の構成が今後の総裁選前倒し議論に決定的な影響を与えると指摘する。「前例がなかったことだけに、具体的なルール作りから総裁選管理委員会がやっていく。石破首相の退陣を求めるメンバーが多ければ、そんな方向性になるでしょうし、逆に少ないと石破首相を擁護するようなルールになっていく。委員11人中、確実に『総裁選前倒し』を言っているのは、3人ほどではないか。うまいメンバー選びをしたもんだ」と語り、委員会内部の勢力図が、総裁選前倒しの是非や手続きの方向性を大きく左右することになるとの見方を示した。この「絶妙な」人選は、総裁選前倒しを巡る動きを慎重に進めたい勢力の意向を反映している可能性をうかがわせる。
結論
参議院選挙の大敗後、自民党内で始まった総裁選前倒しの議論は、党内の深い亀裂と権力闘争を浮き彫りにしている。石破首相の進退を巡る意見対立、前例のない手続きの複雑さ、そして総裁選管理委員会のバランスの取れた人選は、この問題の解決がいかに困難であるかを示唆している。今後、党がどのような決定を下すかは不透明であり、その動向は日本政治全体の安定に大きな影響を与えることとなるだろう。