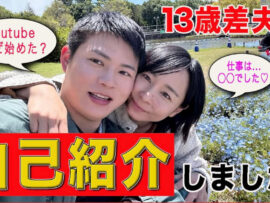あなたは「生理休暇」という言葉を聞いて、実際に利用した経験があるだろうか。労働基準法第68条では、「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と明記されており、女性が心身の不調時に休む権利は法的に保障されている。この権利は1947年の法施行以来、70年以上にわたり存在し、違反事業者には罰則も設けられている。しかし、その実態は「幻の制度」と化しているのが現状だ。
 キリンホールディングスのロゴと企業ビルの外観。同社は生理休暇の制度名を変更し、女性従業員が利用しやすい環境作りに取り組んでいます。
キリンホールディングスのロゴと企業ビルの外観。同社は生理休暇の制度名を変更し、女性従業員が利用しやすい環境作りに取り組んでいます。
生理休暇とは?法律で保障された権利の現状
「生理休暇」は、生理による体調不良時に女性が業務から離れることを認める制度である。しかし、厚生労働省の調査によれば、その取得率は驚くほど低い。1997年の3.3%から2014年には1.6%、そして2020年にはわずか0.9%と、右肩下がりの傾向が続いている。これは、法で定められた権利であるにもかかわらず、ほとんどの女性が利用していないことを示している。この厳しい現状を改善するため、一部企業では「生理休暇」の名称を見直す動きが見られる。キリンホールディングスもその一つであり、制度の「改名」を通じて、利用促進への一歩を踏み出している。
取得率低迷の背景にある3つの壁
社会保険労務士の佐佐木由美子氏(グレース・パートナー社労士事務所代表)は、生理休暇の取得率が低い主要な理由を三つ挙げている。
1. 認知度の不足と制度未導入企業の実態
「半数の人が生理休暇を知らないという調査結果もあり、特に非正規雇用では認知度が低い」と佐佐木氏は指摘する。さらに、制度自体が職場に浸透していないケースも多い。従業員10〜99人の企業では41%、9人以下では25.2%の企業しか生理休暇を導入しておらず、そもそも制度がないために利用できない女性も少なくない。
2. 有給休暇ではない経済的負担
法律には生理休暇を有給とする規定がなく、実際に有給としている企業は全体の29%に過ぎない。無給の場合、休暇を取得すれば収入が減少するため、特に非正規雇用の従業員にとっては経済的な負担が直撃し、申請をためらう大きな要因となる。
3. 「言いづらい」職場環境とプライバシーの問題
厚生労働省のアンケート調査(『働く女性と生理休暇について』より)では、「男性上司に言いづらい」「利用している人が少ない」「迷惑をかけたくない」といった理由が取得を阻んでいることが明らかになっている。佐佐木氏は、「生理休暇の申請時に男性上司からプライバシーに踏み込むようなセクハラ発言を受ける、あるいは男性上司が当惑するため言い出しにくいという事例もある」と述べる。また、生理痛の程度には個人差があり、その辛さが本人にしか分からないことから、「女性が女性に対して『生理くらいで休んで』という視線を向けるケースもある」という問題も存在する。これは、女性同士の間に「自分だって我慢してきた」という意識が働くことで、制度利用への心理的障壁を高めている可能性がある。

企業が模索する新たなアプローチ:「改名」の意義と効果
このような現状を打破するため、キリンホールディングスをはじめとする一部の企業は、生理休暇の「改名」というアプローチを試みている。従来の「生理休暇」という名称が持つプライバシー性の高さや、周囲の理解不足からくる心理的なハードルを軽減し、より利用しやすい制度へと変革を図るのが狙いだ。例えば、より包括的な「ウェルネス休暇」や「体調不良休暇」といった名称に変更することで、特定の症状に限定されない多様な不調に対応し、性別に関わらず誰もが心身のケアのために利用しやすい環境を構築している。このような「改名」は、単なる名称変更に留まらず、従業員の健康を重視する企業文化への変革を促し、多様な働き方を支援する企業の姿勢を示すものとして、注目を集めている。
まとめ
日本の「生理休暇」は、法で保障された権利であるにもかかわらず、その利用率は極めて低い「幻の制度」と化している。認知度の低さ、有給化の遅れ、そして何よりも「言いづらい」職場環境がその主な原因として挙げられる。この問題に対し、キリンホールディングスのような先進企業が「改名」という形で制度のあり方を見直し、従業員がより利用しやすい環境を整えようと試みている。これは、単に休暇制度を改善するだけでなく、職場の文化や従業員の健康に対する企業の意識改革を促す重要な動きと言える。生理休暇が名実ともに機能する社会の実現には、制度の見直しと共に、個々の従業員が安心して休暇を取得できるような、開かれた職場環境の構築が不可欠である。
参考文献
- 厚生労働省 労働基準法 第68条
- 厚生労働省「働く女性と生理休暇について」に関するアンケート調査結果
- 佐佐木由美子(グレース・パートナー社労士事務所代表)による分析
- 東洋経済オンラインによるキリンホールディングスへの取材記事
- 「生理休暇」を「改名」したキリンホールディングスにも話を聞いた (Yahoo!ニュース経由)