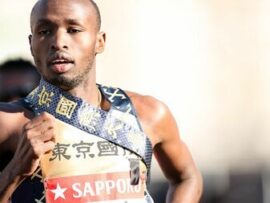日経平均株価が史上最高値を更新し続ける中、多くの投資家が今後の日本株の行方に注目しています。この上昇トレンドは継続するのか、それとも下落に転じるのか。金融業界の専門家22名が、2025年9月以降から2026年3月末にかけての日本株市場について詳細な分析を行いました。本記事では、「強気派」「中立派」「弱気派」それぞれの立場からの見解を深掘りし、市場を形成する多様な要因を解説します。
2025年後半〜2026年3月の日本株市場見通し:専門家22人の分析
ダイヤモンド・ザイが実施した調査では、22人のアナリストなどの専門家が、今後の日本株市場の展望について意見を交わしました。プロの見解は多岐にわたりますが、共通して多くの専門家が「株価変動の大きい相場が続く」と予測しています。この変動の波の中で、株価が基本的に上昇していくと見る「強気」の見方、反対に下落を警戒する「弱気」の見方、そしてどちらともいえない「中立」の立場が存在します。
「強気派」の視点:上昇トレンド継続の要因
「強気派」のアナリストたちは、市場の勢いや企業を取り巻く好材料に注目しています。
暴落後の反発と減税効果への期待(フェアトレード・田村祐一氏)
フェアトレードの田村祐一氏は、相場の「値動きの傾向」から強気の見方を展開します。過去の市場が大きな暴落を経験した後、30〜40%の上昇を見せる傾向があることを指摘。特に、4月のトランプ関税ショック後のもみ合い期間を経て、7月下旬に高値を更新した動きは、2020年のコロナ・ショックなど過去のショック相場と類似していると分析します。暴落によって売り手が一掃され、買い手しか残らない需給状況は、非常に健全な状態と言えるでしょう。
また、田村氏は参院選での与党敗北を契機とした減税論議にも注目。減税が進めばインフレが加速し、消費が活性化することで企業業績が向上し、株価を押し上げると予測しています。
世界的な過剰流動性とPBR改革の推進(グローバルリンクアドバイザーズ・戸松信博氏)
グローバルリンクアドバイザーズの戸松信博氏は、日経平均株価が4万8000円まで上昇する可能性を指摘します。その主な要因として、世界的に流通する資金総量の増加を挙げます。コロナ禍以降、FRB(米国の中央銀行)が市場に資金を供給し続けた結果インフレが引き起こされ、この過剰流動性が短期的な暴落はあれど、株式市場が長期低迷する構造を回避させると考えます。
さらに、日本の多くの上場企業でPBR(株価純資産倍率)改革が進んでいることも重要な要素です。トヨタ自動車やリクルートなどの大手企業が年間1兆円規模の自社株買いを実施することで、自己資本が減少しROE(自己資本利益率)の改善に繋がり、海外投資家からの資金流入を継続させると見ています。また、AIブームの恩恵も日本市場に及び、半導体関連企業が多い日本が日経平均株価を牽引する可能性にも言及しました。
企業業績の保守的予想とトランプ政策の恩恵(こころトレード研究所・坂本慎太郎氏)
こころトレード研究所の坂本慎太郎氏は、日本企業の業績予想が保守的であることに着目。実際には今期の1株利益が前期比10%程度伸びると見ており、海外投資家の継続的な買い越しが、日本企業の業績向上への強い期待を反映していると分析します。
また、トランプ政権の政策はこれまで関税という「ムチ」に焦点が当てられがちでしたが、今後は規制緩和や法人税減税といった「アメ」の部分が顕在化すると予測。これらの政策は日本の輸出企業の収益を押し上げる要因となり、実際、2017年のトランプ第一次政権による法人税減税時には日経平均株価が大きく上昇した前例があります。
 日本の株価動向と市場アナリストの分析風景
日本の株価動向と市場アナリストの分析風景
「中立派」の視点:明確な上昇テーマの欠如と外部要因
「中立派」のアナリストたちは、日本株固有の強力な上昇要因が少ないと見ています。
日本株固有のテーマ不足と消費税減税の議論(智剣・Oscarグループ・大川智宏氏)
智剣・Oscarグループの大川智宏氏は、現在の日本株には市場を強く押し上げるような明確な投資テーマが見当たらないと指摘します。市場予想の1株利益は悪化傾向にあり、全体的に下方修正が進んでいる状況です。
また、参院選で野党が躍進したことにより、消費税減税の議論が再燃する可能性も指摘。消費税の減税は財政悪化の懸念だけでなく、「消費税が減税されるかもしれない」という期待が、自動車やマンションなどの高額消費を手控える傾向を生み出し、中長期的な消費の冷え込みに繋がる可能性があります。
一方で、米国株の堅調さには注目しています。米国のナスダックは最高値を更新し、AIや半導体関連株は今後も勢いを増す見込みです。さらに、米国が景気悪化ではない状況で利下げに動けば、株価には大きなプラス要因となります。大川氏は、米国株が秋以降も上昇基調を維持し、それに牽引される形で日本株も「つれ高」を見込めると分析しました。
債券市場の変調とETF売却のリスク(ザイ・アナリスト・小林大純氏)
ザイ・アナリストの小林大純氏は、債券市場に変調が起きている点を懸念材料として挙げます。健全財政とされてきたドイツなども財政拡張に動き、世界的に債券が売られやすい状況にあります。債券価格の下落による損失を穴埋めするために、金融機関などが保有する日本株ETFを売却する動きが出ており、ここから日経平均株価が大きく買い上がるような勢いは見込みづらいと見ています。
「弱気派」の視点:企業業績の実態と関税の影響
「弱気派」のアナリストたちは、現在の株価が企業業績の実態以上に高水準にあることや、外部リスクの顕在化を警戒しています。
企業業績の過大評価とトランプ関税の顕在化(山和証券・志田憲太郎氏)
山和証券の志田憲太郎氏は、企業業績の実態以上に株価が高水準に達している点に警鐘を鳴らします。トランプ関税が当初通告の25%から15%で合意されたものの、今期の1株利益は前期より約3%マイナスになると予測。会社予想だけでなく、市場予想も4月末から7月末にかけて6.2%低下しており、多くの企業が期初に関税の影響を業績に織り込んでいないため、下方修正のリスクがあると見ています。
足元の株価上昇は需給の良さ、特に年初からのドル離れの受け皿として日本株が買われてきた側面が大きいと分析。現在の株価は、ドル離れによる資金流入と半導体株の急な復活で実力よりも2000円くらい底上げされているとし、実際に米国で関税の影響が出てくれば、株価を押し下げる可能性もあると警告します。
買い戻し一巡後の急落リスクと個人投資家の動向(マーケットコメンテーター・岡村友哉氏)
マーケットコメンテーターの岡村友哉氏も同様に弱気の見通しを持ちます。直近の株価上昇は、意外に強い株価にしびれを切らした売り方の買い戻しによる側面が大きいと分析。買い戻しが一巡し、一度逆回転となれば急落になりやすいと警告します。昨年の夏も、7月に急上昇した後に買いが止まり、8月に大暴落があった事例を挙げ、個人投資家が売り越しを続けている状況から、日経平均株価が4万円を超えた水準では個人の積極的な買いは期待しづらいと見ています。外国人投資家による買いが止まれば、急落のリスクが高まると結論付けました。
結論
2025年後半から2026年3月末にかけての日本株市場は、専門家の間でも意見が分かれる複雑な状況にあります。「強気派」は世界的な流動性の高さ、PBR改革、企業業績の潜在的な強さに期待を寄せ、日経平均株価のさらなる上昇を予測します。一方、「中立派」は日本固有の強力な上昇テーマの欠如や債券市場の動向を懸念しつつも、米国株の堅調さに牽引される可能性を指摘。そして「弱気派」は、企業業績の実態と株価水準の乖離、トランプ関税の影響、そして買い戻し一巡後の急落リスクを警戒しています。
これらの多角的な分析は、今後の市場が多様な国内外の要因に左右され、変動性の高い相場が続く可能性を示唆しています。投資家は、これらの専門家の見解を参考にしつつ、自身の投資戦略を慎重に検討することが求められるでしょう。