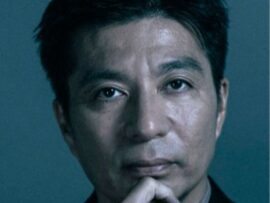「好きなバンドの曲は全部聴いているけれど、お金は払っていない」――。この若者の発言は、多くの世代に衝撃を与えたかもしれません。かつてはCDを購入して音楽を「所有」するのが主流でしたが、今やスマートフォン一つでYouTubeやサブスクを通じ「無料で、または定額で楽しむ」のが当たり前です。本記事では、若者世代の音楽消費行動の変化に着目し、データに基づき「CDは本当に売れなくなったのか?」という疑問に迫ります。
若年層の音楽体験:無料とSNS、サブスクが主流に
日本レコード協会が発表した2024年度「音楽メディアユーザー実態調査」によると、若年層はYouTubeなどの動画共有サイトに加え、InstagramやTikTokといったSNSを通じて音楽に触れる機会が非常に多いことが明らかになっています。これらのプラットフォームは、最新のヒット曲からニッチなジャンルまで、幅広い音楽を手軽に楽しむことを可能にしました。
さらに、10代・20代の間では、Apple Music、Spotify、LINE MUSICなどの定額制音楽配信サービスが幅広く利用されており、学生割引などの低コストで多様な楽曲にアクセスできる点が、利用を促進しています。このように、若者にとって音楽は「無料または定額で楽しむもの」という認識が深く定着し、物理的なCDを購入して聴くスタイルは、もはや主流とは言えません。
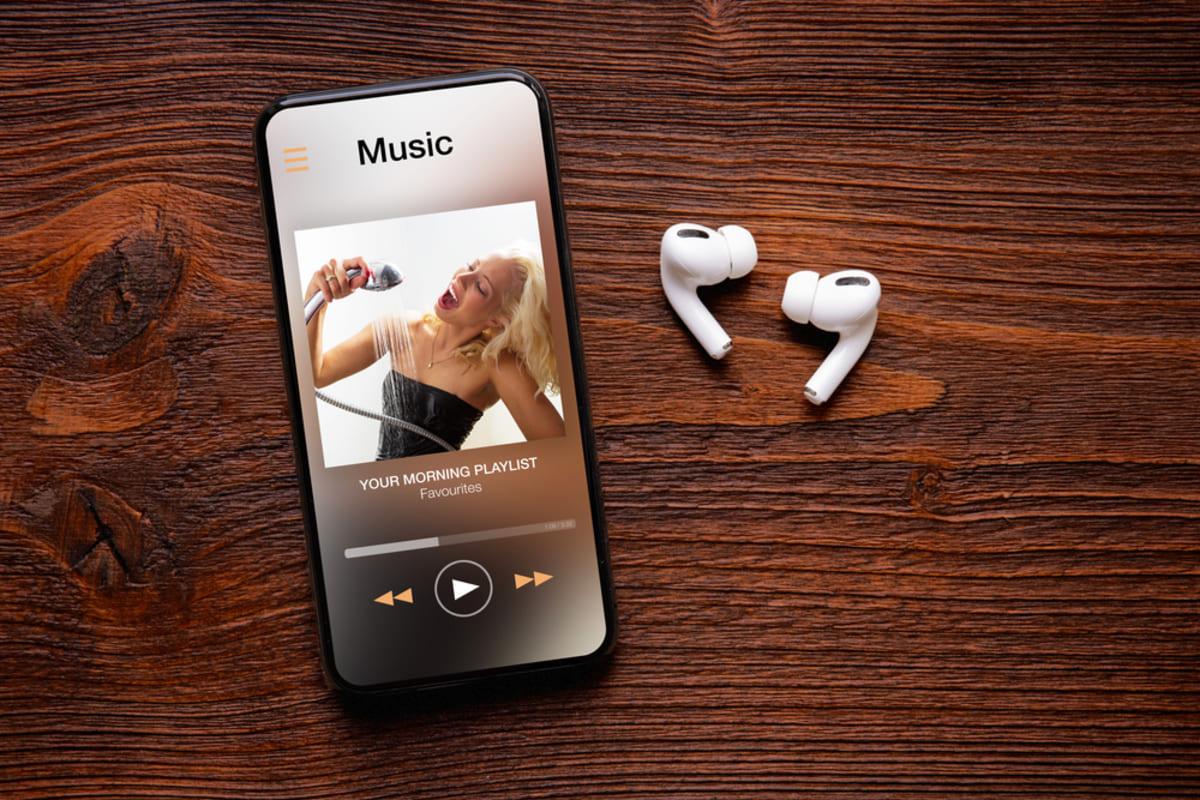 スマートフォンでデジタル音楽を消費する若者
スマートフォンでデジタル音楽を消費する若者
データが示すCD売上の劇的な減少
CDの売上データも、この変化を明確に裏付けています。日本レコード協会の資料によれば、2000年当時のCD生産枚数は約4億1405万枚、金額にして5239億円に上り、CDが音楽鑑賞の圧倒的な主役でした。
ところが、2024年にはCD生産枚数が約1億450万枚、金額が1402億円へと激減しており、生産枚数、金額ともに約4分の1近くにまで縮小しています。この長期的な推移は、CDが誰もが購入する当たり前の存在ではなくなったことを示唆しています。音楽の楽しみ方が「所有するもの」から「アクセスして聴くもの」へと移行した現代において、CDは時代の流れとともにその存在感を薄めていると言えるでしょう。
結論
以上のデータから、若者世代を中心に音楽消費行動は大きく変化し、CDの売上が劇的に減少している実態が明らかになりました。音楽を「所有」する価値観から「アクセス」する価値観へと移行した現代において、定額制音楽配信サービスや無料の動画共有サイトがその中心的役割を担っています。CDが完全に消え去ることはないかもしれませんが、その役割は確実に変化し、デジタルコンテンツが主流の音楽市場を形成していると言えるでしょう。