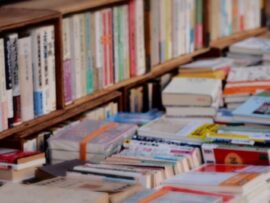大型選挙での相次ぐ敗北を受け、退陣の危機に瀕している石破茂首相が、政権の命運を左右する「運命の9月」を間もなく迎えます。与党・自民党が総裁選を前倒しするかどうかの決定方式を9月上旬に定める方針であり、石破政権の行方に強い関心が集まっています。また、石破首相と連携を続けてきた森山裕幹事長の進退も、参院選の検証後に決まると報じられており、首相の去就はさらに不透明感を増しています。本稿では、石破政権の今後を占う上で鍵となる三つの主要な動きを詳細に分析します。
世論は石破首相の「辞任不要」を支持
まず注目すべきは、世論が石破首相の味方をしている点です。昨年10月の政権発足以来、衆院選、今年6月の東京都議選、7月の参院選と立て続けに惨敗を喫し、日本政界で石破首相に対し「責任論」が高まる中、世論は対照的な反応を示しています。読売新聞(22~24日実施)の世論調査では、石破首相の支持率が前月比で17ポイントも上昇し39%を記録するという異例の現象が見られました。前日の毎日新聞の調査(23~24日実施)でも支持率は33%で、前月比4ポイント増となっています。特に読売の調査では、石破首相は「辞任すべき(42%)」との回答を上回り、「辞任する必要はない(50%)」という意見が優勢でした。議院内閣制の日本では、選挙敗北が首相の辞任につながるのが通例ですが、7月の参院選敗北後にこの世論が逆転した点は極めて特筆すべきです。石破首相の辞任に反対する集会が首相官邸近くで開催されるなど、「自民党の保守化」に対する国民の懸念が世論調査の結果に影響を与えている可能性が指摘されています。
続投への強い意欲を示す石破首相は、この世論の追い風を受け、さらに勢いを増しているように見えます。日本の敗戦日であり終戦記念日でもある8月15日、石破首相は政敵である安倍晋三元首相とは異なる路線を明確にしました。追悼の辞では、安倍政権以降聞かれなくなった「反省」という言葉を13年ぶりに口にしたのです。さらに最近では、9月2日の日本の停戦協定調印に合わせて首相メッセージを発表することを検討していると報じられています。日本メディアによると、8月24日夜には都内の飲食店で小泉純一郎元首相と会談し、国政運営について意見を交わしました。戦後60周年談話を発表した小泉元首相から、戦後80周年に向けた首相の見解について助言を受けたものとみられ、歴史認識における姿勢を明確にする狙いがあると推測されます。
 石破茂首相、政権の岐路に立つ
石破茂首相、政権の岐路に立つ
外交成果を掲げ、退陣論を牽制する石破氏
自民党保守派を中心に退陣を求める声が強まる中、石破首相にとって外交は強力な武器となっています。石破首相は8月23日に韓日首脳会談を実施したのに続き、25日にはシンガポールのリー・シェンロン元首相、そして29日にはインドのナレンドラ・モディ首相との会談を控えています。読売新聞の報道によると、特に29日の日印首脳会談では、インドとの間で安全保障協力に関する共同宣言を17年ぶりに改定する予定です。中国を念頭に置き、インドとの経済協力を一層強化することが主要な目的となる見通しです。
その後の外交日程も途切れることなく続きます。9月にはイタリア首相の訪日、国連総会での演説、ASEAN(東南アジア諸国連合)関連の首脳会議が予定されています。さらに、先の李大統領との間で協力を約束した慶州APEC(アジア太平洋経済協力)も控えています。首相にしかこなすことのできないこれらの重要な外交日程は、石破氏の「辞任不可論」に説得力を持たせる大きな要素となるでしょう。国際舞台での存在感を示すことで、内政での求心力低下を補う狙いがあると考えられます。
依然として混迷深まる自民党内の動き
世論の支持や外交成果があるにもかかわらず、石破首相の政権維持が順調ではないとの見方が依然として優勢です。その背景には、自民党内部の複雑な状況があります。まず、参院選敗北の原因を徹底的に検証する総括報告書が9月初旬に完成する予定です。この報告書が発表されれば、党内で再び責任論が高まることが予想され、それに伴い森山幹事長の進退も決まるという観測が出ています。代案が不在の中、野党との政策協議を主導し、石破政権を支えてきた森山氏がもし辞任することになれば、石破政権にとって手痛い打撃となる可能性は否定できません。
政権を揺るがす危機として作用する要素は他にもあります。保守派議員を中心に「石破降ろし」の動きが活発化する中、自民党総裁選を前倒しするかどうかについて、「投票方式」の輪郭が9月中に明らかになる予定です。いわゆる「リコール」規定により、総裁選を前倒しするためには、所属議員および地域組織代表の過半数の賛成が必要です。ただし、反石破勢力が無記名投票を望んでいる一方で、現時点では記名投票に重きが置かれている点は、石破首相にとって追い風となり得ます。記名投票であれば、造反票が集まりにくくなるため、前倒しが難しくなる可能性があります。
法政大学大学院公共政策研究科の白鳥浩教授は、最近の石破首相の支持率上昇は外交的要素が強いと分析しています。続けて白鳥教授は、「見守るべきは一時的な支持率上昇ではなく、支持しないと答える約50%にものぼる無党派層の変化だ」と指摘しました。「支持率が上がったといっても30%台にすぎず、一時的に自民党の保守化への懸念から上昇した可能性がある」との説明です。また、白鳥教授は「現在の状況(少数与党)では、どのような法案も国会で成立させるのは不可能な状態だ」と述べ、立法府としての機能不全への懸念を示しています。最終的に「選挙総括報告書が発表された後、自民党内で責任論が再び噴出し、総裁選が前倒しになるかどうかが石破政権の去就問題を左右するだろう」と結び、9月の動向が政権の命運を握るとの見解を示しました。
石破首相は、世論の意外な支持と精力的な外交活動を背景に、党内からの退陣要求をかわそうとしています。しかし、党内情勢は依然として複雑であり、9月に発表される参院選総括報告書や総裁選の投票方式決定が、石破政権の今後を大きく左右することになるでしょう。「運命の9月」は、石破首相にとって政治手腕とリーダーシップが真に試される正念場となりそうです。