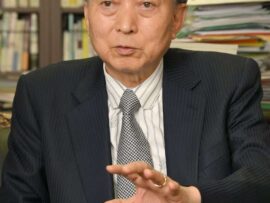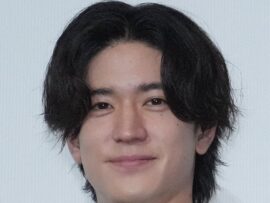日本の医療は世界でもトップクラスの質を誇るという認識は広く浸透しています。しかし、その「質の高さ」を支える具体的な仕組みや、それに伴うコスト、そして効率性については、深く知られていない側面も多いのが実情です。本稿では、客観的なデータに基づき、日本の医療が直面する課題、特に病床数と平均在院日数に焦点を当て、その実態を「医療の価値」という視点から詳細に分析します。私たちは本当に最適な医療を受けているのでしょうか。
 日本の医療制度、病院のベッド数や入院日数をデータで分析するイメージ。
日本の医療制度、病院のベッド数や入院日数をデータで分析するイメージ。
世界一の病床数、その多さは「良いこと」なのか?
2020年時点のデータによると、人口1,000人当たりの病床数(主に急性期医療を提供する病床)において、日本は経済協力開発機構(OECD)加盟国の中で最多を記録しています。この事実を「医療が手厚い証拠」と捉える見方もあるでしょう。しかし、医療の真の「価値」は、「医療の質 ÷ コスト」という方程式で考えることができます。質の高さはもちろん重要ですが、それに要するコストが過剰であれば、医療の価値は相対的に低下してしまうのです。
例えば、病床数が実際の医療需要(実需)を大きく上回る場合、病床の過剰供給は病院経営の収益悪化を招きかねません。また、後述する平均在院日数の長期化は、医療従事者一人当たりの患者対応数を増加させ、結果として彼らの負担増大や離職率の上昇に繋がり、病院経営の持続可能性にも深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。こうした観点から、日本の医療システムにおいては、実需に見合った適切な病床数を目指すことが喫緊の課題と言えるでしょう。
長期入院は「手厚いケア」か、「病院経営」のためか?
日本の平均在院日数は、諸外国と比較して顕著に長く、約16日と他国の2倍以上に達しています。この長期入院の傾向は、「患者に対する手厚いケア」の表れと肯定的に受け取られることもありますが、その背景には「病院経営上の都合」という側面があることも否めません。
入院日数が長期化する要因は多岐にわたりますが、急性期医療を終えた患者や、もともと急性期ではない患者に必要な回復期病床の不足が挙げられます。これにより、これらの患者が急性期病床を長期間利用せざるを得ない状況が生じています。さらに、現行の診療報酬制度の仕組みが、過剰に存在する急性期医療の病床を埋めるために、患者を長く在院させるインセンティブとして機能しやすい構造になっていることも、この問題に拍車をかけています。
DPC/PDPS制度がもたらす「長期入院インセンティブ」
患者を長く入院させるインセンティブが働く背景には、日本の急性期病院の多くに適用されている「診断群分類包括支払い制度(DPC/PDPS)」が大きく影響しています。この制度では、入院患者の病名や治療内容に基づいて、国から病院に支払われる1日あたりの報酬が定められています。
DPC/PDPS制度では、入院期間が長くなるにつれて1日あたりの診療報酬は段階的に減少するよう設定されていますが、入院期間中である限り報酬は発生し続けます。一方、欧米で一般的な包括支払い制度では、1日あたりの報酬ではなく、「1入院あたり(より正確には1疾患あたり)」の包括払いが主流です。この欧米型の制度では、治療を早期に完了させ、在院日数を短縮するインセンティブが強く働きます。ただし、早期退院が未完治による再入院や合併症のリスクを高める可能性もあるため、欧米ではこれに加えて「医療の質指標」を可視化し、その「質」を報酬制度に組み込むことで、適切な医療提供と効率性を両立させようと試みています。
まとめ
本稿では、日本の医療システムにおける病床数の過剰と平均在院日数の長期化という二つの側面を、データに基づいて分析しました。日本の医療は高い質を維持していますが、その背後には「医療の価値」を低下させかねない非効率性や、病院経営上の課題が潜んでいます。実需に見合った病床数の調整、回復期病床の拡充、そして診療報酬制度の見直しにより、真に患者のためとなる、持続可能で質の高い医療体制を構築することが、今後の日本の医療にとって不可欠と言えるでしょう。