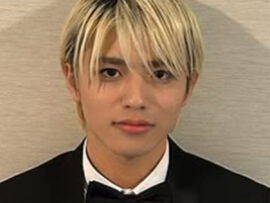参院選での与党大敗後、自民党内で石破茂首相(自民党総裁)の去就を巡る権力闘争が激化しています。「石破降ろし」を求める声が高まる中、臨時総裁選の実施を求める動きが見られますが、党執行部の提示した条件がその勢いを鈍化させています。本稿では、首相続投の是非を問うこの攻防の深層に迫り、今後の政局の行方を分析します。
参院選大敗後の「石破降ろし」と臨時総裁選への動き
7月20日に投開票が行われた参院選で、自民・公明両与党は歴史的な大敗を喫しました。しかし、石破茂首相がその責任を明確に取ろうとしない姿勢に対し、自民党内からは「石破降ろし」の動きが活発化。これに伴い、任期満了を待たずに総裁選を実施する「臨時総裁選」の前倒しを求める声が急速に高まりました。当初、この「石破降ろし」の勢いは強く、現職総裁の辞任に追い込む可能性も指摘されていました。
臨時総裁選の「蘇生装置」化:執行部の戦略と政局の変化
しかし、事態は新たな局面を迎えます。森山裕幹事長を始めとする自民党執行部は、臨時総裁選を実施するための要件として、党所属国会議員と都道府県代表の過半数の要求に加え、「書面での提出」と「氏名の公表」を義務付ける方針を示しました。この条件が発表されると、「石破降ろし」を求める動きの勢いは目に見えて衰えました。もし臨時総裁選が成立しなければ、それは事実上、石破総裁の続投が信任されたことを意味します。本来、時の総裁を辞任させる装置として機能するはずの臨時総裁選が、皮肉にもその総裁を「蘇生させる装置」へと転化しつつあるのです。この状況は、「首相続投」派にとっても「石破降ろし」派にとっても、後には引けない総力戦の様相を呈しています。
 石破茂首相が自民党役員会に出席し、深刻な表情で議論に耳を傾ける様子
石破茂首相が自民党役員会に出席し、深刻な表情で議論に耳を傾ける様子
9月2日に予定されている自民党両院議員総会では、参院選総括委員会が大敗の要因を盛り込んだ報告書を提出する予定であり、これを機に政局が再び大きく動き出すと予想されます。森山幹事長は「責任を明らかにする」と述べていますが、その進退は不透明です。また、臨時総裁選は果たして成立するのか、そして石破首相は次の手として何を打ってくるのか、多くの注目が集まっています。
石破首相の延命を狙う「心理戦」と党則の活用
臨時総裁選を巡る動きは、8月8日の両院議員総会で具体化しました。有村治子会長(参院議員、麻生派)が議決機関である総会として、総裁選管理委員会に対し実施の是非を判断するよう申し入れを行い、これを逢沢一郎委員長(衆院議員、無派閥)が受諾。実施に向けた手続きが進められることになりました。自民党の党則6条4項には、総裁の任期満了前であっても、党所属国会議員295人と都道府県連代表47人の総数342人の過半数、つまり172人以上の要求があれば総裁選を行うと定められています。この規定は、2001年に森喜朗首相・総裁に党内から退陣要求が出たことを契機に設けられたもので、現職総裁も出馬は可能ですが、党内の過半数から辞任要求が出れば勝ち抜くことは極めて困難とされ、事実上の「総裁リコール規定」として知られています。この規定の運用を巡る「心理戦」が、石破首相の政治生命を左右する重要な鍵を握っています。
結論
自民党内の石破茂首相の去就を巡る権力闘争は、参院選大敗後の党内刷新を求める声と、現職首相の延命を図る執行部の戦略が複雑に絡み合い、極めて流動的な状況にあります。臨時総裁選という、本来は総裁を辞任させるためのメカニズムが、条件設定によって総裁を「蘇生」させる装置と化すという皮肉な展開は、今後の日本の政治に大きな影響を与えるでしょう。9月2日の両院議員総会を控え、この政局がどのような結末を迎えるのか、そして日本の政治はどこへ向かうのか、引き続き注視していく必要があります。
参考文献:
- Yahoo!ニュース (2025年8月30日). 「自民党役員会に臨む石破茂首相=2025年8月26日、東京・永田町の同党本部」.
https://news.yahoo.co.jp/articles/6f1dc64073e1e7cc8c8625bf6807e719c9f71ff7