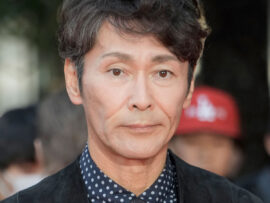日本の夏の象徴として親しまれてきたセミの鳴き声が、記録的な猛暑の中で異例の沈黙を見せています。例年であればけたたましく響くはずのその声が、気温のピーク時には聞こえず、むしろ暑さが和らいだ頃に耳にするようになったとして、「涼しさの目安」として捉える声がSNSを中心に広がり、新たな夏の感覚が生まれています。この興味深い現象の裏には、一体どのような生態の変化があるのでしょうか。
記録的猛暑とSNSの「セミ異変」
気象庁の発表によると、2025年8月5日には群馬県伊勢崎市で41.8度という過去最高気温が観測されるなど、今年の夏は全国各地が経験したことのない猛暑に見舞われました。こうした異常な気温の中で、X(旧Twitter)上では8月下旬頃から、セミの鳴き声に関する異変が話題となっています。
「一番暑かった時期にはセミが鳴いてなくて変な夏だなと思ってた」
「最近じゃ『やっと蝉が鳴く気温まで下がったね』とか家族で話してる…」
「すでに蚊は夏の風物詩ではなく、涼しくなったら刺されるという存在になってるから、セミもそうなる日は遠くないかも…」
「実際マシな気温かどうかを手軽に知る為の目安にしてる」
これらの投稿は、セミの鳴き声が「暑さの象徴」から「涼しさの目安」へと、人々の間でその意味合いが変わりつつあることを示唆しています。
 猛暑の中で静かに木にとまるセミ。夏の風物詩であるセミの鳴き声が、異常な気温により減少している現状を象徴するイメージ。
猛暑の中で静かに木にとまるセミ。夏の風物詩であるセミの鳴き声が、異常な気温により減少している現状を象徴するイメージ。
専門家が語るセミの「暑さ対策」と種別行動
セミと猛暑の関係について、防虫サービスなどを手掛ける東洋産業(岡山市)の名物社員で、虫の生態に詳しい大野竜徳氏は、J-CASTニュースの取材に対し「セミも暑くなりすぎると鳴かずに涼しい場所で暑い時間をやり過ごします」と語っています。
具体的にはセミの種類によって耐えられる温度が異なるといい、西日本に多く生息するクマゼミは「33度くらいが限界」で、「30度くらいだと元気に鳴きます」と説明。一方で、関東を中心にみられるミンミンゼミは例外で、「35度でも鳴きます」とその特徴を挙げました。これにより、セミが鳴く環境は種によって差があることが分かります。
変わる「夏の感覚」:セミの鳴き声が示す現代の「涼しさ」
大野氏は、セミを涼しさの象徴や目安とする見方について、現代の異常な気象状況を背景に、私たちの「夏の感覚」そのものが変化している可能性を指摘しています。
「昔と比べて異常な暑さなのは間違いありません。文字通り『セミも鳴けない』暑さになっています。セミが鳴けば涼しい日、と感じるのは人の感覚も変わってきたのかもしれません(33度くらいまでは元気にセミが鳴くと考えて、33度は涼しいですか? おそらく20年前だったらこの気温はものすごい暑い日、と言っていたのでは?)。自然を主観的に感じる今の私たちには昔とは違う感覚になっているのでしょう」
かつては「猛暑日」と認識された33度の気温も、40度を超えるような極端な暑さを経験した後では、セミが鳴き始める「比較的涼しい」と感じられるようになるという、人間の適応と気候変動の影響を浮き彫りにしています。
まとめ
今年の日本の夏に見られた「セミが鳴かない猛暑」という現象は、単なる季節の移ろいを超え、気候変動が私たちの日常や感覚に深く影響を与えていることを示しています。セミの鳴き声が「涼しさの目安」となるという社会的な観察は、生物の生態変化だけでなく、人間が異常気象に適応しようとする中で生まれる新しい認識と価値観の表れと言えるでしょう。この変化は、これからの夏の過ごし方や、環境問題への意識を再考するきっかけとなるかもしれません。
参考文献
J-CASTニュース(2025年8月31日)「『セミも鳴けない』異常な暑さ…猛暑で鳴き声に異変?専門家が語る生態、SNSで『涼しさの目安』の声」
https://news.yahoo.co.jp/articles/d07b3ed68d4e91ebb164f187708a5aae993fa663