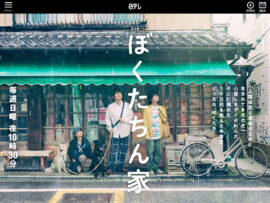高齢ドライバーによる痛ましい死亡事故が報じられるたび、「年を取ったら自動車の運転免許証は返納すべきだ」という声が社会で高まります。しかし、当事者やその家族が「返納しようにもできない」と苦悩する、見過ごされがちな現実があるのではないでしょうか。本記事では、免許返納をめぐって葛藤する人々の声と、交通心理学の専門家の見解を通じて、この複雑な社会問題を多角的に考察します。
免許返納がもたらす「想定外の不自由」:81歳女性の証言
愛知県で夫と二人暮らしをする81歳の女性は、今年1月に自動車の運転免許証を自主返納しました。自宅周辺にはのどかな畑が広がり、以前は都市部まで車で30分かけて買い物に出かけ、車椅子生活の82歳の夫を病院へも自らが運転して連れて行っていました。そんな生活の中、女性はなぜ返納を決断したのでしょうか。
「高齢になり心身ともにおぼつかなくなってきたからです。自分で気をつけて運転していても、万が一事故に巻き込まれたら、病気の夫がいま以上に困ることになる。運転に不安を感じ始める前に、やめようと決意しました」と彼女は語ります。
当初、女性は免許を返納しても「なんとかなる」と考えていました。食料品は移動スーパーや宅配サービスを利用し、夫の通院費は年金を節約してタクシーで賄えばよい、と。しかし、現実の生活は想定とは大きく異なりました。
 高齢者の運転免許返納を検討する家族の姿。高齢ドライバーの判断と家族の支え。
高齢者の運転免許返納を検討する家族の姿。高齢ドライバーの判断と家族の支え。
「移動スーパーは品数が少なく値段も高い。生活費をおろしに郵便局へ行ったり、壊れたお風呂のふたを買いに行ったりと、自分のペースですぐに出かけられないのが不便で仕方ありません。夫の通院も、自宅玄関や病院の待合室で20分、30分と車椅子のままタクシーを待つのが本当に辛いのです。様々なことが、予想外の負担となりました」
現代社会において、高齢者の運転に対する視線は厳しさを増しています。事故が起きるたびに、SNSでは「高齢者だから運転するべきではない」といった声が溢れます。果たして、「高齢者は一律に運転免許を返納すべき」なのでしょうか。
「年齢で区切る問題ではない」交通心理学専門家が指摘する現実
九州大学大学院教授で交通心理学を専門とする志堂寺和則さんは、「そこは微妙なところ。年齢だけで決めることではないと思います」と述べ、社会の一般的な認識に疑問を呈します。警察庁の資料によると、高齢者ではない年齢層の死亡事故が大幅に減少している一方で、高齢者の死亡事故の減少幅は小さく、全体に占める割合が増加しているのは事実です。しかし、志堂寺さんは、その背景にはあまり知られていない事柄や「ミスリード」が存在すると指摘します。
「高齢者の運転による事故で、誰が亡くなっているかをご存じでしょうか。実は、約7割が高齢の本人あるいは同乗者であり、この割合の高さは若い人の運転による事故と大きく異なる特徴です。多くの人が、『高齢ドライバーがブレーキを踏み間違えたりして他人をケガさせている』といったイメージを持ちがちですが、これは実態とはかけ離れています。もちろん、加齢によって運転能力が低下する側面はありますが、あくまでも『思うように運転ができなくなったら返納すべき』なのであり、例えば『80歳になったら』などと年齢で一律に区切る問題ではありません」
志堂寺教授の指摘は、高齢者の運転免許返納問題が、単なる年齢制限や社会的な感情論では解決できない、より深い課題を抱えていることを示唆しています。個々の運転能力や生活環境、そして地域社会のサポート体制を総合的に考慮した上で、慎重な判断が求められるのです。
結論
高齢者の運転免許返納は、社会全体の安全に関わる重要な問題である一方で、当事者や家族の生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。今回の事例と専門家の見解は、この問題が単なる「高齢だから返納すべき」という単純なものではなく、個人の心身の状態、地域の交通環境、そして返納後の生活をいかに支えるかといった多角的な視点から考察されるべきであることを浮き彫りにしました。
高齢ドライバーが適切な時期に安全な運転を終えるためには、年齢だけで一律に判断するのではなく、「運転に不安を感じた時」という個々の判断を尊重し、社会全体でその後の生活を支える具体的な仕組みづくりが不可欠です。地域交通の改善や代替移動手段の充実、そして家族や行政によるきめ細やかなサポート体制の構築が、誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けた鍵となるでしょう。
参考文献
- 高齢の家族に免許返納は「すべき」か否か 「返納できない」リアルな背景を交通心理学の専門家が指摘 (Yahoo!ニュース / AERA dot.)