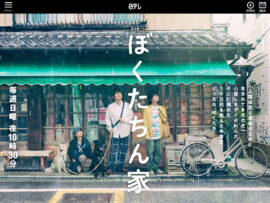高市早苗首相が維新との連立政権合意書で、来年の通常国会での実施を明記した大規模太陽光発電所(メガソーラー)への法的規制が注目を集めています。かつて再生可能エネルギーの象徴として推進された太陽光発電は、今や「規制」の対象として議論されており、その背景には安全管理や環境破壊、老朽化した施設の廃棄といった懸念が横たわっています。政府の政策転換が示唆する日本のエネルギー政策の新たな方向性に対し、現場からは不安の声も聞かれます。
 日本の農村地域に広がるメガソーラー施設と周辺の風景
日本の農村地域に広がるメガソーラー施設と周辺の風景
「美しい国土」と「悪い太陽光」:政策転換の背景
高市首相は、自民党総裁選出馬当初から「美しい国土を外国製の太陽光パネルで埋め尽くすことには猛反対だ」と述べ、メガソーラーに対する強い反対姿勢を示してきました。この動きは、2012年度に導入された固定価格買い取り制度(FIT)により、太陽光発電の設置が急増したことに起因します。資源エネルギー庁のデータによると、太陽光による発電電力量は2011年度の48億kWhから、2022年度には926億kWhと約19倍に増加しました。
この急速な普及に伴い、各地で建設反対運動が頻発。最近では釧路湿原国立公園周辺や千葉県鴨川市などでメガソーラー設置による環境破壊や土砂崩れのリスクが懸念され、地方自治体による独自の規制強化の動きが報じられています。こうした社会的な背景を受け、高市首相が規制強化を打ち出し、自民・維新の合意書にも「美しい国土を保全する重要性を確認し、森林伐採や不適切な開発による環境破壊及び災害リスクを抑制」するための規制実施が明記されました。石原宏高環境相もまた、「自然破壊、土砂崩れにつながる“悪い太陽光”は規制していかなくてはいけない」と発言し、政府として「質の悪い」太陽光発電への対応を強化する方針を明確にしています。
地域住民が見るメガソーラー:多様な声と未来への懸念
一方で、農村部では耕作放棄地などを活用した小規模なソーラーパネルの設置も進んでいます。実際にソーラーパネルのそばで暮らす人々の声は多様であり、そこには政策では捉えきれない現実が存在します。
利点と懸念が混在する共存の現実
栃木県高根沢町で2016年から稼働するメガソーラーの近くに住む60代男性・Aさんは、「稼働以来、特に困っていることはない」と語ります。反対運動もなく、「メガソーラーのせいで特に暑いと感じることもない」と話すAさん。「雑木林が開かれて見晴らしがよくなり、土地を貸したり売ったりした人は喜んでいるのではないか」と、一部の住民には経済的恩恵があったことを示唆します。しかし、今後のことには漠然とした不安を抱いており、「耐用年数を超えた後、このパネルの処分をどうするのか」という廃棄問題への懸念を示しました。別の60代男性・Bさんも同様に、「壊れた時や処分する時にどうするのかが決まっているのかも分からない。問題が出るとしたらそういうタイミングだろう」と、長期的な影響への不安を口にしています。

農家の視点:経済的メリットと課題
農業を営む60代男性・Cさんは、自らも知人の勧めで約3000万円を投じて300枚の太陽光パネルを設置しました。Cさんは、「借金返済までまだ17年ほどかかるが、遊ばせていた土地を活用でき、年間100万円くらいの利益になる」と語り、農業の不作時には大きな助けになっているとその経済的メリットを強調します。しかし、「売電価格も年々下がっているため、今後新たに参入する人は厳しいかもしれない」と、現状の課題も指摘しており、再生可能エネルギーの普及と持続可能性の間にある難しさを示唆しています。
結論
高市首相が推進するメガソーラー規制は、再生可能エネルギー導入における負の側面への対応として重要性を増しています。FIT制度による急速な普及がもたらした環境への影響や、住民からの懸念、そして将来的な廃棄問題は、単なるエネルギー政策にとどまらない、国土保全と地域社会の持続可能性に関わる喫緊の課題です。政府の政策転換は、開発と環境、経済的利益と社会的責任のバランスをいかに取るかという、より包括的な視点での議論と具体的な解決策が求められていることを浮き彫りにしています。