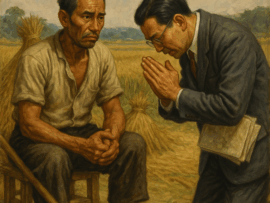今年7月の参議院議員選挙では、既存政党が苦戦し、新しい政治勢力が台頭しました。当初、選挙の主要な争点の一つは「生活の底上げ」であり、特に国民の懸念の中心にあったのは物価高騰問題でした。実際、生鮮食品を除く消費者物価指数は持続的に上昇傾向にあり、2020年を100とした場合、2025年7月には111.6を記録。これは’20年と比較して物価が10%以上上昇していることを示しており、多くの国民が生活の苦しさを感じている現状を浮き彫りにしています。
参院選の主要争点と与野党の公約
物価高騰への対策として、与党である自民党と公明党は「一律2万円の給付」を公約に掲げました。特に子どもが2人いる4人家族を例に挙げ、「合計12万円」の給付を前面に押し出し、その効果を強調しました。これに対し、野党は「消費税減税」を主要な対抗策として提案し、選挙戦では「給付か減税か」が大きな論点となりました。国民はどちらの政策が自身の生活を支えるのか、注目していました。

政局の混迷と与党公約の行方
しかし、選挙から1カ月余りが経過した現在、政治状況は混迷を極めています。参院選での大敗の責任を問われた石破茂首相は辞任の意向を示さず、「それでも比較第一党だ」と主張しましたが、自民党内では「石破おろし」の動きが活発化しました。一方で、石破内閣の支持率が上昇するという「石破辞めるな」旋風も起こり、党内は大きく混乱しています。近く開催される自民党両院議員総会で、石破首相の続投か退陣かが決まる見込みですが、こうした政局の混乱の中で、選挙公約は置き去りにされつつあります。
自民党は国民に「1人あたり2万円、子どもや住民税非課税世帯の大人には4万円」の給付を約束していましたが、8月に入って「一律給付の中止」が報じられました。自民党の大敗は、国民が一律給付に「ノー」を突きつけた結果とも解釈できます。また、与党が少数である現状では、野党の反対も予想され、公約実現は困難を極めるでしょう。国会での十分な議論も経ずに、選挙公約が反故にされることに対し、期待を寄せていた国民への説明や代替策は示されておらず、生活に困窮する人々は依然として取り残されたままです。
 参院選後の政局混乱と物価高騰に直面する市民の生活
参院選後の政局混乱と物価高騰に直面する市民の生活
野党による消費税減税実現の困難
一方、野党が掲げた消費税減税の実現もまた、厳しい状況にあります。その理由は主に三つ挙げられます。
第一に、野党が「一枚岩」にまとまっていない点です。各党の公約を見ると、立憲民主党は食料品の消費税を最長2年間ゼロ、国民民主党は実質賃金が持続的にプラスになるまで消費税を一律5%、日本維新の会は食料品の消費税を2年間ゼロ、日本共産党は消費税の廃止を目指し緊急的に5%に減税と、対象品目、引き下げ幅、期間など、すべてがバラバラです。これらの異なる提案を集約し、与党に迫る動きは見られません。
第二に、野党側の「やる気」の問題です。立憲民主党の野田佳彦代表は2012年に首相として消費税増税を推進した経緯があります。参院選では党内の減税派に推されて減税を掲げましたが、その真剣さには疑問符が残ります。また、減税期間を「最長2年」と限定することにも、その政策効果に対する疑念が生じます。
まとめ
参議院選挙で示された国民の生活を支えるための公約は、与党の「一律給付」も野党の「消費税減税」も、現在の政治状況の中では実現が困難な様相を呈しています。政局の混乱が続く中、物価高騰に苦しむ国民の生活への具体的な支援策は、宙に浮いたままです。政治がその役割を十分に果たせない状況において、国民一人ひとりが自身の生活を守るための対策を改めて見直す必要に迫られていると言えるでしょう。
参考資料
Source link: https://news.yahoo.co.jp/articles/d7bd687d7c421fc58f7e8224196c6b105f7c8316