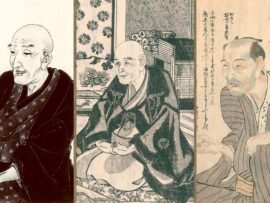2023年8月23日、東京・渋谷の商業施設「渋谷ヒカリエ」で発生した催涙スプレー噴射事件は、肩の接触から口論に発展した末の出来事でした。近年、街中で些細な体の接触が原因で大きなトラブルに発展するケースが散見され、その背景には現代社会の複雑な心理やSNSの影響が潜んでいると指摘されています。
街中で多発する「ぶつかりトラブル」の実態
渋谷ヒカリエの事件以外にも、歩行中の肩の接触が傷害事件に繋がる事例が相次いで報じられています。2024年9月には神奈川県のJR茅ケ崎駅前で、面識のない男性同士が肩をぶつけ口論となり、一方の男性が傘で顔面を突かれる事件が発生しました。また、2022年8月には神奈川県高津区の路上で、肩がぶつかりそうになったことを理由に顔面を殴られ、下あごを骨折する重傷を負う事件も起きています。これらの事件は、単なる偶然の接触が深刻な結果を招く可能性を示しています。
 街中で肩がぶつかり口論になる人々。現代社会における対人トラブルの増加を示唆するイメージ写真。
街中で肩がぶつかり口論になる人々。現代社会における対人トラブルの増加を示唆するイメージ写真。
「歩きスマホ」が引き起こす心理的摩擦
なぜこれほどまでに、肩がぶつかるという日常的な出来事が「キレる」きっかけとなり、傷害事件にまで発展するのでしょうか。東洋大学社会学部社会心理学科の戸梶亜紀彦教授は、その一因として「歩きスマホ」を挙げています。スマートフォン画面に集中し、イヤホンで周囲の音を遮断する行為は、公共の場にいるにも関わらず「完全なプライベート環境」を作り出します。このような状況で他者と接触すると、驚きだけでなく「自分の空間に侵入された」という強い怒りが芽生え、過剰な反応を引き起こしやすくなるのです。
「正義」を振りかざす「ぶつかり行為」とSNSの影
さらに戸梶教授は、「歩きスマホ」をしている人が、周囲から意図的に「ターゲット」にされる可能性も指摘します。「前を見て歩かない人が悪いのに、なぜ自分が道を譲らなければならないのか」という心理から、あえて道を避けず、時には「痛い目に遭わせてこらしめてやろう」と過剰な正義感を振りかざし、自らぶつかりに行く「ぶつかり行為」に及ぶケースさえあると言います。
X(旧Twitter)上では、「ぶつかりおじさん」「ぶつかりおばさん」といったワードで、このような意図的な接触行為が頻繁に報告され、リュック姿の男性が駅構内で次々と女性に肩をぶつけて歩く動画なども話題になりました。戸梶教授は、こうした「ぶつかり行為」の多発が、現代のSNS社会と関連しているという仮説を立てています。SNS上では、似たような思想を持つ人々がコミュニティを形成し、そこで発信される意見に多くの賛同が集まります。この現象は「エコーチェンバー」と呼ばれ、自分の考えが世の多数派であると錯覚し、自らの倫理観や善悪の基準を絶対視する危険性をはらんでいます。ネット空間での自己主張や批判が、次第に現実世界でも「正義」のためなら相手に身体的ダメージを与えても良いという攻撃性へと繋がり、対人トラブルを深刻化させている可能性が指摘されています。

結論
公共の場での「ぶつかりトラブル」は、単なるマナー違反に留まらず、現代社会における対人攻撃性の蔓延やSNSが助長する「エコーチェンバー」現象と深く結びついています。スマートフォン利用者の注意力の散漫と、他者への攻撃性を正当化する心理が複雑に絡み合い、社会全体に潜在する「闇」を浮き彫りにしています。この問題は、私たち一人ひとりが公共空間での振る舞いや、インターネット上の情報との向き合い方を見つめ直す必要があることを示唆しています。
参考文献
- AERA編集部・大谷百合絵 (2025年8月30日). 「肩がぶつかって“キレる”人の心理とは…」. Yahoo!ニュース.
(Source link: https://news.yahoo.co.jp/articles/227a16ea1ceff00fe1d16a5a86c0c40406000c6e)