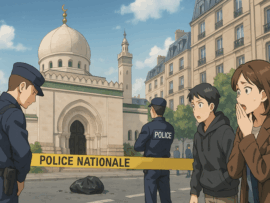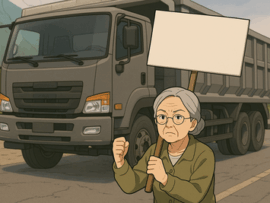去る9月6日、秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下の成年式が執り行われました。民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられているにもかかわらず、殿下が19歳の誕生日を迎えられたこの日に式典が行われたことは異例とされています。神道学者で皇室研究家の高森明勅氏は、この1年間の延期は秋篠宮殿下が「あえて悠仁殿下が18歳のうちに成年式を行うことを避け、前例のない選択をされたためではないか」と指摘しており、今回の成年式は、皇室が直面する現代的な課題を浮き彫りにしています。
40年ぶりの男性皇族成年式が示す皇室の現実
悠仁殿下の成年式は、男性皇族としては実に40年ぶりの出来事でした。これは、昭和60年(1985年)11月30日に行われた秋篠宮殿下の成年式以来のことです。この40年という長い期間は、秋篠宮殿下のご誕生から悠仁殿下がお生まれになるまでの間、皇室に男子が一人も誕生しなかったという、ある意味で厳しい現実を示しています。この間に内親王が4人、女王が5人と、合わせて9人の女性皇族が誕生しているにもかかわらず、男性皇族が生まれなかった事実は、現在の「男子のみ」という皇位継承ルールがいかに危うい基盤の上に成り立っているかを改めて我々に問いかけています。今回の成年式は、単なる通過儀礼に留まらず、皇室の将来を巡る議論に一石を投じる結果となりました。
女性皇族に成年式がない背景と現代的価値観との乖離
現在の皇室においては、女性皇族に成年式にあたる公的な儀式がありません。この背景には、明治時代に皇室のさまざまな儀式が整備された際、男性皇族の儀式については前近代の「元服」や「加冠」といった伝統をもとに「皇室成年式令」(明治42年、1909年)として制度化された一方で、女性皇族の伝統的な儀式であった「笄冠(けいかん)」や「着裳(ちゃくも)」が制度化されなかった経緯があります。これにより、前近代よりも「男性優位」に偏った制度が確立され、宮内庁がこれを見直すことなく慣例として踏襲しているのが現状です。男女がアンバランスな形で存在する儀式のあり方は、現代の多様な価値観に照らすならば、疑問を呈さざるを得ない点であり、皇室の方々のお気持ちにも沿わない可能性をはらんでいます。
 勲章を着用し、成年皇族としての風格を見せる悠仁親王殿下
勲章を着用し、成年皇族としての風格を見せる悠仁親王殿下
異例の「1年延期」が提起する謎
今回の悠仁殿下の成年式には、もう一つ大きな「謎」が伴っています。それは、殿下がご成年を迎えられてから、まる1年間も式典の挙行が延期されたという事実です。民法の改正により成年年齢が18歳に引き下げられたため、悠仁殿下は昨年のお誕生日をもってすでに成年を迎えられています。この際には、ご成年に関する記者会見もすでに行われており、その記憶は新しいことでしょう。にもかかわらず、晴れの儀式である成年式は、今年の19歳のお誕生日まで延期されました。この異例の判断が下された背景には一体何があるのか、皇室研究家らの間で様々な憶測を呼んでおり、その真意については公式な説明が待たれるところです。
結論
悠仁親王殿下の成年式は、40年ぶりの男性皇族の儀式であると同時に、異例の1年延期という形で執り行われました。この出来事は、皇位継承問題における男子継承の不安定さ、女性皇族の儀式における男女格差、そして成年年齢と儀式挙行時期のずれという、現代の皇室が直面する複数の重要な課題を浮き彫りにしました。これらの問題提起は、皇室の伝統と現代社会の価値観との調和という、今後の日本社会にとって避けては通れない議論を促すものと言えるでしょう。
参考文献
- 高森明勅氏による論考 (President Online 掲載)
- Yahoo!ニュース (記事掲載元)
- 皇室成年式令(明治42年皇室成年式令)
- 民法改正に関する政府発表資料