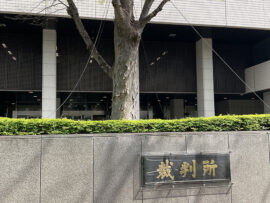近年、SDGs(持続可能な開発目標)やDEI(多様性・公平性・包括性)といった概念が社会のあらゆる場面で注目され、教育現場もその例外ではありません。これらは「新しい時代」を生き抜く上で不可欠な基本的な考え方とされています。しかし、現役東大生である土田淳真氏は、受験マンガ『ドラゴン桜2』の桜木建二が提唱する「メシを食う力」や「フラットな目線」の教育論を引き合いに出し、若者たちがこれらの概念に対して抱く「しらけた感情」や「うさんくさい」という本音について深く掘り下げています。この冷静な視線は、単なる反発ではなく、現代社会が抱える複雑な課題を浮き彫りにしています。
「しらけた感情」の背景にあるもの
若者たちがSDGsやDEIといった概念に対して抱く「冷めた感情」は、それらが「自分で生み出したものではない」という点に一因があるのかもしれません。「次の時代はこうだ」と暗黙の了解のように規定されることで、心からの自信や確信を持つことが難しいと感じています。一方で、彼らはこれらの規範に明確に反発しているわけでもありません。それは、SDGsやDEIに代わる「若者全体の統一意思としての」代替案が見当たらないからです。冷めた視線を持ちながらも、社会の構造を変える道筋や具体的な方法論を見つけられないという無力感が同時に存在しているのです。
「多様性」という言葉への違和感と「Z世代」の抵抗
「若者」とひとくくりにされること自体への抵抗も、この世代の特徴です。例えば、「Z世代」という言葉が流行語大賞にノミネートされた一方で、当事者である若者たちには「私たちはZ世代だ!」というような強い連帯感は薄いのが現状です。私たちの世代は趣味も好みも多様であり、それをSNSなどで臆することなくアピールしています。しかし、それは「多様性」という規範を目指した結果ではなく、個々人が好き勝手に行動した結果にすぎません。そのため、あたかもそれが「多様性という軸を大切にしている」というストーリーに当てはめられると、違和感を覚えることになります。
 三田紀房の漫画『ドラゴン桜2』の表紙
三田紀房の漫画『ドラゴン桜2』の表紙
抽象概念と「例外」の扱い:教育現場での向き合い方
「多様性」という言葉が持つ「キラキラと光り輝いているもの」という規範にとらわれることには危うさが伴います。例えば、かつて話題になった「トー横キッズ」も、見方を変えれば一つの多様性と言えるでしょう。しかし、彼らが多様性として扱われることは少なく、むしろ社会の異分子として描かれることが多いのが現実です。もちろん解決すべき社会問題が存在することは事実ですが、抽象的な概念を築こうとすると、本来想定していなかった「例外」の扱いに苦慮することが多々あります。「例外」とされる人々もまた人生を全うしており、無視されるいわれはありません。現実を直視するためには、「清濁合わせのむ」覚悟が求められるのです。
教育という視点から考えた時、SDGsやDEIといった「お行儀の良い」概念とどのように向き合うべきでしょうか。無批判に肯定することも、斜に構えて全否定することも望ましくありません。むしろ、これらを探求すべき材料として、「なぜこのような概念が生まれたのか」「現実にどのように応用され、どのような意見を集めているのか」といった多角的な分析を通じて、深く理解していくことが、これからの時代を生き抜くために重要な姿勢と言えるでしょう。