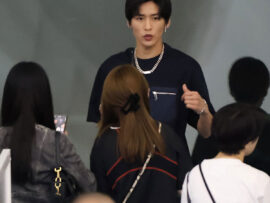2024年10月21日、自民党の高市早苗総裁が憲政史上初となる女性首相に選出され、日本の政治史に新たな一章を刻みました。高市氏が10月4日の自民党総裁選で新総裁に選出されてから17日目という異例の時間を要したこのプロセスは、少数与党に陥った自公政権が、公明党の連立離脱という困難に直面し、過半数確保が危ぶまれる中で進められました。しかし、この難局において、高市氏に救いの手を差し伸べたのが日本維新の会でした。維新との連携を通じて、新政権樹立への道が開かれたのです。
高市首相誕生までの道のり:難航した政権基盤の確立
高市氏が首相指名を受けるまでの道のりは、決して平坦ではありませんでした。総裁選後の自民・公明両党は、衆議院で過半数を割り込む少数与党の状態にあり、さらに公明党が連立から離脱を表明したことで、高市氏の首相指名は一時は極めて厳しい状況にあると見られていました。このような政治的真空状態の中、自民党は196議席、日本維新の会は35議席を擁し、両党が協力しても衆議院の過半数である233議席には2議席不足するという計算でした。自民党は、無所属議員らにも積極的な働きかけを行い、支持拡大を図りました。
その結果、10月21日に行われた衆議院での首相指名選挙の1回目の投票で、高市氏は237議席を獲得。決選投票を経ることなく、首相に指名されるという劇的な展開を迎えました。日本維新の会は、離党表明をしている議員がいるにもかかわらず、所属議員35人全員が高市氏に投票した模様です。これにより、維新は新たな連立パートナーとして、初めての重要な役割を果たすこととなりました。
 首相に選出された高市早苗氏(右)と日本維新の会の吉村代表が、連立交渉後に握手を交わす様子。憲政史上初の女性首相となる高市氏と、政策実現を掲げる維新の協力関係を示す一枚。
首相に選出された高市早苗氏(右)と日本維新の会の吉村代表が、連立交渉後に握手を交わす様子。憲政史上初の女性首相となる高市氏と、政策実現を掲げる維新の協力関係を示す一枚。
日本維新の会との「閣外協力」:政策実現を優先する姿勢
公明党とは異なり、日本維新の会は連立政権に参加するにあたり、大臣ポストを出さない「閣外協力」という異例の形式をとりました。高市氏は、維新との連立に向けた政策協議を進める中で、「閣内に入ってほしい」と大臣ポストの提供を求めていたとされています。しかし、維新側は大臣ポストを受け取らず、政策実現に徹する方針を伝えたといいます。
維新代表を務める吉村洋文大阪府知事は、テレビ番組出演時にこの点に触れ、「大臣ポストがほしいわけではありません。政策を実現したいんです」と強く発言しました。吉村代表が強調したのは、維新が自民党に突き付けた具体的な政策です。これには、大阪を想定した副首都に東京のバックアップ体制を築く「副首都構想」の推進、日本の将来を左右する「社会保障改革」、そして「衆議院の議員定数削減」などが含まれます。維新は、閣外からこれらの政策の実現を強力に後押しすることで、国民の負託に応えたいという姿勢を示しています。
維新内部に残る「ポスト要求」の声:政策実現と大臣職のジレンマ
しかし、日本維新の会内部には、閣外協力という形に疑問を呈し、大臣ポストを求める声も少なからず存在します。ある維新の衆議院議員A氏は、党内での議論を振り返り、「政策の実現のためには、総務大臣と厚生労働大臣を維新がとるべきという意見がけっこうあった。私も同感でした」と語っています。結果として、遠藤敬国対委員長が首相補佐官として官邸に入るにとどまり、閣外協力の枠を超えませんでした。
A氏によれば、党内では「大臣ポストが2、副大臣・政務官は合計で10」といった具体的な数字まで挙がり、旧民主党時代に外務大臣などを務めた経験がある前原誠司衆議院議員や、前代表の馬場伸幸衆議院議員を「適任」とする声もあったといいます。元神奈川県知事で、維新の松沢成文参議院議員は自身のX(旧Twitter)で、「早くフルスペックの閣内協力に格上げすべきだ。政策を実現するにはポストが必要。大阪副首都構想を実現するために、藤田(文武)共同代表自らが総務大臣として入閣するというウルトラCを出したら、維新の本気度が伝わって面白かったのに」と訴えました。維新内部では、松沢氏に賛同し、呼応する意見も少なからずあるとされており、政策実現の手段としてのポストの重要性が改めて議論されています。
高市氏の首相就任は、日本の政治に新たな風を吹き込むと同時に、日本維新の会との「閣外協力」という異例の連携は、今後の政権運営においてどのような成果と課題をもたらすのか、その動向が注目されます。政策実現を重視する維新の姿勢と、自民党との連携が、日本の未来にどのような影響を与えるのか、引き続き高い関心を持って見守る必要があります。
参考文献: