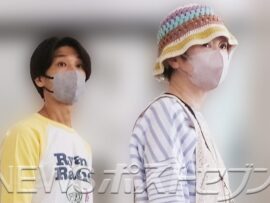近年、大学における有期雇用の研究者に対する「雇い止め」問題が社会的な関心を集める中、東京高裁が22日に下した判決が関係者の間で「画期的」と評され、大きな話題となっています。特に労働法に詳しい弁護士からも注目されるこの判決は、大学側の雇用慣行に一石を投じる内容です。
この裁判の原告は、千葉工業大学の国際金融研究センターで上席研究員を務めた荒川正頼氏(58)です。荒川氏は2020年4月から2年間、有期雇用契約で勤務。中央官庁の官僚を辞して転職した際、大学側からは4年目以降は無期雇用に転換するとの口頭での説明を受けていたと主張しています。しかし、2022年3月に同センターが廃止されることになり、大学側は荒川氏に対し雇用契約の打ち切りを提示。荒川氏がこれに応じなかったにもかかわらず、大学は同年3月をもって一方的に雇用関係を終了させました。
これに対し荒川氏は、自らの地位確認と未払い賃金などの支払いを求め東京地裁に提訴。地裁は今年3月、荒川氏の主張を大筋で認める判決を出しましたが、賞与の請求は認められず、双方ともに控訴していました。
東京高裁は、一審の地裁と同様に原告側の訴えを認め、「雇い止め」を無効とする判決を言い渡しました。この判決において特に重要視されたのは、大学が主張するセンター廃止の妥当性でした。高裁は、大学の理事会がセンター廃止を決議していないことを指摘し、「手続き的な不備があるものと言わざるを得ない」と厳しく断じました。
 千葉工業大学の校舎。大学での「雇い止め」問題が注目を集めている。
千葉工業大学の校舎。大学での「雇い止め」問題が注目を集めている。
大学側はセンターの所長が病気で不在だったことが廃止につながったと主張しましたが、判決は所長不在の中でも有意義なシンポジウムが開催されていた事実を挙げ、その主張を退けました。さらに、「理事会の決議事項として議論が尽くされていないことは、手続のみならず、判断の相当性についても影響し得るもの」と指摘。これにより、地裁では認められなかった賞与の支払いも大学側に命じる結果となりました。一審の東京地裁も、所長の去就を巡る大学側の感情的なもつれに言及し、「(廃止が)適切に検討された結果によるものなのか疑問が残る」としていました。
判決はまた、荒川氏が国家公務員として定年まで10年を残して転職してきた経緯も重視。「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」と結論付け、今回の「雇い止め」の不当性を明確にしました。
今回の東京高裁の判決は、大学における有期雇用の研究者に対する「雇い止め」の適法性を判断する上で、意思決定過程の手続き的な正当性と、雇い止めの理由の合理性が極めて重要であることを示唆しています。特に、長期的なキャリアパスを見据えて転職を決断した個人の事情を考慮する点も、今後の同様の訴訟における重要な判断材料となるでしょう。この判決は、教育機関における雇用慣行の見直しを促し、有期雇用者の法的保護を強化する上で大きな意味を持つものと期待されます。
参考文献
- Yahoo!ニュース (2024年10月27日). 「大学研究者の『雇い止め』は無効 東京高裁が『画期的』判決 なぜ」.
https://news.yahoo.co.jp/articles/15867b1c208867b451e967923661c1accd137d8f