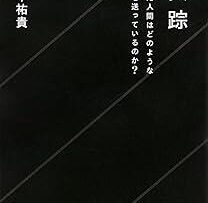NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の視聴者は、トキ(髙石あかり)が目撃した衝撃的な光景に驚きを隠せなかったことだろう。松江の街角で、トキの実母であるタエ(北川景子)が地面にござを敷き、物乞いをする姿が描かれたのだ。第6週「ドコ、モ、ジゴク」で示されたこの突然の零落は、多くの観客に「なぜ」という疑問を投げかけた。
一体、庭の広い豪邸で不自由なく暮らしていたタエが、なぜ路傍の物乞いへと転落してしまったのか。その背後には、ドラマが巧みに描き出す個人の物語と、明治維新後の激動の時代に「士族」と呼ばれる武士階級が直面した厳しい現実が横たわっている。
ドラマ『ばけばけ』が描くタエの零落
タエの三男であり、トキの実弟である雨清水三之丞(板垣李光人)が語ったところによれば、その経緯は過酷なものだった。トキの実父である傳(堤真一)の病死後、タエと三之丞は傳が経営していた機織り会社の借金返済のため、屋敷や家財を全て売り払ったという。その後、彼らは島根県安来の親戚を頼るが、三之丞が多少働いた際も、タエは「雨清水家の人間は人に使われるのではなく、人を使う仕事に就きなさい」と苦言を呈し、三之丞は働き口を失ってしまう。
どうにもならなくなった二人は松江に戻り、タエは物乞いとなり、三之丞は「人を使う仕事」を探すものの、当然ながら見つからないままだ。実母のあまりにも衝撃的な零落を目にしたトキは、当初は断っていた教師・錦織友一(吉沢亮)からの女中奉公の申し出を受けることを決意する。それは、実の母を助けるためには他に道がないと考えたからに他ならない。しかし、第7週に入ってもタエの物乞い生活は続き、トキが稼いだ金を傳からの預かりものと偽って三之丞に渡しても、彼の不器用なプライドがそれを母親に渡すことを阻むのだった。
第3週までは豪邸に住んでいたタエが、わずか数週間のうちにこれほどまでに零落することが現実にあり得るのか。そう疑問に思う視聴者もいるかもしれないが、この時代においては、それは十分に起こり得る悲劇だったのである。
明治維新と士族の運命:誇り高き武士階級の変遷
明治維新後、日本全国の旧藩は新政府に協力した側と、敗れた側に分かれた。松江藩は途中から新政府軍に恭順を示したものの、徳川家の親戚である「親藩」だったため、その態度は煮え切らず、結果として敗れた側と認識された。このため、新政府の要人からの縁故を期待することはほとんどできなかった。
しかし、松江の士族たちが維新後すぐに没落したわけではない。江戸時代までの武士は、主君への奉公の報酬として「家禄」を受け取って生活を営んでいた。明治2年(1869年)の版籍奉還後、貴族階級である華族にならなかった武士たちは「士族」となったが、しばらくの間は引き続き家禄が支給されていた。
だが、家禄の支給は国家財政にとって大きな負担となった。明治政府はまず明治7年(1874年)から8年(1875年)にかけて、士族からの家禄奉還(自主的な家禄の返上)を受け付けた。希望者には家禄の支給を打ち切る代わりに、その6年分を現金と、年8%の利子が付く秩禄公債として交付した(家禄と維新功労者への賞典禄を合わせたものが秩禄と呼ばれた)。
そして明治9年(1876年)、政府は「秩禄処分」を断行し、士族らに5年から14年分の家禄に相当する金禄公債証書を発行する代わりに、家禄の支給を全面的に廃止した。ここまではまだ良かったとされている。政府は家禄廃止に伴い、士族が就業することを奨励したが、問題はその後で顕在化した。
武士とは、いわば礼節と武芸しか知らない存在であり、そんな彼らがいきなり事業に乗り出したところで、成功させるのは至難の業だったのである。士族たちの多くは、受け取った公債を安易に事業に投資したり、誘いに乗じて投機に走ったりした。しかし、周囲には百戦錬磨の商人や老獪な詐欺師が跋扈しており、純粋培養されてきた士族たちは彼らの餌食となり、ひとたまりもなかった。こうして、公債を投じた士族の大半は短期間のうちにそれを失い、さらには家屋敷までも売却せざるを得ない状況に追い込まれていったのだ。
タエの物語は、まさにこの明治初期の士族階級が経験した劇的な社会変化と、それに伴う個人の悲劇を鮮やかに映し出している。ドラマは、個人の誇りや世間体といった感情が、経済的困難とどのように絡み合い、厳しい選択を迫るのかを深く問いかけていると言えるだろう。
参考文献:
- Yahoo!ニュース. (2025年11月14日). 豪邸に住む奥方から路傍の物乞いへ. https://news.yahoo.co.jp/articles/c2629da000a725d8329993f94c94baf5be23d339

 タエを演じる北川景子
タエを演じる北川景子