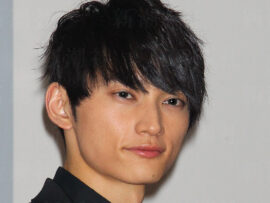地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」の配備計画停止を受け、装備の導入自体も白紙化することになれば弾道ミサイル防衛(BMD)構想も見直すことが急務となる。北朝鮮と中国の脅威をにらみ、発射直後の対処や「(発射前の)敵基地攻撃能力も代替案の選択肢」(政府高官)とされ、能力保有の検討が加速する可能性がある。
■技術向上を誇示した北朝鮮
イージス・アショアは装備の有効性に疑問符がつき始めている。北朝鮮が昨年、通常より低い高度を高速飛行するディプレスト軌道をとり、下降中の終末段階で変則的に上昇した後に落下する可能性のある新型短距離弾道ミサイルを4回にわたり8発撃ち、技術向上を誇示したからだ。
現行のBMDはイージス艦搭載の海上配備型迎撃ミサイル(SM3)と地対空誘導弾パトリオット(PAC3)の2段構えで、SM3は大気圏外を飛行している中間段階、PAC3は着弾直前の終末段階で迎撃する。地上配備型のイージス・アショアは海上配備型SM3を補うが、どちらもディプレスト軌道のミサイルを迎撃することは難しい。
■発射前・直後に電波・サイバー攻撃
イージス・アショアの導入自体も見送る場合、想定される代替案は2つある。
防衛省はミサイルと地上基地の電波送受信を遮断して、ミサイルを自爆に導く電波妨害装備の研究を今年度から始め、発射直後の上昇段階で対処することを目指しており、こうした研究開発を加速させるのがひとつ。もうひとつは発射前にミサイル発射基地や指揮統制施設を無力化させることを目指し、対処するための攻撃能力を保有する案だ。
米国も発射前と発射直後に電波妨害やサイバー攻撃を仕掛けて発射や飛行を妨げる作戦を重視しているため、幅広い装備開発や運用で日米協力を深められる。
日本は電波とサイバーを宇宙と並び重視する「新たな領域」と位置づけている。省内でコストカッターと呼ばれている河野太郎防衛相は巨額の経費がかかるイージス・アショアより、「BMDでも新たな領域の防衛に通じる装備に予算を投入すべきだとの判断に傾いているのでは」(自衛隊幹部)と指摘される。
(半沢尚久)