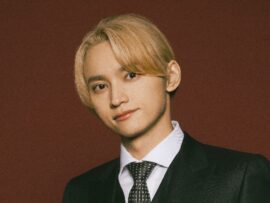日本の最東端、南鳥島。その周辺海域に眠る膨大なマンガンノジュール、そして希少金属をめぐる静かな攻防が始まっています。中国の国有企業が南鳥島沖の公海で海底採鉱試験を計画しているというニュースは、日本の海洋戦略の遅れを浮き彫りにするものでした。資源大国への道を歩む中国の野望、そして日本の取るべき道とは?
海底に眠る宝:マンガンノジュールの魅力
 南鳥島周辺の海底に豊富に存在するマンガンノジュール
南鳥島周辺の海底に豊富に存在するマンガンノジュール
マンガンノジュールは、深海底に存在する球状の鉱物塊で、マンガン以外にもコバルト、ニッケルなどの希少金属を豊富に含んでいます。これらの金属は、電気自動車のバッテリーやハイテク製品に不可欠な素材であり、その需要は世界的に高まっています。南鳥島周辺海域には、国内消費量の数十年分に相当するマンガンノジュールが眠っていると言われており、まさに海底の宝と言えるでしょう。
中国の深海戦略:海洋強国への布石
中国は、海洋強国戦略の一環として、海底資源の探査・開発に積極的に投資してきました。5000mを超える深海での採掘技術は、世界でも中国だけが保有していると言われ、今回の南鳥島沖での採鉱試験も、その技術力の高さを示すものです。国際海底機構の承認を得て、公海における探査権を獲得した中国は、着実に資源確保に向けた歩みを進めています。
日本の課題:海洋資源開発への遅れ

実は、南鳥島沖のレアアース鉱床を発見したのは、2012年の東京大学による調査でした。しかし、その後の日本の対応は遅く、海底資源開発への投資も限定的でした。「海洋国家」を標榜しながらも、具体的な行動が伴っていない現状は、中国との差をますます広げる結果となっています。海洋政策研究財団の佐藤一郎氏(仮名)は、「日本は海洋資源開発において、戦略的なビジョンと積極的な投資が不可欠です」と指摘しています。
公海の資源:国際的なルールと日本の対応
公海の海底資源は、「人類の共同財産」とされ、国際海底機構が管理しています。今回の中国の採鉱試験は、国際法上は問題ないとされていますが、日本としても、国際的なルールに基づきながら、自国の利益を守るための戦略を練る必要があります。具体的には、海底資源探査技術の開発、国際海底機構への積極的な参加、そして関係国との連携強化などが挙げられます。
未来への展望:持続可能な海洋開発
海底資源開発は、将来の資源確保という点で重要な意義を持つ一方で、海洋環境への影響も懸念されています。持続可能な開発を実現するためには、環境保護への配慮が不可欠です。日本は、環境保全技術の開発にも力を入れることで、国際社会におけるリーダーシップを発揮していくことが期待されます。