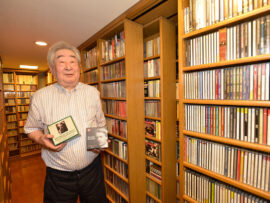新幹線での炭酸水の価格に元国土交通相が苦言を呈し、話題となっています。果たして、その価格は本当に「酷い」のでしょうか?この記事では、価格設定の背景、サービスの価値、そしてビジネスモデルの観点から、多角的に分析していきます。
価格設定の背景:単純比較はNG?
元国土交通相は、新幹線の炭酸水の価格を「通常価格の1.5倍以上」と指摘しました。スーパーやコンビニで販売されている炭酸水と比べると、確かに割高に感じられます。しかし、両者を単純に比較するのは適切なのでしょうか?
 新幹線で販売されている飲み物
新幹線で販売されている飲み物
新幹線での販売には、輸送コスト、在庫管理、スペースの制約、そして人件費など、小売店にはないコストが発生します。航空機の機内販売やホテルのミニバーも同様の理由で価格が高めに設定されています。
さらに、元国土交通相が利用したのは、グリーン車専用のモバイルオーダーサービス。これは、限られた利用者向けの特別なサービスであり、通常の販売価格とは異なる視点で捉える必要があります。フードサービスコンサルタントの山田一郎氏(仮名)は、「提供される場所、時間、そしてサービスの質を考慮すると、価格設定は妥当と言えるでしょう」と述べています。
移動中のサービス価値:利便性という付加価値
鉄道の車内販売は、単なる商品の売買ではありません。移動中に商品を購入できる利便性こそが、大きな価値と言えるでしょう。
 新幹線車内
新幹線車内
かつては、出張や旅行の際に車内販売を利用する人が多く見られました。しかし、コンビニや駅ナカ店舗の普及により、事前購入が一般的になり、車内販売のニーズは減少しました。人手不足も重なり、多くの新幹線でワゴン販売は廃止されています。
グリーン車専用のモバイルオーダーサービスは、「必要な人に、必要な分だけ届ける」という新しいニーズに応えるもの。利便性という付加価値を提供していると言えるでしょう。旅行ジャーナリストの佐藤花子氏(仮名)は、「移動中の貴重な時間を有効活用できる点で、このサービスは高く評価できる」と語っています。
新幹線におけるビジネスモデル:変化への対応
新幹線のビジネスモデルは、時代の変化に合わせて常に進化しています。かつて主流だったワゴン販売から、モバイルオーダーサービスへの移行は、その一例と言えるでしょう。
少子高齢化、人口減少、そしてコロナ禍といった社会情勢の変化は、鉄道業界にも大きな影響を与えています。顧客ニーズの多様化、コスト削減の必要性、そしてサービスの質の向上など、様々な課題に直面しています。
このような状況下で、新幹線は新たなビジネスモデルを模索し続けています。モバイルオーダーサービスは、その試行錯誤の一つと言えるでしょう。価格設定も、これらの要素を総合的に考慮して決定されています。
まとめ:多角的な視点が重要
新幹線の車内販売の価格設定は、様々な要因が複雑に絡み合って決定されています。単純な価格比較ではなく、サービスの価値、ビジネスモデル、そして社会情勢といった多角的な視点から考察することが重要です。
あなたはどう思いますか?ぜひ、コメント欄で意見を聞かせてください!また、この記事が役に立ったと思ったら、シェアをお願いします。jp24h.comでは、他にも様々な情報を発信しています。ぜひ、他の記事もご覧ください。