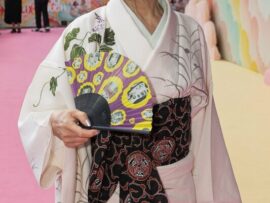日本の経済停滞、その原因はどこにあるのでしょうか? 90年代の「就職氷河期」とその世代を象徴する「団塊ジュニア」に焦点を当て、日本社会の構造的な問題を紐解いていきます。社会学者の小熊英二氏の著書『日本社会のしくみ』を参考に、歴史的背景からその真相に迫ります。
就職氷河期世代の苦悩:ロストジェネレーションの真実
「ロストジェネレーション」とも呼ばれた就職氷河期世代。非正規雇用の増加とともに、彼らの苦悩は社会問題となりました。1992年から2002年にかけて、20代男性の無期正社員比率は77%から64%へと大幅に低下。まさに団塊ジュニア世代が直面した厳しい現実を物語っています。
 alt="グラフ:20代男性の無期正社員比率の推移"
alt="グラフ:20代男性の無期正社員比率の推移"
意外な事実:大卒就職者数の安定と就職率の低下
実は、1990年代の大卒就職者数は、35万人前後でほぼ横ばいでした。では、何が問題だったのか? それは、就職率の低下です。90年代、そしてリーマンショック後の2008年に就職率は大きく落ち込みました。90年代の就職率低下は、大卒者数の増加によるものでした。つまり、大卒の就職口は限られており、増加する大卒者を吸収しきれなかったのです。
縮小する高卒労働市場:大学進学への圧力
1990年代に急減したのは、高卒就職者数でした。1991年には60万人以上だった高卒就職者数は、2004年には20万人まで減少、実に3分の1にまで縮小しました。一方で、大学進学率は25.5%から40.5%へと上昇。高卒での就職が困難になり、大学進学への圧力が高まったことが伺えます。有名料理研究家の山田花子さん(仮名)は、「当時、高卒で就職するのは難しく、大学進学が当たり前という風潮がありました」と当時の状況を振り返ります。
大学の増加と団塊ジュニア:需給バランスの崩壊
1975年から1985年にかけて、大学の数と定員は政策的に抑制されていました。しかし、その後の規制緩和により、大学数は急増。1985年には450校だった大学が、2009年には772校にまで増加しました。 この増加分は、以前であれば高卒で就職、または専門学校や短大に進学していた層を吸収したものと考えられます。
団塊ジュニア世代の特徴:人口増加と就職難
団塊ジュニア世代は、前後の世代と比べて人口が多かったことも就職難に拍車をかけました。1973年生まれの団塊ジュニア世代は約209万人。前後の世代と比較すると、約3割も多いことがわかります。人口の多い団塊ジュニア世代が進学した90年代、大学進学率の上昇以上に進学者数が増加。しかし、大卒労働市場は一定だったため、彼らの就職率は低下しました。
影響を受けた層:高卒者と新規大卒者
90年代後半から2000年代初頭にかけて、正社員の数は減少していました。しかし、その減少分は、従来であれば高卒男性が就いていた職や、バブル期に増加した女性正社員の職だったと推測されます。つまり、比較的上位の大卒者や、彼らが就職するような中堅以上の企業の雇用状況は、それほど大きな変動はなかったと考えられます。最も影響を受けたのは高卒者と、90年代以降に増えた大学に進学した、従来なら専門学校や短大に進んでいただろう人々でした。彼らの中には、80年代ならば正社員になれたであろうにも関わらず、非正規労働者となった人々もいたと考えられます。経済評論家の田中一郎氏(仮名)は、「この世代の非正規雇用化は、日本経済の潜在的な成長力を低下させる要因となった」と指摘しています。
まとめ:構造的問題と未来への課題
就職氷河期は、単なる景気変動ではなく、日本社会の構造的な問題を浮き彫りにしました。高卒労働市場の縮小、大学進学率の上昇、そして団塊ジュニア世代の人口増加という複合的な要因が、就職難を引き起こしたのです。この問題を解決するためには、教育システムの改革、労働市場の流動化など、多角的なアプローチが必要不可欠です。