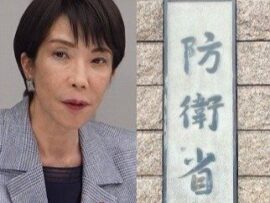壱岐島沖で発生した医療ヘリコプターの転覆事故は、痛ましいことに死者3名を出した深刻な事態となっています。事故の全容解明が急がれますが、新たな情報が入ってきました。機長が手動でフロート(浮き具)を作動させていたことが明らかになり、不時着水を試みた可能性が高まっているのです。
事故概要と新たな情報
2025年4月6日、長崎県壱岐島沖で患者搬送中の医療ヘリコプターが転覆。搭乗者6名が救助されましたが、搬送中の患者である本石ミツ子さん(86)、医師の荒川渓さん(34)、そして本石さんの息子である和吉さん(68)の3名の死亡が確認されました。
関係者への取材によると、機長は唐津海上保安部に対し、緊急着水時に使用するフロートを手動で作動させたと説明しています。このことから、事故前に何らかの異変を察知し、安全確保のための行動をとったと推測されます。運輸安全委員会の航空事故調査官も「不時着した可能性が高い」との見解を示しており、事故原因の究明が進められています。
 救助活動の様子
救助活動の様子
救命胴衣の未着用と運航会社の過去
今回の事故で、搭乗者全員が救命胴衣を着用していなかったことも判明しました。運航会社であるエス・ジー・シー佐賀航空では救命胴衣を機内に配備していましたが、通常は着用せずに運航していたとのことです。航空法に基づく細則では、洋上運航時の救命胴衣着用が一部義務付けられていますが、救急搬送など医療上の理由で困難な場合は対象外となっています。佐賀航空は片方のエンジン停止時に救命胴衣を着用する規定を設けていましたが、今回の状況が規定に該当するかは不明です。救命胴衣の着用が生存率に影響した可能性も視野に入れ、調査が進められています。
実は、佐賀航空は2024年7月にも別のヘリで死亡事故を起こしており、福岡和白病院は患者搬送の委託を一時停止していました。「安全が確保された」との説明を受け、約5ヶ月前に再開した矢先の事故発生となりました。
佐賀航空の安全管理体制に疑問符
佐賀航空所有の機体は過去にも墜落や不時着などの事故を起こしており、安全管理体制に疑問の声が上がっています。2004年12月には佐賀県で墜落事故を起こし3名が死亡、2008年7月にも長崎県で墜落事故を起こし死傷者が出ています。今回の事故を受け、佐賀航空の宮原幸徳・統括航空事業本部長は謝罪しましたが、再発防止策の徹底が求められています。
事故原因究明と今後の対策
今回の事故は、医療搬送における安全性の重要性を改めて浮き彫りにしました。機長の迅速な対応により、全員が救助されたことは不幸中の幸いです。しかし、3名の尊い命が失われたことは重く受け止めなければなりません。運輸安全委員会と海上保安部は、事故原因の究明を急ぐとともに、関係機関と連携して再発防止策の検討を進める必要があります。
事故発生場所
専門家の声
航空安全の専門家である佐藤一郎氏(仮名)は、「今回の事故は、医療搬送における安全管理の徹底が改めて求められる事例だ。救命胴衣の着用基準や緊急時の対応マニュアルなど、関係機関が連携して見直しを進める必要がある」と指摘しています。
事故の全容解明と再発防止策の確立が急務であり、今後の動向が注目されます。