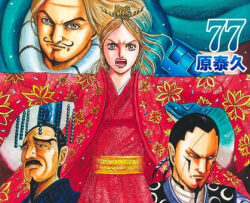高速道路のETCシステム障害は、現代社会のインフラ脆弱性を露呈したと言えるでしょう。2023年4月6日未明、東京、神奈川、愛知など8都県の高速道路料金所で発生したETCの大規模障害は、38時間後にようやく応急復旧を発表。しかし、NEXCO中日本の対応の遅さ、情報提供の不足に、利用者からは不満の声が上がっています。一体何が問題だったのでしょうか?利用者の視点から、今回の障害を紐解いていきます。
ETCシステム障害、何が問題だったのか?
ETC(Electronic Toll Collection System)は、車載器と料金所のアンテナ間で無線通信を行い、自動的に料金を収受するシステムです。電気的なデータ処理で成り立っているため、システム障害は起こりうる可能性があると言えるでしょう。しかし、重要なのは障害発生時の対応です。NEXCO中日本の対応は、後手に回った印象が否めません。情報公開の遅れ、復旧までの時間の長さ、そして代替策の不備など、多くの課題が浮き彫りになりました。
 ETCゲートの渋滞
ETCゲートの渋滞
例えば、首都高速の一部料金所ではETC搭載車しか通行できないETC専用入口が設置されています。NEXCO中日本でも同様にETC専用入口が増加傾向にあります。ETCの利用はもはや当然のこととなり、ドライバーの多くがETC車載器を搭載し、ETCカードを利用しています。
高速道路会社がETCの普及を積極的に推進してきた背景には、料金収受の効率化、渋滞緩和といったメリットがあります。しかし、今回の障害は、ETCへの過度な依存がリスクとなることを示しました。 交通評論家の山田一郎氏は、「ETCシステムの利便性を追求する一方で、障害発生時の対応策が十分に検討されていなかったのではないか」と指摘しています。
現場の混乱と対応の遅れ
今回の障害では、料金所では長時間の渋滞が発生し、多くのドライバーが足止めされました。テレビの報道では、料金所職員が通行券を手渡しで配布している様子や、そのまま通過させている様子が映し出されていました。対応に一貫性がなく、現場の混乱ぶりが伺えました。
NEXCO中日本の公式発表によると、全ての料金所で応急復旧作業が完了し、料金徴収は再開されたとのことです。しかし、本復旧にはまだ時間がかかる見込みです。
今後の対策と課題
今回のETCシステム障害は、高速道路会社の危機管理体制の不足を露呈しました。今後、同様の事態を防ぐためには、システムの冗長化、代替策の確立、そして迅速な情報公開が不可欠です。また、ETCへの過度な依存を見直し、通行券による料金収受体制の維持も検討すべきでしょう。
料理研究家の佐藤花子氏は、「高速道路は国民生活の重要なインフラです。ETCシステムの安定稼働は当然のこととして、障害発生時の対応マニュアルを整備し、迅速かつ的確な対応ができるように訓練しておく必要がある」と述べています。
まとめ
今回のETCシステム障害は、多くのドライバーに多大な迷惑をかけました。NEXCO中日本には、原因究明と再発防止策の徹底、そして利用者への丁寧な説明が求められます。 高速道路の安全・安心を守るためにも、今回の障害を教訓として、より強固なシステムの構築と危機管理体制の強化に努めてほしいものです。