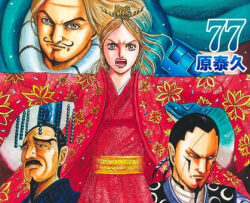トルコは、日本人に対して特別な親近感を抱く「超」親日国家として知られています。その背景には、歴史的なつながり、経済協力、そして現代文化への共感など、多岐にわたる要因が存在します。今回、日本のある高齢者が85日間にわたるトルコでの自転車旅行中に体験した数々の温かい「おもてなし」を通じて、トルコが持つ日本への深い愛情と、それが育まれた理由を深掘りします。この体験は、単なる観光の枠を超え、両国民間の絆の強さを浮き彫りにするものです。
予測不能な親切:一人旅のテントに届くトルコのおもてなし
2025年7月11日、古都ブルサから約20キロ西の地点で夕刻を迎え、小川の畔にテントを設営した日本人旅行者は、予期せぬ歓待を受けました。就寝しようとしていた矢先、近くを通りかかった二人の女性が、食料品の入った買い物袋を差し入れてくれたのです。中にはバナナ、クッキー、ポッキー、栄養ドリンク、ウェットティッシュといった、旅人に嬉しい品々が入っており、その温かい心遣いに旅行者は深く恐縮しました。
トルコでの自転車旅行中、このような地域住民からの差し入れは一度や二度ではありませんでした。ある時は、住宅地の児童公園で野営していると、公園前の邸宅の主人が早朝、トレーにトルココーヒー、卵料理、トースト、フルーツ盛り合わせを乗せて朝食を届けてくれました。また別の機会には、モスクの管理人が、庭で栽培したイチジクや、素晴らしい味わいのオリーブの漬物と共に、温かい朝食を提供してくれたこともありました。
 トルコでの自転車旅行中、テントで休憩する日本人旅行者。現地の人々から差し入れを受けた様子を想起させる。
トルコでの自転車旅行中、テントで休憩する日本人旅行者。現地の人々から差し入れを受けた様子を想起させる。
海辺の別荘地では、近くの別荘からフライドチキン、ピラフ、サラダといった夕食の差し入れがありました。この時、差し入れを持ってきた高校生の長男は、将来医師になるため猛勉強していると語り、旅行者はトルコの若者の勤勉さに触れる機会も得ました。これらの親切の背景には、当初、旅行者が不法滞在者などの不審者ではないかと警戒していた住民が、日本人であることを知ると、すぐに「親日感情」のスイッチが入り、温かい歓迎に変わるという共通のパターンが見られました。ホテルやチャイハネ(喫茶店)でも、オーナーや従業員のご厚意で、果物の盛り合わせやケーキなどを何度も差し入れてもらい、72歳という年齢で炎天下の自転車旅を続ける日本人高齢者への尊敬と応援のメッセージが込められていました。トルコの男性平均寿命が76歳であることを考えると、72歳での自転車旅行は驚異的であり、トルコ人にとっては称賛の対象となるのです。
歴史と文化が織りなす親日感情の深層:東郷、トヨタ、そしてアニメ
7月12日、ウルアバト湖畔の風光明媚なギョルヤズ村を早朝に出発し、マルマラ海の港町バンドゥルマまで12時間かけて自転車を走らせていた途中、幹線道路沿いのガソリンスタンドで、イスタンブールから来たという家族連れから声を掛けられました。日本人と知るやいなや、一家はそれぞれが日本を絶賛する会話が始まりました。
78歳の祖父は、孫の青年の通訳を通して、「トルコ人は皆日本人を尊敬している。日本海海戦でロシアのバルチック艦隊を全滅させた東郷平八郎元帥を知らないトルコ人はいない。私自身は山本五十六を大変尊敬している。彼は日本人の美徳を体現した偉大な軍人である」と熱弁をふるいました。この言葉からは、かつてオスマン帝国が宿敵としたロシアを日露戦争で打ち破った日本の軍事力が、トルコ人の誇りや共感を深く刺激した歴史的背景が伺えます。これはポーランドにおける親日感情の源泉とも類似しており、ポーランド海軍の教育課程に宮本武蔵の『五輪書』や『葉隠れ精神』、そして日露戦争の日本海海戦が必修科目とされていることからも、その影響の大きさが理解できます。
 トルコで日本人旅行者と交流する家族。日本への深い親日感情を語り合う。
トルコで日本人旅行者と交流する家族。日本への深い親日感情を語り合う。
さらに、一家の父親と青年は、日本の高い技術力を称賛し、トルコでも生産されているトヨタの自動車、特にカローラが世界一であると力説しました。長年、欧州の下請け工場としての役割を担ってきたトルコの産業人にとって、日本の優れたモノづくり技術は憧れの対象であり、経済発展への希望でもあったのです。歯科医を目指している孫娘の大学生は、現代日本のサブカルチャーへの深い理解を示し、「日本の漫画やアニメ、例えば『ワンピース』はトルコでも若者に大人気であり、単なる娯楽に留まらず、深い哲学が背景にあり、人生の指標を与えている」と語りました。このように、トルコの親日感情は、歴史的な軍事関係、高度な技術力への憧れ、そして現代の文化的な共感という、多層的な要因によって形成されていることが明らかになります。旅行者は、この家族が持参した野菜サラダ、トルコ風チーズ揚げパン、トルコ風パイを共に囲み、温かい交流を楽しみました。
トルコと日本の間に流れるこの特別な絆は、単なる表面的なものではなく、深い歴史と文化の根っこでしっかりと結ばれています。今回の一人旅の経験は、その真髄を垣間見せる貴重な機会となりました。